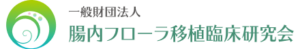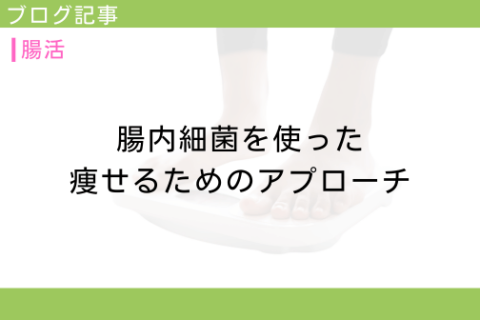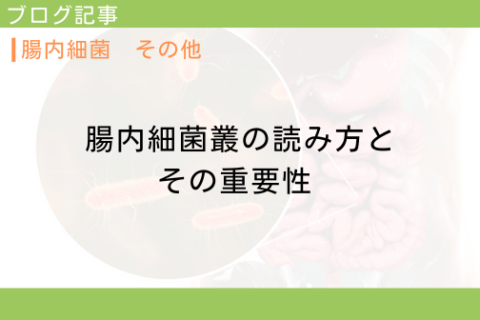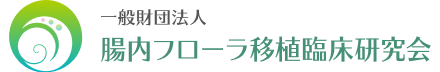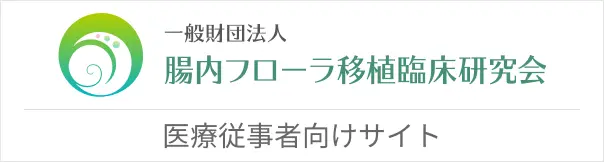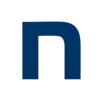腸内には約100兆個以上の細菌が存在し、日々の私たちの健康に大きな影響を与えています。健康を促進し免疫力を高める細菌、腸内環境を悪化させる細菌、また、環境によって良くも悪くもどちらにも変わりうる細菌など、様々な腸内細菌がヒトの体内で絶妙なバランスを維持しています。
腸内細菌とは
腸内細菌とは、私たちの腸の中に生息している微生物のことを指します。これらの細菌は、人間の健康や免疫機能にとって欠かせない存在です。腸内には種類豊富な細菌が共生しており、それぞれ異なる役割を果たしています。
腸内細菌の種類
腸内細菌は、主に善玉菌、悪玉菌、日和見菌の3種類に分類されます。
まず、善玉菌は腸の健康をサポートする好ましい細菌です。腸内の有害物質を抑制し、免疫機能を向上させる役割を果たします。具体的には、ビフィズス菌やラクトバチルスなどが挙げられます。
次に、悪玉菌は健康に悪影響を与える細菌で、腸内のバランスが崩れる原因となります。これらの菌が増殖すると、消化不良や便秘、さらにはアレルギーや生活習慣病に繋がることがあります。
最後に日和見菌ですが、これらは善玉菌や悪玉菌と共存し、状況に応じていずれかの役割を果たす菌です。腸内の環境によってその働きが変わるため、腸内フローラのバランスを保つことが重要になります。
と、以上のように、腸内細菌は大きく「善玉菌」「悪玉菌」「日和見菌」の3つに分類されるのですが、これはあくまで便宜上のカテゴリーです。
実際には、これらに明確に当てはまらない細菌や、状況によって性質が変わるものも存在します。例えば、ヒトの腸内で影響の大きい細菌10種には下記の様なものがあります。
ヒトの腸内で影響の大きい腸内細菌10種
1 ビフィドバクテリウム(Bifidobacterium) – 主要な善玉菌で、乳酸や酢酸を産生し腸内環境を整える。
2 ラクトバチルス(Lactobacillus) – 乳酸菌の一種で、消化を助け免疫を強化する。
3 エシェリヒア・コリ(Escherichia coli) – 大腸菌の一種で、無害なものから病原性のものまで多様。
4 バクテロイデス(Bacteroides) – 腸内の主要菌で、食物繊維を分解し短鎖脂肪酸を生成する。
5 プレボテラ(Prevotella) – 炭水化物の分解を助け、食生活によって増減する。
6 クロストリジウム(Clostridium) – 一部は有益だが、病原性のある種(C. difficileなど)も含む。
7 フェーカリバクテリウム(Faecalibacterium) – 抗炎症作用のある酪酸を産生する重要な善玉菌。
8 ルミノコッカス(Ruminococcus) – 食物繊維を分解し短鎖脂肪酸を産生する。
9 エンテロコッカス(Enterococcus) – 一部はプロバイオティクスとして有益だが、耐性菌も問題視される。
10 ストレプトコッカス(Streptococcus) – 善玉・悪玉両方の性質を持ち、口腔内にも多く存在。
これら10種には善玉菌・悪玉菌・日和見菌が混在していますが、すべての腸内細菌が3カテゴリーに明確に分類できるわけではありません。状況によって影響が変わることも多いため、腸内細菌は非常にダイナミックなものと言えます。
特に有名な、1 ビフィドバクテリウム(Bifidobacterium) 、2 ラクトバチルス(Lactobacillus)、6 クロストリジウム(Clostridium)、9 エンテロコッカス(Enterococcus)については下記にて詳しく説明します。
ビフィズス菌(Bifidobacterium)
ビフィズス菌は、腸内に存在する重要な善玉菌の一つで、特に乳児期に多く見られます。主に腸内で乳酸を生成し、腸内のpHを下げることで、悪玉菌の増殖を抑える役割を果たしています。これにより、腸内環境が整えられ、免疫力の向上にも寄与します。
また、ビフィズス菌は、消化吸収を助けるだけでなく、腸内の有害物質を排出する働きも持っています。腸内フローラのバランスを保つことで、便通を改善し、便秘や下痢を防ぐ効果が期待できます。このため、特に中高年層の方々には、積極的にビフィズス菌を含む食品を摂取することがすすめられています。
ビフィズス菌は、ヨーグルトや発酵乳製品、さらにはサプリメントとしても手軽に取り入れることができるため、日常生活に取り入れることが健康維持の一助となるでしょう。腸内環境を整えることで、全体的な健康を支える大切な存在です。
乳酸菌(Lactobacillus)
乳酸菌は、善玉菌の中でも特に有名な種類であり、私たちの腸内において重要な役割を果たしています。主に発酵食品に含まれ、代表的なものにはヨーグルトやキムチがあるため、比較的身近に感じられる存在です。
乳酸菌は、腸内で糖分を発酵させて乳酸を生成します。この乳酸が腸内のpHを下げ、悪玉菌の繁殖を抑える働きを持っています。結果として、腸内環境が整うことで、消化不良や便秘の予防に繋がります。
さらに、乳酸菌は免疫機能の向上にも寄与します。腸は「免疫の要」とも言われており、腸内に良い菌が多いと、体全体が健康を維持しやすくなります。乳酸菌を積極的に摂ることで、生活習慣病のリスクを減らす効果も期待できるのです。
なお、「乳酸菌」という言葉は広い意味で使われ、前述のビフィズス菌も乳酸を作るため乳酸菌の一種とも言えますが、厳密には ビフィズス菌(Bifidobacterium) と 乳酸菌(Lactobacillusなど) は異なる分類に属しています。
クロストリジウム(Clostridium)
クロストリジウムは、腸内に存在するグラム陽性の細菌群で、約200種以上が知られています。主に腸内に生息し、タンパク質分解酵素や発酵能力を持つため、食品の分解や栄養素の生成に関与しています。
一部のクロストリジウム属の細菌は、腸内フローラにとって重要な役割を果たします。しかしながら、特定の種類は病気を引き起こす原因にもなり得ます。特に、クロストリジウム・ディフィシルは、抗生物質の使用後に腸内バランスが崩れることで増殖し、重篤な下痢や腸炎を引き起こすことがあります。
そのため、腸内におけるクロストリジウムのバランスを保つことは非常に重要です。ヨーグルトや納豆などの発酵食品を摂取することで、腸内環境を整え、善玉菌を増やすことが推奨されます。
エンテロコッカス(Enterococcus)
エンテロコッカスは、腸内に存在する重要な善玉菌の一種です。この細菌は、特に腸の健康に寄与する役割を持っています。エンテロコッカスには、食物の消化や栄養素の吸収を助ける機能があり、腸内環境を整えるために非常に重要です。
また、エンテロコッカスは免疫機能をサポートする働きもあります。これにより、体外から侵入する病原菌に対抗し、健康な身体を保つための力を強化します。特に中高年層では、免疫力が低下しやすいため、エンテロコッカスの摂取は重要です。
さらに、エンテロコッカスはヨーグルトやヤギのチーズなどの発酵食品に多く含まれています。これらの食品を積極的に食べることによって、腸内フローラを整え、健康な生活を送る手助けになるでしょう。エンテロコッカスを通じて、腸内の善玉菌を増やすことが、健康維持には欠かせない要素です。
腸内細菌の役割
腸内細菌は、私たちの健康に欠かせない重要な役割を果たしています。
まず、消化を助け、栄養素を効果的に吸収する機能があります。特に、食物繊維を分解し短鎖脂肪酸を生成することで、エネルギー源となり、腸の運動も促進します。
また、腸内細菌は免疫機能の調整にも寄与しています。善玉菌が増えることで悪玉菌の繁殖を抑え、体内の炎症を抑える効果が期待されます。これにより、風邪やインフルエンザのリスクを軽減することも可能です。
さらに、腸内細菌はセロトニンという神経伝達物質の生成にも関与しており、メンタルヘルスの向上にもつながります。このように、腸内細菌のバランスを整えることが、心身の健康維持にとても重要です。
善玉菌の働き
善玉菌は腸内において非常に重要な役割を担っています。
まず第一に、善玉菌は消化を助ける働きがあります。特に食物繊維を分解して短鎖脂肪酸を生成することで、エネルギー源として利用され、腸の蠕動運動を促進します。これにより、便通が改善され、便秘の予防にもつながります。
さらに、善玉菌は免疫系の調整にも深く関与しています。腸内に存在する善玉菌が機能することで、体の免疫機能が強化され、外部からの病原菌に対する防御力が高まります。これにより、風邪やインフルエンザのリスクが低下し、健康維持に寄与します。
加えて、善玉菌は腸内環境のバランスを保つためにも重要です。悪玉菌が増えすぎないように抑制し、全体的な腸内フローラの健康を保つ役割も果たしています。これらの働きによって、善玉菌は私たちの健康を支えているのです。
悪玉菌の影響
悪玉菌は腸内環境に悪影響を及ぼすことがあります。これらの細菌が増えると、腸内フローラが乱れ、様々な健康問題を引き起こす可能性があります。特に、消化不良や便秘、下痢などの症状が現れることが多いです。
悪玉菌は、食べ物の分解を妨げ、栄養の吸収効率を低下させます。その結果、栄養不足や体重の減少を招くこともあります。また、悪玉菌の増殖は免疫機能を低下させ、感染症のリスクを高める要因となります。
さらに、悪玉菌が増えることで産生される有害物質が体内に蓄積し、炎症を引き起こすこともあります。これが慢性的な健康問題を引き起こし、生活習慣病のリスクを高めることに繋がります。
このように、悪玉菌の影響は多岐にわたりますので、日頃から腸内環境を意識し、バランスを保つことが重要です。善玉菌を増やす食事や、生活習慣を心がけましょう。
日和見菌とは
日和見菌とは、腸内の環境に応じて善玉菌にも悪玉菌にも変わる特性を持った細菌のことです。腸内フローラのバランスが良いときには、善玉菌として働き、有益な栄養素を吸収したり、免疫力を高めたりします。このため、日和見菌の存在は腸内環境において非常に重要です。
しかし、悪玉菌が優勢な状況では、日和見菌も悪玉菌としての役割を果たし、腸内環境をさらに悪化させる可能性があります。このように、日和見菌はその振る舞いによって腸内の健康に影響を与えるため、腸内のバランスを維持することが大切です。
日和見菌を元気に保つためには、食生活の改善が不可欠です。バランスの取れた食事を心掛け、発酵食品や食物繊維を積極的に摂取することで、腸内環境を良好に保つ手助けをすることができます。
腸内細菌と健康
腸内細菌は健康に大きく関与していることが多くの研究で明らかになっています。腸内にはビフィズス菌や乳酸菌などの善玉菌が存在し、これらは消化を助け、栄養素の吸収を促進します。また、腸内フローラが整うことで免疫機能の向上にも寄与し、感染症やアレルギーのリスクを低下させる効果が期待されます。
さらに、腸内細菌はストレスやうつ病とも関連性があります。善玉菌が豊富な腸内環境は、脳内に良い影響を与え、メンタルヘルスの維持にも役立ちます。このように、腸内環境を整えることは、身体だけでなく心の健康にも有益であると言えるでしょう。
日常生活では、食生活を見直すことで腸内細菌のバランスを整えることができます。発酵食品や食物繊維を積極的に摂取することが、腸内健康を促進し、全体的な健康状態を向上させてくれるのです。健康的な腸内環境を保つことは、質の高い生活を送るために欠かせない要素となります。
腸内環境の整え方
腸内環境を整えるためには、いくつかのポイントを意識することが重要です。まず第一に、食事の内容を見直しましょう。食物繊維を多く含む野菜や果物、豆類を積極的に摂取することで、善玉菌が育ちやすくなります。特に、発酵食品を取り入れることをお勧めします。ヨーグルトや納豆、キムチなどは、腸内の善玉菌を増やす効果があります。
次に、十分な水分補給も忘れずに行いましょう。水分は便秘の予防にもつながり、腸内の動きをスムーズにします。そして、適度な運動も腸内環境を整える鍵です。ウォーキングやストレッチなどの軽い運動で腸の動きを促進しましょう。
さらに、ストレス管理も大切です。ストレスは腸内のバランスを崩す原因となりますので、リラックスできる時間を持つことが腸内環境改善に寄与します。
つらいことや思うようにならないことを、同じ形のまま抱え続けるのではなく、いったん重い荷物は脇に置き、時には気持ちを思い切り開放させることも体の緊張を解くことにつながります。このように、日常的に自身のストレスに意識的になる、ストレスをため過ぎない、自分だけは自分を褒めてみる、などを心掛ける、それだけでも腸内環境の改善につながるでしょう。
食事と腸内環境
食事は腸内環境に大きな影響を与える要素の一つです。まず、食物繊維を豊富に含む食品の摂取が重要です。野菜や果物、穀物に含まれる食物繊維は、腸内の善玉菌のエサとなり、これを活性化させてくれます。特に、オートミールや豆類、海藻類は効果的です。
また、発酵食品を取り入れることも有効です。ヨーグルトや納豆、キムチなどは、腸内の善玉菌を増やす働きがあります。これらの食品を日常的に摂取することで、腸内のバランスを整えることができます。
さらに、加工食品や糖分の多い食事は、悪玉菌の増殖を促すため注意が必要です。これらの食品は腸内環境を悪化させる原因となりますので、控えることをお勧めします。普段なにげなく買っている食品や、ストレス発散効果の高い食品の中に、腸内環境を悪化させるものが入っていないか、意識的に食事を見直すことで、腸内環境を改善し、健康的な体を維持することができるでしょう。
ライフスタイルの重要性
ライフスタイルは腸内環境を大きく左右する要素です。日々の生活習慣が、体内の善玉菌や悪玉菌のバランスに影響を及ぼします。特に食事内容、運動、睡眠といった基本的な要素は、腸内フローラに直結しています。
まず、食事は腸内環境を整えるための基本中の基本です。ご飯、パン、麺類や、動物性脂肪や揚げ物といった、高脂肪、高糖質ばかりの食事を続けると、悪玉菌が増えやすくなるため、バランスの良い食事を心がけることが重要です。特に発酵食品や食物繊維を意識的に摂取することが効果的です。
また、適度な運動も腸内環境には欠かせません。運動をすることで、腸の蠕動運動が促進され、便通が改善されることが期待できます。例えば今日からエスカレーター、エレベーターは控え、とりあえず歩いてみる、なども良い習慣です。
さらに、質の良い睡眠も腸内環境をサポートします。毎夜10時に眠ることは難しいかもしれませんが、早めにベッドに横になるだけでも、どれほど体が疲れ消耗しているかを静かに感じることができます。ご自身を労わる時間を大切にして、十分な睡眠が脳と体の調和を保ち、ストレスを軽減することで、腸内のバランスが整いやすくなります。
このように、ライフスタイルを見直すことで、腸内環境をスムーズに整えることができ、さらには全体的な健康にもつながるのです。
加齢による腸内細菌の変化
加齢に伴い、腸内細菌のバランスが変化することが多くの研究で示されています。若い頃には善玉菌が多く、腸内環境が活発な状態ですが、年齢を重ねるにつれて、悪玉菌が増えがちです。
特に60代以降になると、腸内細菌の多様性が減少し、ビフィズス菌などの善玉菌が減少することが知られています。この変化は、消化機能の低下や免疫力の低下といった健康問題を引き起こす可能性があります。
また、加齢により食事や生活習慣が変化することも、腸内細菌のバランスに影響を与えます。高齢者は食事の偏りや運動不足がちですが、これらが腸内環境を悪化させる要因となります。日常的に腸に良い食生活を心がけることが、腸内細菌を健全に保つために重要です。
まとめ
腸内細菌は、私たちの健康にとって非常に重要な役割を果たしています。ここで紹介したように、数多くの腸内細菌が腸内に存在しますが、主として善玉菌、悪玉菌、日和見菌という三つの種類の菌が共存しており、バランスが崩れることで健康に影響を及ぼす可能性があります。
特に、中高年層は腸内環境の変化に敏感であり、消化不良や便秘、疲れやすさを感じることが多いです。これを防ぐためには善玉菌を意識して摂取し、腸内のバランスを保つことが大切です。
腸内細菌の種類にはさまざまなものが存在するため、それぞれの細菌が持つ特性や役割を理解し、自分の健康をサポートする食品を選ぶことが重要です。腸内環境を整えることで、健康で快適な生活を送るための第一歩といえるでしょう。
腸内フローラ移植臨床研究会では、抗菌薬を使わない、患者さんへの負担の少ない新しい「腸内細菌叢移植」を既に690件以上実施しています。ご自身の腸内細菌叢が分かる腸内細菌叢検査も実施しています。ご自身の腸内細菌叢の今の状態や、腸内環境を改善することにご関心のある方は、ぜひお近くのクリニックまでお気軽にお問い合わせ下さい。
参考文献
- Dominguez-Bello MG, et al. Delivery mode shapes the acquisition and structure of the initial microbiota across multiple body habitats in newborns. Proc Natl Acad Sci U S A. 2010;107(26):11971-11975. doi:10.1073/pnas.1002601107
- Boulangé CL, et al. Impact of the gut microbiota on inflammation, obesity, and metabolic disease. Genome Med. 2016;8:42. doi:10.1186/s13073-016-0303-2
- Guinane CM, et al. Role of the gut microbiota in health and chronic gastrointestinal disease: understanding a hidden metabolic organ. Therap Adv Gastroenterol. 2013;6(4):295-308. doi:10.1177/1756283X13482996
- Tewari N, et al. Navigating commensal dysbiosis: Gastrointestinal host-pathogen interplay orchestrating opportunistic infections. Microbiol Res. 2024;286:127832. doi:10.1016/j.micres.2024.127832
- Hou K, et al. Microbiota in health and diseases. Signal Transduct Target Ther. 2022;7(1):135. doi:10.1038/s41392-022-00974-4
- Nagata S, et al. Effect of Oral Administration of Lactobacillus on the Immune Function of Elderly Adults. Clin Diagn Lab Immunol. 2015;12(5):674-679. PMID:1614816
- Yasuda K, et al. Infant Intestinal Microbiota Prevention of Allergic Diseases: Food Allergy and Atopic Dermatitis. Allergol Int. 2017;66(4):515-522. doi:10.1016/j.alit.2017.08.005
- Takeda T, et al. Usefulness of Bifidobacterium longum BB536 in Elderly Individuals With Chronic Constipation: A Randomized Controlled Trial. Am J Gastroenterol. 2023;118(3):561-568. doi:10.14309/ajg.0000000000002028
- Kurokawa S, et al. Intestinal microbiota features of healthy Japanese adults in relation to centenarian lifestyles. J Clin Biochem Nutr. 2017;61(3):217-221. doi:10.3164/jcbn.17-41
- Wu GD, et al. Linking long-term dietary patterns with gut microbial enterotypes. Science. 2011;334(6052):105-108. doi:10.1126/science.1208344
- Wastyk HC, et al. Gut-microbiota-targeted diets modulate human immune status. Cell. 2021;184(16):4137-4153.e14. doi:10.1016/j.cell.2021.06.019
- Sokol H, et al. Faecalibacterium prausnitzii is an anti-inflammatory commensal bacterium identified by gut microbiota analysis of Crohn disease patients. Proc Natl Acad Sci U S A. 2008;105(43):16731-16736. doi:10.1073/pnas.0804812105
- Yano JM, et al. Indigenous bacteria from the gut microbiota regulate host serotonin biosynthesis. Cell. 2015;161(2):264-276. doi:10.1016/j.cell.2015.02.047
- Van Nood E, et al. Duodenal infusion of donor feces for recurrent Clostridium difficile infection. N Engl J Med. 2013;368(5):407-415. doi:10.1056/NEJMoa1205037
- Allen JM, et al. Exercise Modifies the Gut Microbiota with Positive Health Effects. Oxid Med Cell Longev. 2018;2018:38317. doi:10.1155/2018/38317
監修者:農学博士 嶋秀明(シンバイオシス株式会社)
公開日:2025年5月27日