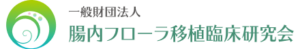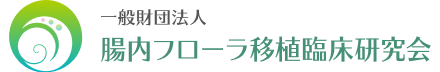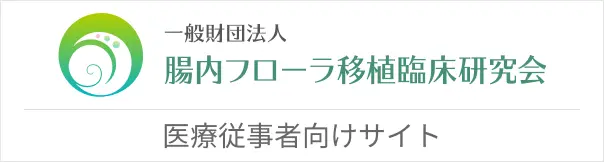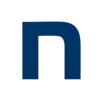腸内細菌の研究で第一人者として知られる國澤純先生が、腸内フローラと健康の深い関係について語る、注目の学術大会を2025年9月21日(日)に開催しました。

テレビ番組「林修の今でしょ!」でもおなじみの國澤先生が登壇される腸内フローラ移植臨床研究会 第9回学術大会は、腸内細菌と最先端医療に関心を持つ医療従事者の方のみならず、一般の方にもご参加いただきました。
本記事では、その國澤先生の研究と見解に基づいて、腸内細菌の基礎から最新の応用、そして個別化栄養への可能性までを分かりやすくご紹介します。
腸内細菌が健康を左右する理由とは?
腸内細菌とは何か?その基本を理解する
腸内細菌とは、私たちの腸内に棲む無数の微生物の総称です。
腸内環境は、数百種類以上の細菌から構成され、その数は人体の細胞数を超えるとも言われています。
これらの細菌は消化を助けたり、ビタミンを合成したり、免疫を調整するなど、健康の維持に欠かせない働きをしています。
例えば國澤先生の著書『9000人を調べて分かった腸のすごい世界』では、「腸内細菌は“スーパー生命体”であり、“共生者”といえる存在である」と述べられており、その重要性が強調されています。
私たちの健康状態は、腸内細菌の多様性とバランスによって左右されるのです。
腸内細菌が健康に与える影響とは
國澤先生によると、腸内細菌は単なる“消化の補助役”ではなく、全身の健康に深く関与している存在です。
私たちの体は、腸で吸収される栄養素だけでなく、腸内細菌が生み出すさまざまな物質にも影響を受けています。
そのため、腸の状態が良いか悪いかは、意外にも「全身」の健康状態にまで波及していくのです。
実際に、腸内環境の乱れ(腸内フローラのバランスの崩れ)は、肥満、糖尿病、アレルギー、がん、そしてメンタルヘルスなど、さまざまな疾患と関連があることが明らかになっています。
これは、腸内でつくられる代謝産物が血流に乗って肝臓や脳に届き、全身の代謝や行動、さらには感情にまで影響を与えるためです。
こうした背景から、國澤先生は「腸内細菌を整えることが、病気予防の第一歩になる」と語っています。
腸内細菌が免疫を左右する仕組み
腸内環境と免疫機能の間には密接な関係があり、腸内フローラのバランスが免疫力の鍵を握っているとされています。
國澤純先生の研究でも、腸管に集中する免疫細胞が腸内細菌の刺激によって活性化されたり、炎症を抑える調整機構が働いたりすることが明らかになっています。
腸内細菌が私たちの健康に与える影響は多岐にわたりますが、その働きの一つに「代謝産物の生成」があります。
これらの代謝産物の中には、免疫機能の調整に重要な役割を果たすものも含まれています。
たとえば、酪酸を産生する腸内細菌は、大腸の上皮細胞を健康に保つ役割があります。
酪酸は、腸のエネルギー源として使われ、上皮細胞の増殖を促したり、腸のバリア機能を強化したりすることで、病原菌の侵入を防ぐ“門番”のような働きをしてくれます。
さらに、酪酸には免疫系の過剰反応を抑える働きもあります。
たとえば、炎症を引き起こす免疫細胞の活性をコントロールしたり、炎症を抑える制御性T細胞の働きを助けたりすることで、アレルギーや自己免疫反応の暴走を防いでくれるのです。
國澤純先生の著書『強い体と菌をめぐる知的冒険』では、アレルギーや自己免疫疾患と腸内細菌の構成に関連がある事例が紹介されており、腸内環境を整えることは“体を守る力”の底上げにつながるとされています。
腸内環境を整えるための食生活
腸内細菌を育てる食材とは
國澤先生は、「食事は腸内細菌との対話である」とし、日常の食生活の中で意識的に腸内細菌に“良い餌”を与える重要性を強調しています。
「腸内細菌を育てる」とは、腸内にすでに棲んでいる善玉菌を増やし、活発に働ける状態をサポートすることを意味します。
つまり、私たちが何を食べるかによって、腸内の細菌たちの“顔ぶれ”や“元気度”が大きく変わるのです。
菌が元気になると、より多くの有用な代謝物をつくってくれるようになります。
良い餌のひとつに、食物繊維があります。
食物繊維が豊富な野菜や海藻、発酵食品(味噌、納豆、ヨーグルトなど)は腸内の善玉菌を育てる代表的な食品です。
特にプレバイオティクス(善玉菌のエサ)となるオリゴ糖やレジスタントスターチは重要な役割を果たします。
例えば、バナナ、ゴボウ、大麦、玉ねぎなどはオリゴ糖を多く含み、善玉菌の増殖をサポートします。
さらに、発酵食品に含まれるプロバイオティクス(善玉菌そのもの)との組み合わせにより、腸内フローラの改善効果がより高まります。
避けるべき食習慣とその理由
國澤先生は、「普段の食習慣が腸内環境を決める」、「健康的な腸内環境の維持には日々の積み重ねが重要だ」と強調しています。
とくに、加工食品や高脂肪・高糖質を多くとる食生活は、悪玉菌の増加や炎症性腸疾患のリスクを高めると警鐘を鳴らしています。
具体的には、清涼飲料水やスナック菓子、揚げ物ばかりを摂取していると、腸内で有害物質を発生させる菌が増え、炎症を引き起こす可能性があると指摘しています。
また、食物繊維不足は腸の粘膜バリアを弱める要因ともなります。
食物繊維の摂り方とその重要性
腸内細菌にとって最も重要な栄養素の一つが「食物繊維」です。
特に水溶性食物繊維は、腸内の善玉菌を育てるための“エサ”となり、短鎖脂肪酸の生成を助けます。
國澤先生は、日々の食事にゴボウ、大麦、海藻、納豆など多様な食物繊維を取り入れることを推奨しています。
とはいえ、特定の食材ばかりに偏るのではなく、根菜類や豆類、果物、海藻などをバランスよく“毎日少しずつ”取り入れるのが理想的です。
一方で、パンや肉中心の外食、インスタント食品ばかりの生活では、ほとんど食物繊維がとれていないケースも多く、自覚がないまま腸内環境を乱してしまっていることもあります。
現代人の食生活では不足しがちなため、意識的な摂取が不可欠であり、それが健康の基盤づくりとなるのです。
短鎖脂肪酸がもたらす多彩な健康効果
短鎖脂肪酸(SCFA:Short Chain Fatty Acids)とは、腸内細菌が食物繊維を発酵させることでつくり出す代謝産物です。
短鎖脂肪酸という単語、聞きなれないかもしれませんが、腸内細菌を語る際には非常に重要なワードなのです。
代表的なものに、酪酸・酢酸・プロピオン酸があります。
酪酸は、腸のエネルギー源となり腸壁のバリア機能を保つ働きがあり、酢酸は抗菌作用や脂質代謝の調整に関与します。
プロピオン酸は肝臓での糖代謝に関わり、血糖値のコントロールにも影響を及ぼすとされています。
こうした短鎖脂肪酸は、腸内のpHを弱酸性に保ち、悪玉菌の増殖を抑えるとともに、炎症を抑えたり、腸内の粘膜を強くする働きもあります。
さらに、SCFAは腸から吸収されて血流に乗り、脳や肝臓など全身の臓器にも作用することが分かってきました。
たとえば、メンタルヘルスの改善や代謝異常の予防、さらには一部のがんリスクの低下など、多彩な健康効果が期待されています。
國澤先生は、これらのSCFAの濃度を測定することで、腸内環境の“今の健康度”を数値でとらえられるようになる可能性を示唆しています。
腸内細菌とメンタルヘルスの関係
腸内細菌が心に与える影響
腸内と脳は「腸脳相関」と呼ばれる密接なネットワークでつながっています。
國澤先生の研究では、特定の腸内細菌がセロトニンやドーパミンなどの神経伝達物質の分泌に影響することが示されています。
つまり、腸の状態が気分や精神状態に影響を及ぼす可能性があるのです。
たとえば、うつ傾向のある人では特定の腸内細菌――たとえばビフィズス菌やラクトバチルス菌など――が著しく減っているという報告もあり、腸内環境の整備が心の安定につながるという新たな視点が注目されています。
これらの善玉菌は、セロトニンの前駆物質であるトリプトファンの代謝や、炎症性サイトカインの抑制に関与しており、精神的な安定に一役買っています。
しかしストレスの多い生活、加工食品中心の食事、抗生物質の使用などによって、こうした有用菌が減少してしまうと、腸内バランスが乱れ、結果として脳にもマイナスの影響が及ぶと考えられています。
最近では、うつ病の治療や予防の一環として、腸内環境の改善を取り入れる「精神腸相関ケア」も研究され始めています。
ストレスと腸内環境の相互作用
國澤先生は「心の健康を守るためにも腸を整えることが重要」と述べています。
『強い体と菌をめぐる知的冒険』では、ストレス下で腸内環境が変化しやすいこと、また善玉菌がセロトニン経路を活性化することでストレス反応を抑制できる可能性があると紹介されています。
つまり、ストレスによって腸内のバリア機能が低下し、有害菌が増殖することがある一方で、腸内環境が整うとストレス耐性が高まる、ということです。
腸と心のつながりを理解することは、現代人にとって必須の教養とも言えるでしょう。
腸内細菌研究の最前線
最新の研究成果とその応用
近年の腸内細菌研究は、単なる細菌の分類から、機能の理解と応用へと進化しています。
國澤純先生の研究チームは、最新のメタゲノム解析や多層的オミクス解析を駆使し、腸内フローラがどのように私たちの代謝、免疫、さらには脳機能と関わるのかを解明しています。
これにより、たとえば腸内細菌の特定パターンが血糖コントロールや免疫反応の強さに関与していることが分かってきました。
こうした知見は、疾病予防やパーソナライズド医療の基礎となり、今後の食事指導や治療法に大きな影響を与えると期待されています。
菌のリレー、健康をつなぐマイクロバイオータの旅
「菌のリレー」とは、腸内におけるさまざまな菌の“役割のバトンパス”のような働きを指します。
國澤先生は、『9000人を調べて分かった腸のすごい世界』の中で、“菌同士の連携”がうまくいくかどうかが腸内環境のカギになると述べています。
具体的には、食物繊維を分解して糖を作りだす「糖化菌」がまず働きます。
その後に乳酸菌が乳酸を、ビフィズス菌は乳酸と短鎖脂肪酸の酢酸を生み出し、そしてまた別の菌の働きによって酪酸などが生み出される、という菌のリレーをつなげ、、菌は腸内で助け合って生きている、ということなのです。
(菌のリレーに興味のある方はぜひ、『9000人を調べて分かった腸のすごい世界』を読んでみて下さいね。)
腸内細菌とお薬手帳
腸内環境は、日々の食事だけでなく、薬の影響も大きく受けています。
特に抗生物質は、感染症の原因となる悪玉菌を退治する一方で、腸内の善玉菌まで一緒に減らしてしまうため、服用後もしばらく腸内細菌のバランスに影響が残ることがあります。
國澤先生の研究でも、薬の使用履歴と腸内細菌の構成との関連性に注目が集まっています。
たとえば、ある種の腸内細菌が薬の成分を分解してしまい、薬の効き目に個人差が生じるケースがあることが分かってきました。
こうした知見は、将来的に「この菌を持っている人には、別の薬の方が有効かもしれない」といった、個別化医療の発展にもつながる可能性があります。
今後は、お薬手帳のように腸内環境のデータを記録し、より適切な処方につなげる取り組みが進むかもしれません。
ポストバイオティクスの可能性
ポストバイオティクスとは、死菌やその代謝産物が体に良い影響を与えるという新しい視点です。
國澤先生の研究によると、死菌であってもその細胞壁成分や生成した酪酸などが腸管免疫を活性化し、炎症を抑制することが可能です。
これは、加熱処理された乳酸菌入り食品や、プロバイオティクスとは異なる新しい機能性食品の開発にもつながる概念であり、今後の医療や栄養補助の新潮流として期待が寄せられています
腸内環境の可視化が切り拓く新たな健康医療
精密栄養学と個別化栄養の時代へ
國澤先生は、腸内細菌プロファイルに基づいて食事内容を最適化する「精密栄養学」の重要性を提唱しています。
『9000人を調べて分かった腸のすごい世界』では、同じ食べ物でも人によって血糖値の上がり方が異なることが紹介されており、これが栄養指導のパーソナライズ化を進める大きなヒントになるとされています。
腸内フローラの構成によって、食物の吸収や代謝に差が生まれ、健康への影響も異なる、と分かってきたため、もはや“一律の栄養指導”ではなく、個々人の腸内環境に応じた食事設計が求められる時代となっているのです。
腸内環境の可視化と新たな健康医療
腸内細菌が私たちの健康に与える影響がますます明らかになる中、今後どのように「腸内環境の状態」を見える化し、活用していけるのか――。
2025年9月21日(日)、リーガロイヤルホテル大阪にて開催した、腸内フローラ移植臨床研究会 第9回学術大会にて、國澤先生が「腸内環境の可視化が切り拓く新たな健康医療の可能性」と題して基調講演に登壇いただきました。

本大会は多くの皆さまにご参加いただき、盛況のうちに無事終了いたしました。
現在は【アーカイブ配信】のお申込みを受け付けております。
当日ご参加が叶わなかった方も、ぜひこの機会に最新の知見をご視聴ください。
腸内環境の可視化は、これまで“ブラックボックス”だった健康の鍵を明らかにし、未来の医療を根底から変える可能性を秘めています。
國澤先生の講演を聞けるまたとない機会です。ぜひお申込みください。
よくある質問(Q&A)
Q1. 腸内環境を整えるには、どれくらいの期間がかかりますか?
腸内環境の改善には個人差がありますが、2週間〜3ヶ月程度で変化が見られることが多いです。
食事を見直し、継続的に発酵食品や食物繊維を取り入れることが大切です。
Q2. プロバイオティクスやサプリメントは本当に効果がありますか?
一部のプロバイオティクスやサプリメントには臨床的な効果が認められているものもあります。
ただし、人によって合う・合わないがあるため、効果が感じられない場合は製品を変えるか、自然食品からの摂取を重視しましょう。
Q3. 腸内細菌はどうやって調べることができますか?
現在は民間の腸内フローラ検査キットを使うことで、自宅でも簡単に腸内細菌のバランスや多様性を知ることができます。
こうした検査と医療の連携が近年注目されています。
Q4. 子どもや高齢者でも腸内環境を整えることは重要ですか?
非常に重要です。
子どもの腸内環境は将来の健康を左右し、高齢者にとっては免疫力や認知機能の維持に関わります。
年齢に応じた食生活で腸をケアしましょう。
Q5. ストレスで腸内環境が悪くなるって本当ですか?
はい、本当です。
強いストレスは腸のバリア機能を低下させ、有害菌の増加につながることがあります。
逆に、腸内環境を整えることでストレス耐性が高まるという研究もあります。
参考文献
1. 國澤純 『9000人を調べて分かった腸のすごい世界 ― 強い体と菌をめぐる知的冒険』
2. 國澤純 『「善玉酵素」で腸内革命』
3. Sender R, Fuchs S, Milo R. Revised estimates for the number of human and bacteria cells in the body. PLoS Biol. 2016;14(8):e1002533. doi:10.1371/journal.pbio.1002533
4. Hosomi K, Saito M, Park J, Kunisawa J, et al. Oral administration of Blautia wexlerae ameliorates obesity and type 2 diabetes via metabolic remodeling of the gut microbiota. Nat Commun. 2022;13:4477. doi:10.1038/s41467-022-32015-7
5. Furusawa Y, Obata Y, Fukuda S, et al. Commensal microbe-derived butyrate induces the differentiation of colonic regulatory T cells. Nature 2013;504:446-450. doi:10.1038/nature12721
6. Nagatake T, Kunisawa J, Arita M, et al. Dietary ω-3 fatty acid exerts anti-allergic effect through conversion to 17,18-epoxyeicosatetraenoic acid in the gut. Sci Rep. 2015;5:9750. doi:10.1038/srep09750
7. Taitz JJ, Tan J, Ni D, et al. Antibiotic-mediated dysbiosis leads to activation of inflammatory pathways. Front Immunol. 2024;15:1493991. doi:10.3389/fimmu.2024.1493991
8. Ryan FJ, Clarke M, Lynn MA, et al. Bifidobacteria support optimal infant vaccine responses. Nature 2025;641:456-464. doi:10.1038/s41586-025-08796-4
9. Schaub AC, Schneider E, Vazquez-Castellanos JF, et al. Clinical, gut microbial and neural effects of a probiotic add-on therapy in depressed patients: a randomized controlled trial. Transl Psychiatry 2022;12:227. doi:10.1038/s41398-022-01977-z
10. Tanabe M, Kunisawa K, Saito I, et al. High-cellulose diet ameliorates cognitive impairment by modulating gut microbiota and metabolic pathways in mice. J Nutr. 2025;155(6):1689-1699. doi:10.1016/j.tjnut.2025.04.004
11. Mutoh N, Kakiuchi I, Hiraku A, et al. Heat-killed Lactobacillus helveticus improves mood states: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Benef Microbes 2023;14(2):109-118. doi:10.3920/BM2022.0048
12. Bermingham KM, Linenberg I, Polidori L, et al. Effects of a personalized nutrition program on cardiometabolic health: a randomized controlled trial. Nat Med. 2024;30:1888-1897. doi:10.1038/s41591-024-02951-6
監修者:農学博士 嶋秀明(シンバイオシス株式会社)
公開日:2025年6月25日
更新日:2025年10月15日