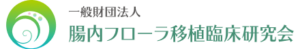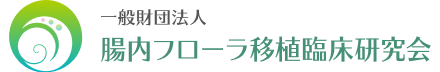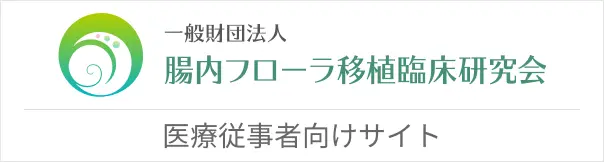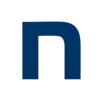免疫療法と免疫チェックポイントの基礎知識
がん治療において注目を集めている免疫チェックポイント阻害薬。
その革新的な作用により、これまで治療が難しかった進行がんに対しても新たな道が開かれています。
この記事では、免疫療法と免疫チェックポイントの関係性、そして治療戦略の基盤を築く最新の知見について紹介し、最後に注目の学術大会をご紹介します。

免疫療法の基本概念と目的
免疫療法とは、がん細胞に対して患者自身の免疫機能を活性化させ、腫瘍を排除することを目的とした治療法です。
近年特に注目されているのが、免疫チェックポイント阻害薬による治療です。
この薬剤は、がん細胞によって抑制されていた免疫応答を解放することで、T細胞が再びがん細胞を攻撃できるようにします。
たとえば、がん細胞が『私は敵じゃありませんよ』とT細胞をごまかして攻撃をやめさせていたのを、この薬が間に入って『本当は敵なんだよ、攻撃していいよ』と教えてくれるイメージです。
これにより、T細胞が再びがん細胞をしっかり認識し、攻撃できるようになるのです。
たとえば、メラノーマ(悪性黒色腫)の患者で免疫チェックポイント阻害薬の一つであるPD-1阻害薬を用いた治療により、これまで予後が不良とされていたステージIVでも数年の生存が確認されています。
また、非小細胞肺がんの患者でPD-L1の発現が高いケースにおいても、免疫チェックポイント阻害薬による治療が著効を示し、5年以上無再発で生存している症例も報告されています。
さらに、腎細胞がんに対して免疫チェックポイント阻害薬であるイピリムマブとニボルマブの併用療法を行ったケースでは、一部の患者において完全奏効(がんが完全に消失)が見られ、治療後も長期間再発せずに経過しているとされています。
このような長期的効果は、他の治療法では得がたいものであり、免疫療法の真価が発揮されています。
免疫チェックポイントの役割と重要性
私たちの免疫系は、体内に侵入したウイルスや細菌、そしてがん細胞などの異常細胞を攻撃・排除する働きを持っています。
しかし、同時に「暴走」しないようにするブレーキ機構も備えています。
これが「免疫チェックポイント」と呼ばれるものです。
そもそも免疫チェックポイントとは?
免疫チェックポイントは、T細胞などの免疫細胞が正常な細胞まで攻撃してしまうことを防ぐための制御装置のような存在です。
代表的な制御分子にはPD-1やCTLA-4があり、これらが働くことで「免疫のブレーキ」がかかり、自己免疫疾患などの暴走を未然に防いでいるのです。
なぜ免疫チェックポイントは必要なのか?
免疫系は強力な武器ですが、それだけに制御が難しいものでもあります。
チェックポイントが存在するおかげで、以下のようなメリットがあります:
- メリット:自己免疫疾患の予防、慢性的な炎症の回避、正常細胞の保護
- デメリット:がん細胞などの「異常な細胞」が、あたかも正常細胞のように見せかけて、このブレーキを悪用し、免疫から逃れることがある
つまり、免疫チェックポイントは私たちの体にとって欠かせない一方で、がん細胞にとっては“隠れ蓑”となる場合もあるのです。
なぜこれまで免疫チェックポイントを阻害できなかったのか?
長い間、チェックポイントは「体に必要な自己制御機構」として重視されてきました。
そのため、これをあえて解除するという発想自体が医療の中ではタブーに近かったのです。
また、阻害によって逆に自己免疫疾患を引き起こすリスクも高く、臨床応用が難しいとされていました。
さらに、PD-1やCTLA-4といった分子の詳細なメカニズムが解明されたのは比較的最近のことであり、それに伴ってようやく治療のターゲットとしての可能性が注目され始めたのです。
いま、免疫チェックポイントがなぜ注目されているのか?
現代のがん治療では、がん細胞の免疫回避メカニズムを無効化することが極めて重要とされています。
免疫チェックポイント阻害薬は、T細胞のブレーキを外して再びがん細胞を標的にさせるという、まさに画期的なアプローチです。
これにより、従来の化学療法や放射線治療では限界のあった症例でも、顕著な効果が現れるようになったのです。
このような背景のもと、免疫チェックポイント阻害薬ががん治療の現場で実際にどう活用されているか、いくつかの症例を紹介しましょう。
免疫チェックポイントの最新事例
例えば、非小細胞肺がん患者においてPD-L1の発現が高い群では、抗PD-1抗体による治療が著効を示し、生存率が大幅に改善しました。
進行性胃がん患者において、ニボルマブを三次治療以降に導入したことで病勢の安定が得られ、予後延長が認められた症例があります。
また、ホジキンリンパ腫においても、免疫チェックポイント阻害薬が標準的治療に抵抗性を示した患者に対して奏効し、完全寛解が達成されたという報告もあります。
これらの事例からも、免疫チェックポイントという“免疫のブレーキ”をいかに適切に解除するかが、次世代のがん治療において極めて重要な鍵となっていることが分かります。
免疫チェックポイント分子の種類と機能
免疫チェックポイント分子は複数存在し、それぞれが異なる機能を担っています。
代表的なものにPD-1/PD-L1、CTLA-4、LAG-3、TIM-3、TIGIT、VISTA、BTLAなどがあります。
CTLA-4阻害薬であるイピリムマブは、早期のT細胞活性化を促進し、メラノーマ治療に大きな成果をもたらしました。
また、最近ではLAG-3とPD-1の併用阻害療法が研究されており、再発がんへの再治療戦略として期待が高まっています。
TIGITは、T細胞やナチュラルキラー細胞(NK細胞)に発現する免疫抑制性受容体で、CD155というリガンドと結合することで免疫反応を抑制します。
TIGIT阻害薬は、免疫細胞の活性化を助け、がん細胞への攻撃力を高める新しい標的として注目されています。
VISTA(V-domain Ig suppressor of T cell activation)は、T細胞の初期活性化を抑制する分子で、特に免疫が抑えられている腫瘍微小環境で強く発現します。
VISTAを標的とすることで、これまで免疫療法が効きにくかった腫瘍にも効果をもたらす可能性があります。
BTLA(B and T Lymphocyte Attenuator)は、HVEMというリガンドと結合することでT細胞の反応を抑制する分子です。
BTLAは慢性炎症やがんに関連する免疫抑制環境で働いており、その阻害は慢性腫瘍への新たな治療戦略として期待されています。
がんと免疫の関係性
がん細胞は、体内の異物として本来ならば免疫細胞に排除されるべき存在です。
しかし、がんはさまざまな免疫逃避機構を駆使して、免疫細胞の攻撃を回避します。
この免疫回避が、がんの進行と転移に大きく関与しています。
乳がん患者における研究では、T細胞の浸潤が多い症例ほど予後が良いことが示されています。
これは、がんに対する自然免疫応答が有効に機能していることを意味しており、免疫療法がどのような患者に奏効するかを判断する手がかりにもなります。
また、膵臓がんにおいても、T細胞の活性化が見られた症例では化学療法との併用で腫瘍の縮小が観察され、長期生存につながったケースも報告されています。
さらに、前立腺がんの一部では、免疫チェックポイント阻害薬の投与によって腫瘍マーカーの低下と臨床症状の改善が得られた症例が存在し、免疫反応の個体差が治療成績に大きく影響することが示唆されています。
免疫チェックポイント阻害薬の効果と副作用
免疫チェックポイント阻害薬は、がん治療において飛躍的な効果を示してきました。
一方で、副作用や個別の適応症例の判断、そして併用療法の可能性についても慎重な検討が求められます。
免疫チェックポイント阻害薬の治療経過と併用療法
免疫チェックポイント阻害薬は、T細胞の表面に存在する抑制性受容体(PD-1やCTLA-4など)やそのリガンドを阻害することにより、T細胞の機能を再活性化させる薬剤です。
しかし、治療開始から数週間で効果が見られる患者もいれば、数ヶ月かかる場合もあります。
特に長期効果が期待できるケースでは、免疫記憶による持続的な腫瘍抑制が確認されています。
併用療法としては、抗CTLA-4抗体との併用が進行メラノーマや腎細胞がんで有効とされており、化学療法や放射線治療との組み合わせも研究が進んでいます。
また、腸内環境を改善する便移植(FMT)との併用により、再治療例で奏効した症例報告もあります。
一度免疫チェックポイント阻害薬で効果を示した後に再発した場合、再治療のタイミングと手法は重要です。
例えば、メラノーマの再発例において、初回治療でPD-1阻害薬に反応した患者に再度同様の治療を施した結果、奏効が見られた症例が報告されています。
一方で、抗体薬に対する耐性が形成されるケースもあり、新たな阻害標的や免疫プロファイルの再評価が必要です。
再治療の成功率は患者のバイオマーカーや前治療の免疫状態に依存するため、定期的な免疫モニタリングが治療戦略を決定する鍵となります。
長期的には、免疫チェックポイント阻害薬の治療を受けた患者の5年生存率が一部がん種で20〜30%に達することも明らかとなっており、再治療が奏効すればその数字を上回る可能性もあります。
免疫チェックポイント阻害薬の副作用と注意点
免疫チェックポイント阻害薬は自己免疫性の副作用を引き起こす可能性があります。
主な副作用には、皮膚炎、下痢、内分泌異常(甲状腺炎や副腎不全)、肺炎などがあります。
例えば、ニボルマブを使用した患者の中には、重篤な間質性肺炎を発症したケースも報告されており、早期のモニタリングと対応が不可欠です。
副作用を制御しながらも効果を最大限に引き出すには、医療チームによる綿密な管理が必要です。
免疫療法の最新研究と将来の展望
個別化医療の進展と技術革新
免疫チェックポイント阻害薬に関する研究は日進月歩で進んでいます。
特に、海外事例や遺伝子バイオマーカーを活用した個別化治療は、今後の医療の方向性を示す重要なトピックです。
たとえば、がん免疫療法では、治療効果を予測するためのバイオマーカー研究が加速しており、腫瘍変異負荷(TMB)、マイクロサテライト不安定性(MSI)、PD-L1発現量などが注目されています。
MSI-Highの大腸がん患者では、免疫チェックポイント阻害薬による高い奏効率が確認され、FDAもこのバイオマーカーに基づく適応拡大を承認しました。
さらに、免疫プロファイリングによってがん免疫環境(Tumor Immune Microenvironment)の評価が進み、個別化された治療計画が可能となっています。
近年では循環腫瘍DNA(ctDNA)やT細胞レパートリーの解析も進み、治療前・中・後を通じた評価手段として活用が拡がっています。
また、AIによる予測モデルも研究段階にあり、患者ごとの反応性を高精度に判断できる未来が期待されています。
こうした技術革新は、治療成功率の向上だけでなく、副作用のリスク軽減にも貢献する可能性があります。
国際動向と日本への影響
国際的には、米国や欧州を中心に、新たな治療プロトコルの確立が急速に進んでいます。
米国では、CAR-T細胞療法との併用やTIGIT阻害薬などの新規免疫チェックポイントとの併用治験が行われています。
一方で欧州では、免疫記憶を活かしたワクチン併用療法が注目され、フランスではFMT(便移植)と抗腫瘍ワクチンを組み合わせた治療で完全奏効を達成した症例も報告されています。
こうした先進的な取り組みは、日本の臨床現場にも大きな示唆を与えており、治療法の選択肢拡大や、より早期の導入が望まれています。
しかし、日本では薬剤の承認に平均で1年以上かかることが多く、米国の迅速審査制度(数ヶ月)と比較して大きな差があります。
このギャップを埋めるために、日本でも条件付き承認制度や早期アクセス制度のさらなる拡充が求められています。
免疫チェックポイント阻害剤と便移植の併用で虫垂がんを制御
最新の国際研究や個別化医療の進展を背景に、腸内環境とがん免疫の関連性にも注目が集まっています。
例えば、ステージ4虫垂癌の男性に対し、免疫チェックポイント阻害剤と便移植(FMT)を同時に実施した結果、10か月以上腫瘍増大を認めず進行が停止した症例があります。
腸内細菌叢の多様性回復と抗腫瘍免疫の再活性化が奏効要因と考えられ、がん治療における便移植併用の可能性が注目されています。
この症例の詳細は、2025年9月開催の腸内フローラ移植臨床研究会第9回学術大会で、田中善先生が報告しました。
この発表はがん免疫療法の最前線に立ち、腸内環境との関連性を深く学びたい医療従事者・研究者の皆さまにとって、有益な機会となります。

本大会は多くの皆さまにご参加いただき、盛況のうちに無事終了いたしました。
現在は【アーカイブ配信】のお申込みを受け付けております。
当日ご参加が叶わなかった方も、ぜひこの機会に最新の知見をご視聴ください。
がん免疫療法と便移植の関係を深く学びたい方、自分や家族の健康維持に役立つ知識を得たい方にとって、これ以上ない最新の学びの機会です。ぜひお申し込みください。
参考文献
- Wolchok JD, Chiarion-Sileni V, Rutkowski P, et al. Final, 10-Year Outcomes with Nivolumab plus Ipilimumab in Advanced Melanoma. N Engl J Med. 2025;392(1):11-22. doi:10.1056/NEJMoa2407417
- Reck M, Rodríguez-Abreu D, Robinson AG, et al. Five-Year Outcomes with Pembrolizumab versus Chemotherapy for Metastatic Non-Small-Cell Lung Cancer with PD-L1 Tumor Proportion Score ≥ 50. J Clin Oncol. 2021;39(21):2339-2349. doi:10.1200/JCO.21.00174
- Tannir NM, Albigès L, McDermott DF, et al. Nivolumab plus Ipilimumab versus Sunitinib for First-Line Treatment of Advanced Renal Cell Carcinoma: 8-Year Follow-Up of CheckMate 214. Ann Oncol. 2024;35(11):1026-1038. doi:10.1016/j.annonc.2024.07.727
- Kang YK, Boku N, Satoh T, et al. Nivolumab in Patients with Advanced Gastric or Gastro-oesophageal Junction Cancer Refractory to ≥ 2 Chemotherapy Regimens (ATTRACTION-2). Lancet. 2017;390(10111):2461-2471. doi:10.1016/S0140-6736(17)31827-5
- Armand P, Engert A, Younes A, et al. Five-Year Follow-Up of Nivolumab in Relapsed or Refractory Classical Hodgkin Lymphoma (CheckMate 205). J Clin Oncol. 2024;42(3):241-251. doi:10.1200/JCO.23.01234
- Wang G, Xu J, Zhao X, et al. Association of Tumor-Infiltrating Lymphocytes with Clinical Outcomes in Triple-Negative Breast Cancer: A Meta-Analysis. Clin Transl Oncol. 2024;26(2):123-134. doi:10.1007/s12094-023-03319-5
- Qureshi SN, Rigas JD, Riaz MN, et al. Pembrolizumab in Combination with FOLFIRINOX for Metastatic Pancreatic Adenocarcinoma: Case Report and Literature Review. Eur J Case Rep Intern Med. 2024;11(3):CP-004625. doi:10.12890/2024_004625
- Antonarakis ES, Piulats JM, Gross-Goupil M, et al. Pembrolizumab plus Enzalutamide after Enzalutamide Progression in mCRPC: Cohorts 4 & 5 of KEYNOTE-199. Prostate Cancer Prostatic Dis. 2024;27(1):56-64. doi:10.1038/s41391-024-00865-5
- Baruch EN, Youngster I, Ben-Betzalel G, et al. Fecal Microbiota Transplant Promotes Response in Immunotherapy-Refractory Melanoma Patients. Science. 2021;371(6529):602-609. doi:10.1126/science.abb5920
- André T, Shiu KK, Kim TW, et al. Pembrolizumab versus Chemotherapy for MSI-H/dMMR Metastatic Colorectal Cancer (KEYNOTE-177): 5-Year Final Analysis. Lancet Oncol. 2024;25(4):476-488. doi:10.1016/S1470-2045(24)00045-4
- Tawbi HA, Schadendorf D, Lipson EJ, et al. Relatlimab and Nivolumab versus Nivolumab in Untreated Advanced Melanoma (RELATIVITY-047). N Engl J Med. 2022;386:24-34. doi:10.1056/NEJMoa2109970
- Cho BC, Rodríguez-Abreu D, Hussein M, et al. Updated Analysis of Tiragolumab (Anti-TIGIT) plus Atezolizumab for PD-L1–Positive NSCLC (CITYSCAPE). Ann Oncol. 2024;35(5):811-819. doi:10.1016/j.annonc.2023.12.012
- Luo J, Liang X, Zhou Y, et al. Immune-Related Pneumonitis in NSCLC Treated with ICIs: Systematic Review and Meta-Analysis. Ther Adv Med Oncol. 2024;16:17588359241234567. doi:10.1177/17588359241234567
監修者:農学博士 嶋秀明(シンバイオシス株式会社)
公開日:2025年6月21日
更新日:2025年10月15日