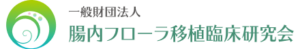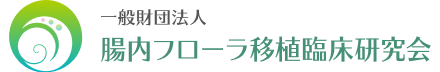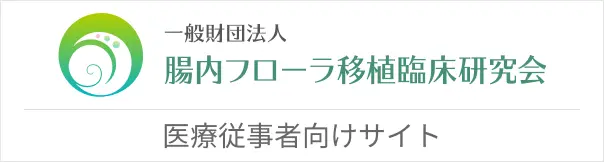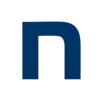Kさんは、長年悩まされてきた様々な体調不良に対し、腸内フローラ移植という治療を選択。その決断に至るまでの経緯や、現在の生活、そして今後の医療への期待について、貴重なお話を伺いました。
プロフィール
・疾患名:過敏性腸症候群、起立性調節障害
・移植期間:2025/1/28〜2025/2/4
・移植回数:3回コース
・移植担当医療機関:医療法人ふたまた会 ナチュラルアートクリニック
インタビュー
腸内フローラ移植をどのように知りましたか?
Kさんのご両親: これまで過敏性腸症候群や起立性調節障害、睡眠障害といった病気を抱えており、特に下痢が続いていたことから、腸内環境に何かしらの問題があると感じていました。腸内環境を改善する方法として腸内フローラ移植があることはある程度知っていましたが、どこで実施しているかは分からず、大学病院での研究的な一時的なものに限られ、特殊な腸の病気でなければ受けられないとわかっていました。様々な情報を探す中で、ナチュラルアートクリニックで腸内フローラ移植が可能であることを知りました。
これまでの治療の中で、主治医から腸内環境の改善についてどのようなアドバイス受けましたか?
Kさんのご両親: 最初の下痢の症状から、腸が悪いという認識はありました。3年前に内科のクリニックでオンライン診察を受けた時のことです。腸内フローラに注目するようになったのは、そこで受けた便検査の結果、悪玉菌はそれほど多くないものの、ラクトバチルス属などの本来いてほしい善玉菌が非常に少ないことが判明し、腸内環境が荒れていると分かったためです。それからサプリメントを服用するようになりました。
腸内フローラのバランスの悪さからどのように「移植」という選択肢に辿り着いたのでしょうか?
Kさんのご両親: 腸内フローラ移植ができる場所を探していました。4年ほど前は腸内フローラ移植に対して「うさんくささ」を感じていましたが、最近はそうでもないという認識でした。様々な情報を調べている時に、清水さんの著書『うんちのクソヂカラ』を見つけて読み、治療の信頼性や実績について納得し、ナチュラルアートクリニックでの治療を決断しました。
自由診療であり、まだ症例数も限られている中で、不安はありませんでしたか?
Kさん:先ほどの内科のクリニックを受診するまでは、過敏性腸症候群など別の治療に重点を置いていました。そのクリニックにかかり始めたのは、とにかく下痢の症状を何とかしたいという思いからでした。
腸内フローラ移植の話はその後、数ヶ月後に両親から聞きましたが、当時は僕自身、両親ほど理解が深くなく、「うさんくささ」や、便を体内に入れることへの生理的な抵抗感、拒否反応のリスクなど、浅い知識から治療の選択肢には入らないと考えていました。 しかし、さらに半年後には体調が改善できる限界まで良くなったと感じましたが、それでも通常の生活を送るにはまだ不十分で、「これ以上打つ手がない」という八方塞がりの状態でした。その時にもう一度両親から便移植の説明と説得を受けました。効果があるか分からないけれども、試してみようという気持ちになり、ナチュラルアートクリニックでの3回の移植を受けることを決めました。
Kさんのご両親: 過去には、過敏性腸症候群の際に受けた大腸ファイバー検査で、下剤により腸内を空にした後、一時的に体調が非常に良かった経験があり、このことから腸内環境の重要性は漠然と感じていました。また、自閉スペクトラム症の治療法に関する専門書も読んでいました。
医療機関、事務局のサポートについてどのように感じられましたか?
Kさんのご両親:腸内フローラ移植臨床研究会の事務局に、ナチュラルアートクリニックで受けた検査の結果が共有されているかどうかの確認をするために、何度もメールを送りました。入金から治療の日程が決まる形なので、仕事を休むなどのためにもう少し治療日程を決めやすくなるとありがたいです。
食事について気をつけられていることはありますか?
Kさんのご両親:油についてはそれほど厳しくないものの、特にグルテンと乳製品を制限しています。以前、好んで食べ過ぎていた麺類を制限しています。親がいなくても手軽に作って食べられる麺類に頼っていたことが良くなかったと感じています。
睡眠についてはいかがでしょうか?
Kさん: 移植前は、睡眠の不安定さや、疲労感などを感じていました。移植終了後は健康なまま学生生活を過ごすことができました。分割睡眠だったものが、一回のまとまった7、8時間の睡眠になり、それもあってか疲労感が軽減されました。ただ、移植と、食事の管理、大学への入学、睡眠リズムの管理、取り始めた健康食品など、多くの変化があったため、どれが大きく影響したかは正直な所わからないです。
また、睡眠障害と腸内細菌叢の乱れに関する研究知見があれば、ぜひ知りたいと思っています。僕の睡眠障害は「過眠」タイプで、非常に長い時間眠ることが特徴です。最近、祖母の看病で外出が増えたことで体力的に疲れ、4日間で約70時間寝ることもありました。
Kさんのご両親:この過眠が「クライネ・レヴィン症候群」や「特発性過眠症」ではないかと心配しており、慢性疲労症候群との関連も考えています。これらの症状と腸内環境がどのように関係しているのか、さらなる研究データに期待しています。
Kさんが腸内環境を整えるために続けていること
- 麺類、特にグルテンと乳製品を制限している。
- GCペプチダーゼ(ペプチド結合を加水分解する酵素の総称)の活用。
- 乳製品をA2ミルク(ベータカゼインがA2型のみで構成されたミルク)、もしくは豆乳などに代替する。
- えごま油など体に良い油をできる限り用いる。
- 納豆やキムチ、ぬか漬けの他にビフィズス菌やオリゴ糖などを摂る。
最後に
Kさんご自身は当初、腸内フローラ移植に対し生理的な抵抗感があり「うさんくささ」も感じていましたが、様々な治療を試した上での「これ以上打つ手がない」という状況や、世間における便移植の認知度向上、そしてご両親の熱心な説得が後押しとなり、治療を受けることを決意されました。
現在、Kさんは3回の腸内フローラ移植を経て体調が安定しているとのことですが、 食事内容の改善(麺類、グルテン、乳製品の制限、ぬか漬けの摂取)を継続するなど、腸内環境を良好に保つための努力を続けています。
Kさんの体験は、腸内環境の変化による症状の改善の可能性と重要性を示唆しています。