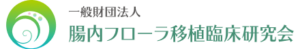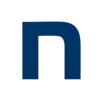赤ちゃんが元気に生まれてくれればなんだっていい。
それはたしかに正論だと思う。
赤ちゃんが危険にさらされるリスクがほんの少しでもあるなら、そしてそのリスクが減らせるなら、帝王切開だって構わない。
帝王切開が最初に行なわれ始めたのは古代ローマ時代。
命がけの出産中に母親が実際に死にかけると、胎児の命だけでも救うために行なわれた措置だった。当然、母親の死亡率はほとんど100%だっただろう。
要は切腹だ。想像するだけで痛すぎる。
麻酔や手術の技術が向上し、帝王切開は胎児だけではなく母親の命も助ける方法になった。
さらには、出産中にトラブルがあった場合には経膣分娩よりも安全な方法として帝王切開が選ばれるようになった。
帝王切開のおかげで、無数の命が助かった。
目次
- 帝王切開の現状
- どうして帝王切開が増えているのか
- 帝王切開とマイクロバイオーム
- 最初の研究
- 最初の研究は正しかったか?
- マイクロバイオーム生態系の立ち上がりが遅くなる
- 帝王切開とマイクロバイオームの両立を目指して
- 膣細菌を赤ちゃんに塗るという方法
- ”vaginal seeding”(膣の種まき)は安全か
・本文中のカッコ付き番号は、記事下部の参考文献の番号を表しています。
・用語解説はこちら(随時更新)
・主要記事マップはこちら(随時更新)
帝王切開の現状
現在日本では、4人に1人の赤ちゃんが帝王切開で生まれてくる。この数字は1990年代の2〜3倍にものぼり、世界の現状とほぼ同じだ。
WHOが推奨する帝王切開率は10〜15%だから、その数字を大きく上回っている。
医療技術や制度の進んでいる先進国たちが、その数字を押し上げているのだろうか?
実はそうでもなく、むしろ発展途上国や新興国で帝王切開率が増えているという現状がある。
エジプトでは、なんと70%以上もの妊婦が望むと望まざるとにかかわらず帝王切開を受けている。(参考:出産の72%が帝王切開 エジプト 医学的に必要ないのに広がる事情:朝日新聞デジタル)
他にもドミニカ共和国、ブラジル、キプロス、トルコなどで50%以上の高い帝王切開率になっている。
日本や世界平均の「20%」という数字がかすんで見えるほどだ。
この状況が続けば、最悪の場合は2030年までに東アジア63%、ラテンアメリカやカリブ海地域で54%、西アジアで50%、北アフリカで48%、南ヨーロッパで47%、オーストラリアやニュージーランドで45%まで数字が上がる可能性があるとWHOは予測している。
Caesarean section rates continue to rise, amid growing inequalities in access
逆に、北欧やオランダでは10%台である。このように国によって差があるということは、医学上の緊急性や必要性とは別のところで帝王切開が選ばれているということが推測できる。
どうして帝王切開が増えているのか
帝王切開には、予定帝王切開と緊急帝王切開がある。
母体や胎児が危険な状態にある場合、お産はしばしば緊急帝王切開に切り替えられる。
母親の年齢や既往症などを考慮して、もしもの場合に帝王切開をすぐに受けられるように大きな病院を産院として選ぶ人も多い。
予定帝王切開も、同様にリスクが高いと判断された妊婦に提案される。
前回のお産が帝王切開だった場合は、そのあとの出産は帝王切開しか選べない病院も多い。前の傷が開いて大量出血するなどのリスクがあると考える医師がいまだに多いからだ。
しかし、現場の医療スタッフの常識がそうだとしても、最新の研究では帝王切開のあとの経膣分娩でそれほどリスクが上がるわけではないということが明らかになっている。
(参考:Vaginal Birth After Cesarean: VBAC: – American Pregnancy Association)
ほかにも逆子や双子、巨大児の場合にも予定帝王切開が選ばれやすい。
医師が予定帝王切開を勧める背景には、実は裏の理由も存在する。
訴訟リスクを回避したい、出産にかかる時間を節約したい、高い手術費用を取れるといったものだ。
リスクが高いからという表向きの理由はあっても、実はすべてのケースで本当に帝王切開が医学的に必要であるというわけではない。
帝王切開を自ら望む母親もいる。
陣痛があまりにも長く耐え難い痛みであるとき、「切ってください」と涙ながらに訴える母親の言葉は、医師の背中を押すだろう。
産休制度が整っていない国や、産休を使えない仕事をしている場合、仕事のスケジュールに合わせて出産したいと望む女性がいてもおかしくない。
そして、予定帝王切開ならば、ずっと担当してくれていた主治医に最後まで見てもらえるというメリットもある。
必要以上に帝王切開が選ばれている現実で、誰かを責めることはおそらくナンセンスだ。
医学的な理由だけではなく、人間社会はさまざまな要素が複雑に絡んでいるのだから。
それでも、帝王切開にはリスクがある。わずかながらメスが赤ちゃんを傷つけたり、呼吸系の障害が残ることもある。
術後の母親の回復には時間がかかる。もちろん、経膣分娩ならリスクがゼロというわけではない。
主治医や妊婦は、それらのリスクを天秤にかける。
近年、帝王切開による長期的なリスクにあるもうひとつの点を加えるべきだという声が上がっている。
腸内細菌たちを中心としたマイクロバイオームの形成だ。
帝王切開とマイクロバイオーム
帝王切開で生まれた赤ちゃんたちは、経膣分娩で生まれた赤ちゃんたちに比べてマイクロバイオームの形成過程に違いがあるのかもしれない。
妊娠中に膣や腸のマイクロバイオームが赤ちゃん向けに変わるのなら、膣を通るプロセスをスキップすることで赤ちゃんが獲得するマイクロバイオームに違いが出るというのは自然な仮説だ。
最初の研究
それを最初に検証したのが、Maria Gloria Dominguez-Bello氏(当時プエルトリコ大学、現ラトガース大学)らの研究チームだ。
2010年に発表された「分娩方法が新生児のさまざまな体の部位において最初のマイクロバイオータの獲得と構成を左右する」と題されたこの研究論文(1)は、生まれたての赤ん坊のマイクロバイオーム(特に腸内細菌)形成における帝王切開の影響を網羅的に検証した最初の研究として位置づけられている。
この研究は、あるハプニングの結果行なわれたものだった。
Dominguez-Bello氏は祖国でもあるベネズエラで20年にわたり、栄養学や微生物学の研究を行っていた。
その時もベネズエラに赴き、ジャングルの奥地で先住民たちの微生物を採取する予定だったのだが、ヘリコプターがキャンセルされてしまった。
ベネズエラの首都で三週間足止めされてしまった彼女は、バカンスを取るよりも「別の研究」に着手することを選んだ。
地元の病院に行って、経膣分娩と帝王切開による分娩で生まれた赤ちゃんたちの細菌にどんな違いがあるか調べることにしたのだ。
この研究には、21歳から33歳まで9人の母親と10人の赤ちゃんが参加し、母親の皮膚、口、膣の細菌や、新生児の皮膚、口、鼻、便(胎便)の細菌が調べられた。
その結果、帝王切開で生まれた赤ちゃんと経膣分娩で生まれた赤ちゃんたちで、それぞれ細菌の構成が大きく異なっていることが示された。
経膣分娩で生まれた赤ちゃんたちは、からだじゅうが母親の膣常在菌で覆われていたのだ。
最初の研究は正しかったか?
この結果は、これに続くさまざまな別の研究者たちによる研究ですべて支持されたわけではない。
生後すぐの赤ちゃんから1歳未満の赤ちゃんまでを対象に、帝王切開による分娩と経膣分娩の差がマイクロバイオームにどのような影響を与えるのか、世界中の研究者が検証を試みた(2)。
その結果は、研究ごとにまちまちだった。
この検証をむずかしくしているいくつかの要因がある。
まず、生まれてから数日、あるいは数ヶ月の赤ちゃんは、マイクロバイオーム(検証対象は細菌)がめまぐるしく変わる。
生まれてから24時間以内に出る「胎便(たいべん)」の腸内細菌の構成は、翌日にはがらりと変わっている。ちなみに胎便は最近まで無菌だと考えられていたが、ある研究では3人に2人の割合で、わずかに検出可能なレベルで細菌が含まれることがわかっている(3)。
第二に、腸内細菌の構成は個人差が大きい。母親が違えば、受け取る細菌も違うのだ。
そして第三に、特に胎便は細菌の数そのものが少ない。解析対象の菌数が少ないと、解析過程でのコンタミネーションなどの影響が大きくなり、結果の信頼性が下がる。
マイクロバイオーム生態系の立ち上がりが遅くなる
それでも、帝王切開で生まれた赤ちゃんは明らかにマイクロバイオームの立ち上がりが遅いことを多くの研究は示唆している。
生態学的な言い方をすれば、生態系が安定するまでに時間がかかる。
特に0歳児に特徴的なビフィズス菌(Bifidobacterium)の増殖が何ヶ月も遅れてしまう。
母乳にはビフィズス菌とその栄養源であるオリゴ糖が含まれているにもかかわらず、帝王切開で生まれた赤ちゃんは母乳を飲んでいてもビフィズス菌がなかなか増えてこない。
これは、生まれる瞬間に母親の便に含まれるビフィズス菌を摂取できないことで、赤ちゃんの未熟な腸マイクロバイオームの生態系の中で別の菌たちが先に増殖を始めてしまい、あとから来たビフィズス菌が増えづらくなってしまっている可能性が考えられる。
両者の違いは、離乳食が始まる生後6ヶ月頃になるとだんだんと消えていくことがわかっている。
そうであっても、未熟な状態で生まれてくるヒトにとって、生後半年ものあいだ一緒にからだづくりをしてくれるメンバーの顔ぶれが違うことは、重要な意味を持つだろう。
では本当に、帝王切開で生まれたことによるマイクロバイオームの「顔ぶれの変更」は、その後の人生に不利益をもたらすのか?
おそらく、かなり確定的に答えはイエスだ。
帝王切開で生まれた赤ちゃんは、生後一年以内に感染症にかかりやすくなる。
病気のリスクは感染症にとどまらない。
小児喘息(4-6)、アトピー(7-9)、アレルギー(8,10)、Ⅰ型糖尿病(11)、炎症性腸疾患(IBD)(5,12)などの免疫応答に関する疾患リスクや、肥満(13)の増加も報告されている。
さらには、学童期において認知能力の発達にも影響をおよぼす(14)ことが示され始めている。
帝王切開とマイクロバイオームの両立を目指して
世界的な帝王切開の割合はうなぎのぼりだと言っていいだろう。
経済的に国全体に大きな負担がかかるうえ、母親の肉体的・精神的負担も大きい帝王切開は、本当に医学的に必要な場合に限るほうがいい。
マイクロバイオームの自然な形成が乱されることと深く関連しているらしいことを踏まえると、余計にその思いは強くなる。
けれど、女性の気持ちを置き去りにしたまま自然分娩信仰を祭り上げるわけにもいかない。
妊娠や出産の過程では、人には言えない心の傷を静かに抱えている女性も多い。
「下から産んであげたかった」
「帝王切開になってしまった」
無事に赤ちゃんが生まれたとしても、何十年もそんな思いを引きずる人もいる。
そんな状況で、赤ちゃんのマイクロバイオーム形成、ならびに将来の健康状態にも悪影響があるかもしれないという知らせは、そんな母親たちを余計に悲しませるだけかもしれない。
でも、科学は常に改善を試みている。ベストではなくとも、ベターな方法を安全に提案するのも、科学の役目だ。
帝王切開で生まれた赤ちゃんに正常なマイクロバイオームを形成してもらおうと、画期的な試みを始めた研究チームがある。
膣細菌を赤ちゃんに塗るという方法
カリフォルニア大学教授(当時コロラド大学教授)のRob Knight氏の娘は、2011年に緊急帝王切開で誕生した。
Knight氏は世界的に著名な微生物学者で、2007年に発足したHuman Microbiome Projectにも主要メンバーとして関わっている。
彼が帝王切開によるマイクロバイオームへの影響を知らなかったはずはない。
実は、Knight氏はその前年に出されたDominguez-Bello氏の論文(前述のベネズエラでの研究)の共同著者としても名を連ねている。
そして彼は、研究者というよりもひとりの父親として行動した。
手術のあと、妻と娘と三人きりになった病室で、彼は妻の膣を綿棒でぬぐって娘の体に塗りつけた。
開腹手術である帝王切開は、当然ながら母親に感染症のリスクがある。
執刀医をはじめとしたスタッフは、自身や器具、部屋の消毒や殺菌を念入りに行なっただろう。生まれてくる赤ちゃんも清潔に取り出されたはずだ。
彼の行為を病院スタッフが知っていたら、決していい顔はしなかっただろう。
けれど父親として娘が将来受けうる不利益をできるだけ避けようとした彼の行動を責めることは、誰にもできないのかもしれない。
この、おそらく世界ではじめての「膣マイクロバイオーム移植」は、どの研究にも含まれていない。研究計画なしの行為だ。
2016年、Dominguez-Bello氏やKnight氏を含む研究チームは、この「膣マイクロバイオーム移植」を帝王切開で生まれた4名の新生児に実施したという論文(15)を出した。
その結果、新生児の体の一部で母親の膣由来のマイクロバイオームが定着し、経膣分娩で生まれた赤ちゃんと同じような構成になったという。
彼らはこの方法を”vaginal seeding”(膣の種まき)と呼び、現在に至るまで着実に研究データ(16,17)を積み重ね続けている。
「この方法はこのようなリスクがある」という事実を明らかにするのも科学の大切な仕事のひとつだが、それが避けられないケースがある場合に「どうすればリスクを少しでも減らせるか」という方法を模索する姿は、研究者としてとても尊敬できる姿勢だ。
彼らは帝王切開の他にも、粉ミルク育児や分娩時の抗生物質の影響をできるだけ避けたり、受けた影響を少なくするための方法を模索している(18)。
”vaginal seeding”(膣の種まき)は安全か
一方で、”vaginal seeding”はまだ効果や安全性、機序がわからない面も多く、実施は慎重になるべきだという声もある。
アメリカ産婦人科学会(American College of Obstetricians and Gynecologists, ACOG)は、”vaginal seeding”はあくまで研究計画に含まれるケースでのみ実施されるべきで、一般的な医療の場や自己判断で行うべきではないとコメントを出している。
(参考:Vaginal Seeding | ACOG)
西オーストラリア大学の研究者らは、2018年に発表した論文(2)内でかなり批判的な立場を取っている。
彼らは帝王切開による分娩と経膣分娩の研究をいくつか取り上げたうえで、両者のマイクロバイオーム形成に本当に差があるのかをまず問題としている。さらに帝王切開そのものではなく、その他の因子に本当の原因がある可能性も考えるべきだと主張する。
帝王切開を余儀なくされた要因(母親側の年齢や疾患、肥満などのリスク因子)、帝王切開の際に服用する抗生物質、陣痛がないこと、母乳の影響、個人間・個人内のマイクロバイオームの多様性などがその因子として考えられるだろう。
別の研究チーム(19)は、これらの因子のうち抗生物質の影響を排除しても両者のマイクロバイオーム形成に明らかな違いがあることを示している。彼らは母乳、きょうだいやペットの有無、産後の入院日数の長さ、おしゃぶりに至るまでさまざまな因子を検討し、
さらには”vaginal seeding”に加え、”fecal seeding”(うんちの種まき)の可能性にすら言及している。
帝王切開はただの「相関」なのかそれとも「原因」なのか。
それを確かめるためには還元主義的な方法を試していくしかないが、無数にある交絡因子をすべて考慮した研究は、相当難しいだろう。
それよりは、完璧なリレーを見せてくれる自然な経膣分娩や母乳育児をなるべく後押しし、それが叶わない場合でも悲観せずにベターな方法を探っていく姿勢を、筆者としては応援したい。
1. Dominguez-Bello MG, Costello EK, Contreras M, et al. Delivery mode shapes the acquisition and structure of the initial microbiota across multiple body habitats in newborns. Proc Natl Acad Sci U S A. 2010;107(26):11971-11975. doi:10.1073/pnas.1002601107
2. Stinson LF, Payne MS, Keelan JA. A Critical Review of the Bacterial Baptism Hypothesis and the Impact of Cesarean Delivery on the Infant Microbiome. Front Med. 2018;5. Accessed October 31, 2023. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmed.2018.00135
3. Hansen R, Scott KP, Khan S, et al. First-Pass Meconium Samples from Healthy Term Vaginally-Delivered Neonates: An Analysis of the Microbiota. PLoS ONE. 2015;10(7):e0133320. doi:10.1371/journal.pone.0133320
4. Debley JS, Smith JM, Redding GJ, Critchlow CW. Childhood asthma hospitalization risk after cesarean delivery in former term and premature infants. Ann Allergy Asthma Immunol. 2005;94(2):228-233. doi:10.1016/S1081-1206(10)61300-2
5. Sevelsted A, Stokholm J, Bønnelykke K, Bisgaard H. Cesarean Section and Chronic Immune Disorders. Pediatrics. 2015;135(1):e92-e98. doi:10.1542/peds.2014-0596
6. Thavagnanam S, Fleming J, Bromley A, Shields MD, Cardwell CR. A meta-analysis of the association between Caesarean section and childhood asthma. Clin Exp Allergy. 2008;38(4):629-633. doi:10.1111/j.1365-2222.2007.02780.x
7. Negele K, Heinrich J, Borte M, et al. Mode of delivery and development of atopic disease during the first 2 years of life. Pediatr Allergy Immunol. 2004;15(1):48-54. doi:10.1046/j.0905-6157.2003.00101.x
8. Bager P, Wohlfahrt J, Westergaard T. Caesarean delivery and risk of atopy and allergic disesase: meta-analyses. Clin Exp Allergy. 2008;38(4):634-642. doi:10.1111/j.1365-2222.2008.02939.x
9. Laubereau B, Filipiak-Pittroff B, Berg A von, et al. Caesarean section and gastrointestinal symptoms, atopic dermatitis, and sensitisation during the first year of life. Arch Dis Child. 2004;89(11):993-997. doi:10.1136/adc.2003.043265
10. Eggesbø M, Botten G, Stigum H, Nafstad P, Magnus P. Is delivery by cesarean section a risk factor for food allergy? J Allergy Clin Immunol. 2003;112(2):420-426. doi:10.1067/mai.2003.1610
11. Cardwell CR, Stene LC, Joner G, et al. Caesarean section is associated with an increased risk of childhood-onset type 1 diabetes mellitus: a meta-analysis of observational studies. Diabetologia. 2008;51(5):726-735. doi:10.1007/s00125-008-0941-z
12. Li Y, Tian Y, Zhu W, et al. Cesarean delivery and risk of inflammatory bowel disease: a systematic review and meta-analysis. Scand J Gastroenterol. 2014;49(7):834-844. doi:10.3109/00365521.2014.910834
13. Darmasseelane K, Hyde MJ, Santhakumaran S, Gale C, Modi N. Mode of Delivery and Offspring Body Mass Index, Overweight and Obesity in Adult Life: A Systematic Review and Meta-Analysis. PLOS ONE. 2014;9(2):e87896. doi:10.1371/journal.pone.0087896
14. Polidano C, Zhu A, Bornstein JC. The relation between cesarean birth and child cognitive development. Sci Rep. 2017;7(1):11483. doi:10.1038/s41598-017-10831-y
15. Dominguez-Bello MG, De Jesus-Laboy KM, Shen N, et al. Partial restoration of the microbiota of cesarean-born infants via vaginal microbial transfer. Nat Med. 2016;22(3):250-253. doi:10.1038/nm.4039
16. Song SJ, Wang J, Martino C, et al. Naturalization of the microbiota developmental trajectory of Cesarean-born neonates after vaginal seeding. Med N Y N. 2021;2(8):951-964.e5. doi:10.1016/j.medj.2021.05.003
17. Mueller NT, Differding MK, Sun H, et al. Maternal Bacterial Engraftment in Multiple Body Sites of Cesarean Section Born Neonates after Vaginal Seeding—a Randomized Controlled Trial. mBio. 2023;14(3). doi:10.1128/mbio.00491-23
18. Mueller NT, Bakacs E, Combellick J, Grigoryan Z, Dominguez-Bello MG. The infant microbiome development: mom matters. Trends Mol Med. 2015;21(2):109-117. doi:10.1016/j.molmed.2014.12.002
19. Reyman M, van Houten MA, van Baarle D, et al. Impact of delivery mode-associated gut microbiota dynamics on health in the first year of life. Nat Commun. 2019;10:4997. doi:10.1038/s41467-019-13014-7
本ブログ記事は、
シンバイオシス株式会社微生物事業部の研究員が
noteにて作成した記事を転記しております。
記事タイトル:帝王切開と自然分娩をマイクロバイオームの視点で考える
記事リンク:https://note.com/symbiosis17/n/nd662182b4ed4?sub_rt=share_pw