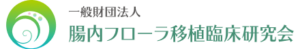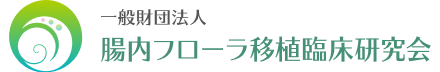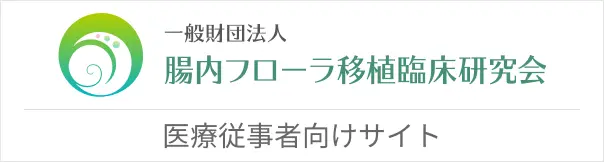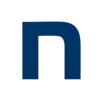本で学ぶ派の人のために、微生物のことを学べるおすすめの一般書をご紹介します。
目次
1.まえがき
2.入門編 まずはここから。
(1)『9000人を調べて分かった腸のすごい世界 強い体と菌をめぐる知的冒険』/國澤 純
(2)『細菌が人をつくる』/ロブ・ナイト
(3)『腸内細菌が喜ぶ生き方』/城谷 昌彦
3.初級編 もう少し詳しく、でもがっつり専門用語はやめてね
(1)『あなたの体は9割が細菌』/アランナ・コリン
(2)『マイクロバイオームの世界』ロブ・デザール&スーザン・L・パーキンズ
(3)『きたない子育てはいいことだらけ』/ブレット・フィンレー、マリー=クレア・アリエッタ
4.中級編 いちばん活躍する知識を授けてくれる本たち
(1)『共生微生物からみた新しい進化学』/長谷川 政美
(2)『失われてゆく、我々の内なる細菌』/マーティン・J・ブレイザー
(3)『土と内臓』/デイビッド・モントゴメリー、アン・ビクレー
(4)『家は生態系』/ロブ・ダン
5.上級編 この分野の概観をひととおり知ったあとのあなたに
(1)『微生物が地球をつくった』/ポール・G・フォーコウスキー
(2)『微生物生態学』/デイビッド・L・カーチマン
6.番外編
(1)『発酵文化人類学 微生物から見た社会のカタチ』/小倉ヒラク
1.まえがき
すべて、私が最後までじっくり読んだことのある本に限定しています。なので、あまり数は多くありません。
この記事を書く際にもお世話になった本ばかりです。
この分野は黎明期〜成長期にある分野で、5年経つと常識が変わっているという場合もあります。
ですが、2010年前後の論文は古典として今でも引用されることも多く、一般書でも2015年以降の出版であれば全体としては大きく間違っていないだろうという印象があります。
時を経ないとわからないこともあって、新しい情報のほうがいい、とも一概に言えない世界で、この分野の権威や優秀な科学ライターたちが定期的にまとめる書籍を読むと得るものがたくさんあります。
全体的にヒト共生マイクロバイオームの比率が大きめですが、微生物そのものの生態や進化史、環境中の微生物についても研究が進んでいて、一般書も存在します。
あと、本文でいちいち触れていないけれど、翻訳者の方たちの仕事もすごい。
2.入門編 まずはここから。
腸内細菌のことはほとんど知らない、という方におすすめの本たちです。
だからといって、いわゆる一般的な腸活本のように、変に煽ってきたり、美容系のきらきらした話題や精神論に特化しているわけでは決してないです。
ちゃんと科学的なエビデンスや見解に基づきつつ、ものすごくわかりやすく書いてくれている書籍です。
これらの入門編を読んで、もっと詳しく知りたい!と思った方は、初級編以降に進まれるといいかと思います。
(1)『9000人を調べて分かった腸のすごい世界 強い体と菌をめぐる知的冒険』/國澤 純
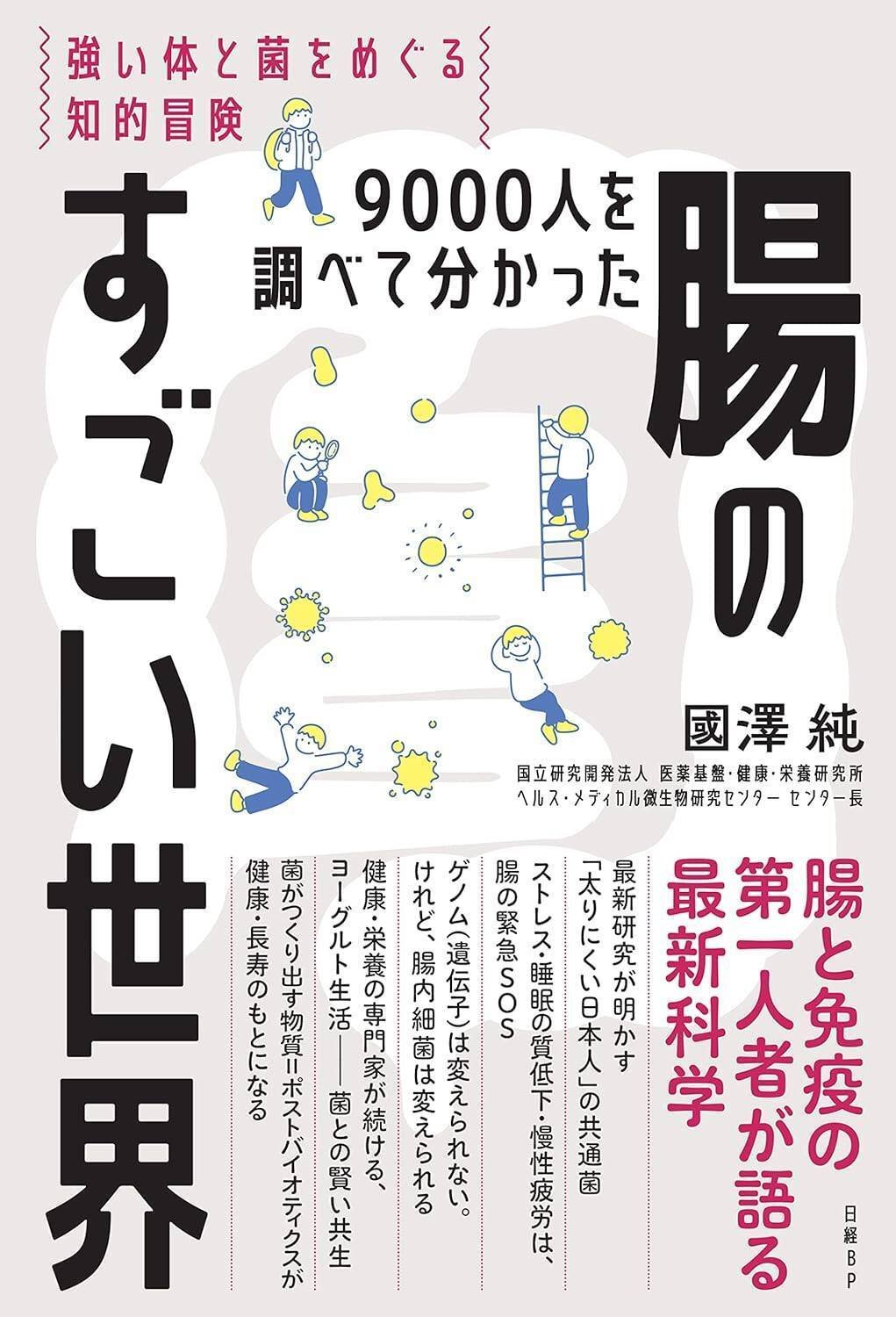
こちら『9000人を調べて分かった腸のすごい世界 強い体と菌をめぐる知的冒険』は2023年4月出版の、一般書としてはかなり新しい書籍です。
著者は国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 ヘルス・メディカル微生物研究センター センター長である國澤 純氏で、彼は間違いなく日本の腸内細菌研究のトップ級の一人です。
個人的にファンです。
2019年には弊社の関連法人である一般財団法人腸内フローラ移植臨床研究会第3回学術大会でも基調講演をしていただいたのですが、ハンパなくレベルの高い内容なのに、一般人にも最後まで面白く聞くことができました。
コミュニケーションスキルも高い研究者って、珍しくないですか?(失礼やな)
かなり詳しく、かつわかりやすく、最新の情報を手っ取り早く知りたい人に最適な一冊です。
タイトル通り、ヒト共生マイクロバイオームのうち腸内細菌をメインに扱っています。
(2)『細菌が人をつくる』/ロブ・ナイト
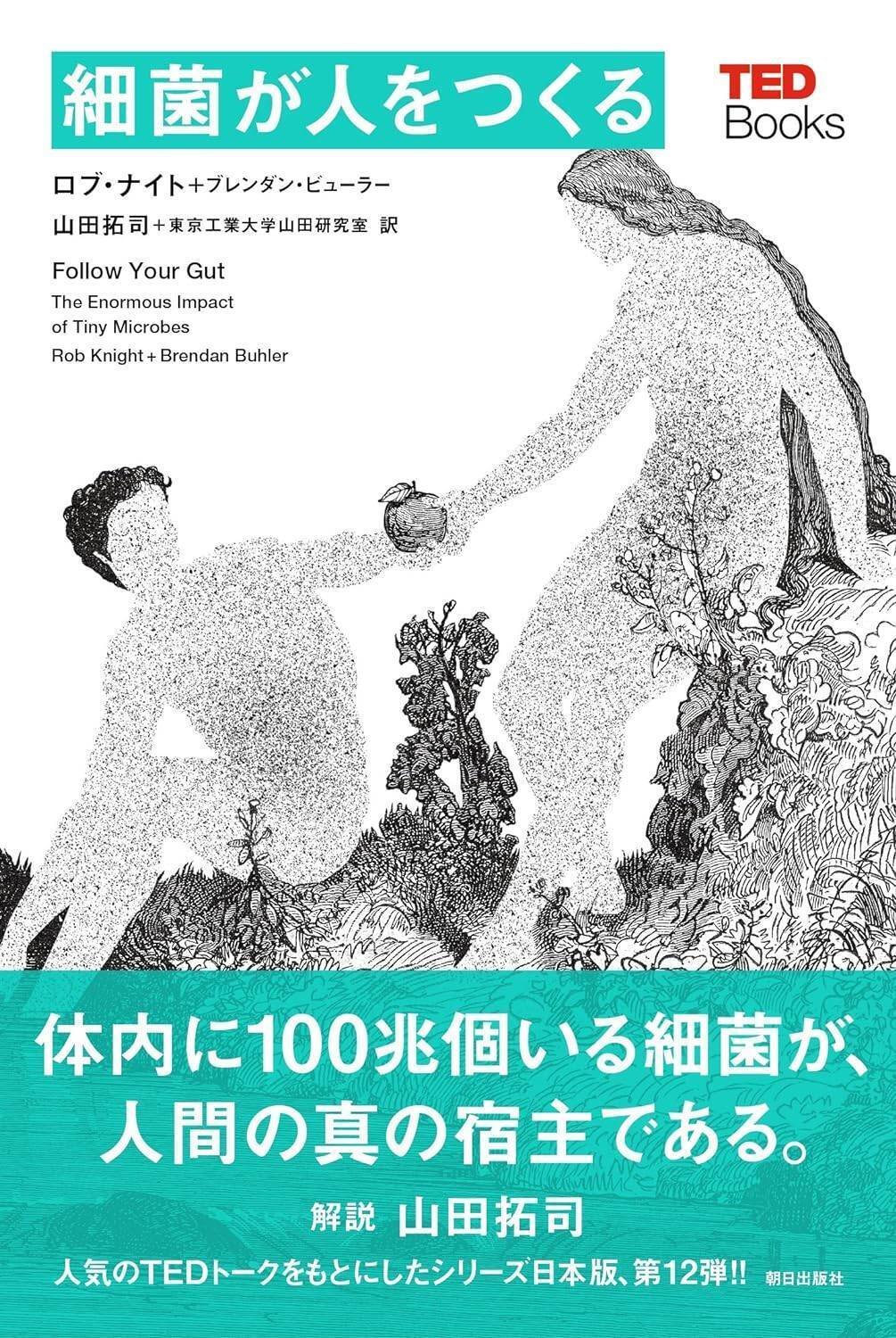
2018年出版の『細菌が人をつくる』は、アメリカの著名な微生物学者であるロブ・ナイト(Rob Knight)氏が著者です。
この本は彼の2014年のTEDトークが元になっていて、この仕事をはじめた頃に動画を見た私は、ポロシャツ&ほっそりカッコいいKnight氏を勝手に推しメン認定していました。(名前もカッコいいよね。Knightって。)
が。
2018年に来日して講演した氏は、なんか…ふつうの…オッチャンでした…
ちょっと二重顎になって、ダボッとしたスーツだったからでしょうか。多忙って大変。
とにかく、科学というのは正確さを維持したままここまで噛み砕いて説明ができるのか! と舌を巻いた一冊。
このくらいわかりやすく書けないうちは、ちゃんと理解しているとは言えないよなぁと自戒をこめておすすめします。
簡単だけれどテキトーではなくて、ほぼすべての記述にリファレンスがつけられています。こちらもヒト共生マイクロバイオーム(特に細菌)が話題の中心。
(3)『腸内細菌が喜ぶ生き方』/城谷 昌彦
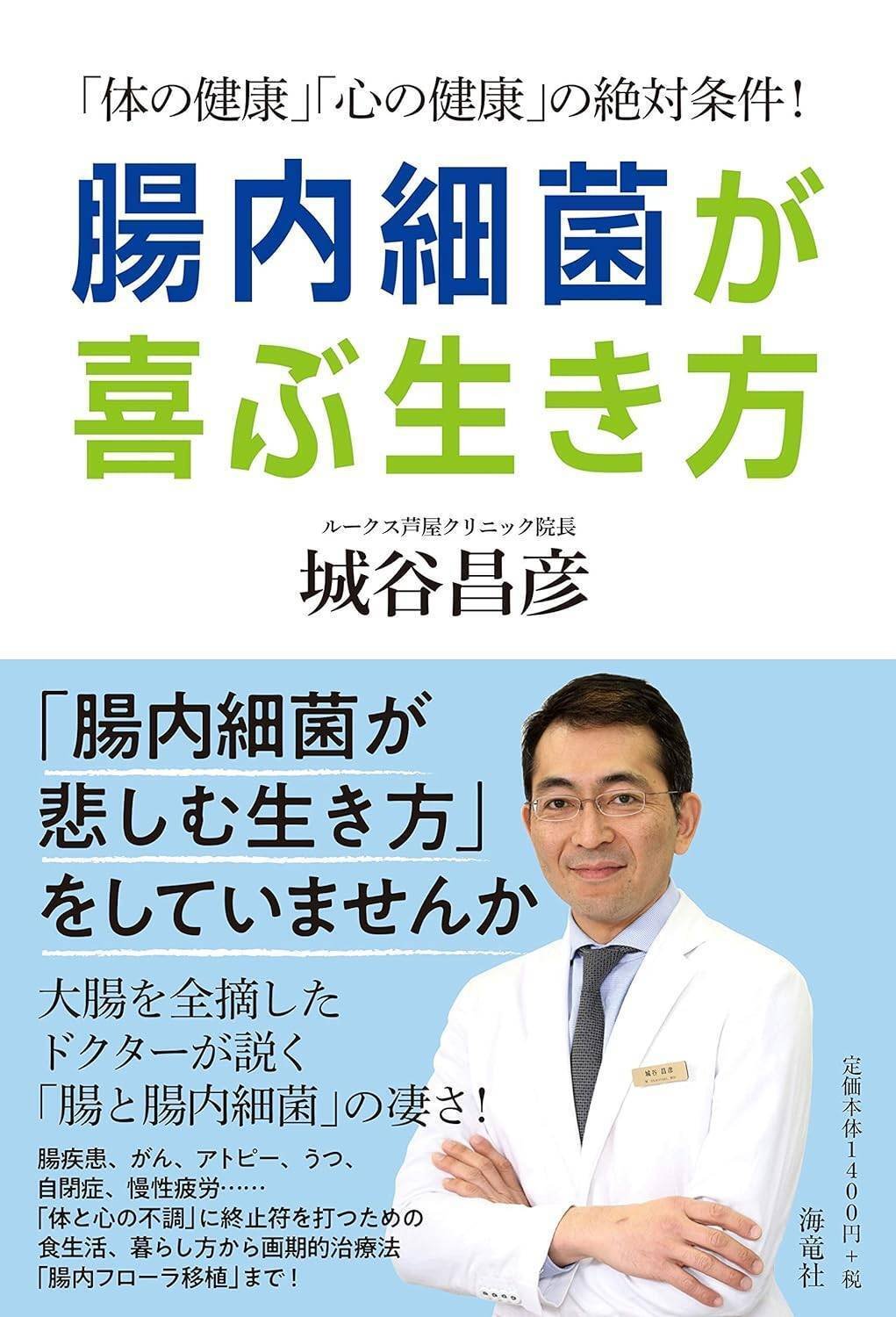
こちらは2019年出版の『腸内細菌が喜ぶ生き方』です。
著者はルークス芦屋クリニック院長の城谷昌彦氏。
弊社関連法人である一般財団法人腸内フローラ移植臨床研究会の専務理事をなさっておられる方です。
城谷先生は、潰瘍性大腸炎を患って大腸を全摘しておられ、その経験も書籍の中で語られています。
腸内細菌と宿主が共生してひとつになっているさまを「ホロビオント(holobiont)」と呼ぶことがありますが、西洋医学の欠点のひとつに木を見て森を見ない、つまりホロビオントとして見れていないことが挙げられると思います。
著者は西洋医学はもちろん、東洋医学や心理学等にも精通し、広い視点で腸内細菌と向き合っておられる数少ない人だと言えます。
3.初級編 もう少し詳しく、でもがっつり専門用語はやめてね
入門編では物足りない方に、初級編の書籍をいくつか紹介します。
門の内側には入ってみたいけれど、あまり小難しい言い回しはしてほしくないわ、という方におすすめ。
(1)『あなたの体は9割が細菌』/アランナ・コリン
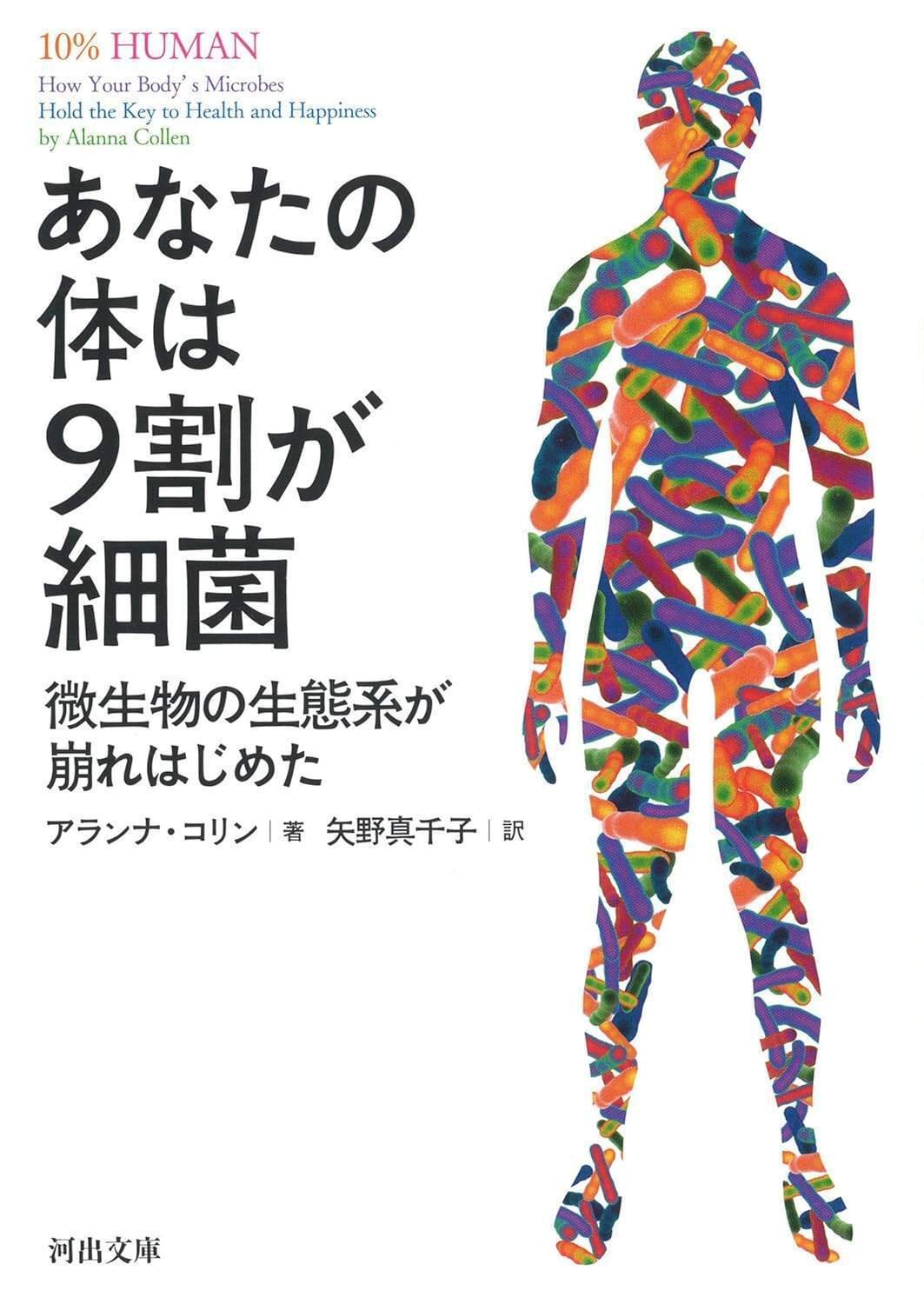
続いては2015年に原書が出版され、日本では2016年に単行本が出た『あなたの体は9割が細菌』を紹介します。
著者のアランナ・コリン氏は進化生物学の博士号を持つサイエンスライター。
抗生物質に命を助けられた経験を持ち、その後の不調は抗生物質による腸内細菌の乱れが原因ではないかと思いはじめたところから、マイクロバイオームの世界に興味を持ち始める。
さすがプロのライターだけあって、話の展開もうまいし、リサーチ力もすさまじい。
私たちの体に共生するマイクロバイオームについて、入門書よりはしっかり学びたいなという人に、まずおすすめしたい一冊です。
(2)『マイクロバイオームの世界』ロブ・デザール&スーザン・L・パーキンズ
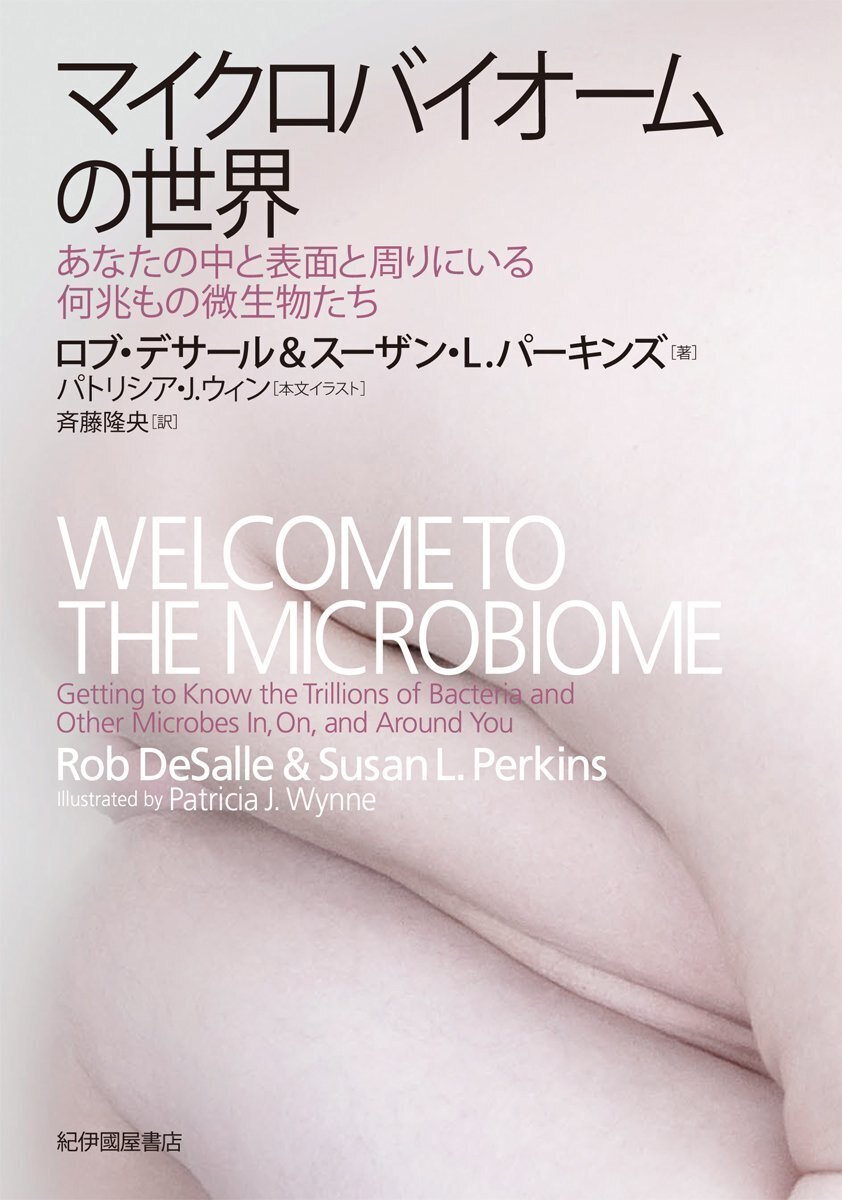
2016年出版の『マイクロバイオームの世界――あなたの中と表面と周りにいる何兆もの微生物たち』も、微生物の概観を学ぶのに適した良書です。
上述の『あなたの〜』と同様にヒト共生マイクロバイオームが中心だけれど、前者が私たちの健康と細菌の関係という視点を軸に展開されているとすれば、こちらはより微生物たちの視点から話を進めていると言えるかもしれない。
その理由は、著者たちのプロフィールを見れば少し納得がいくかも。彼らはアメリカ自然史博物館の学芸員で、実益とは少し距離を置いたところから事実を眺めることに慣れているのでしょう。
本書はアメリカ自然史博物館で2015年11月から2016年8月まで開催されていたマイクロバイオームの展示会に合わせて制作されたものだそうで、内容もなんとなく展示会を順に巡っているかのような気にさせられます。
微生物の種の特定に使われる次世代シーケンサーの仕組みも簡潔に解説されていて、参考になりました。
(3).『きたない子育てはいいことだらけ』/ブレット・フィンレー、マリー=クレア・アリエッタ
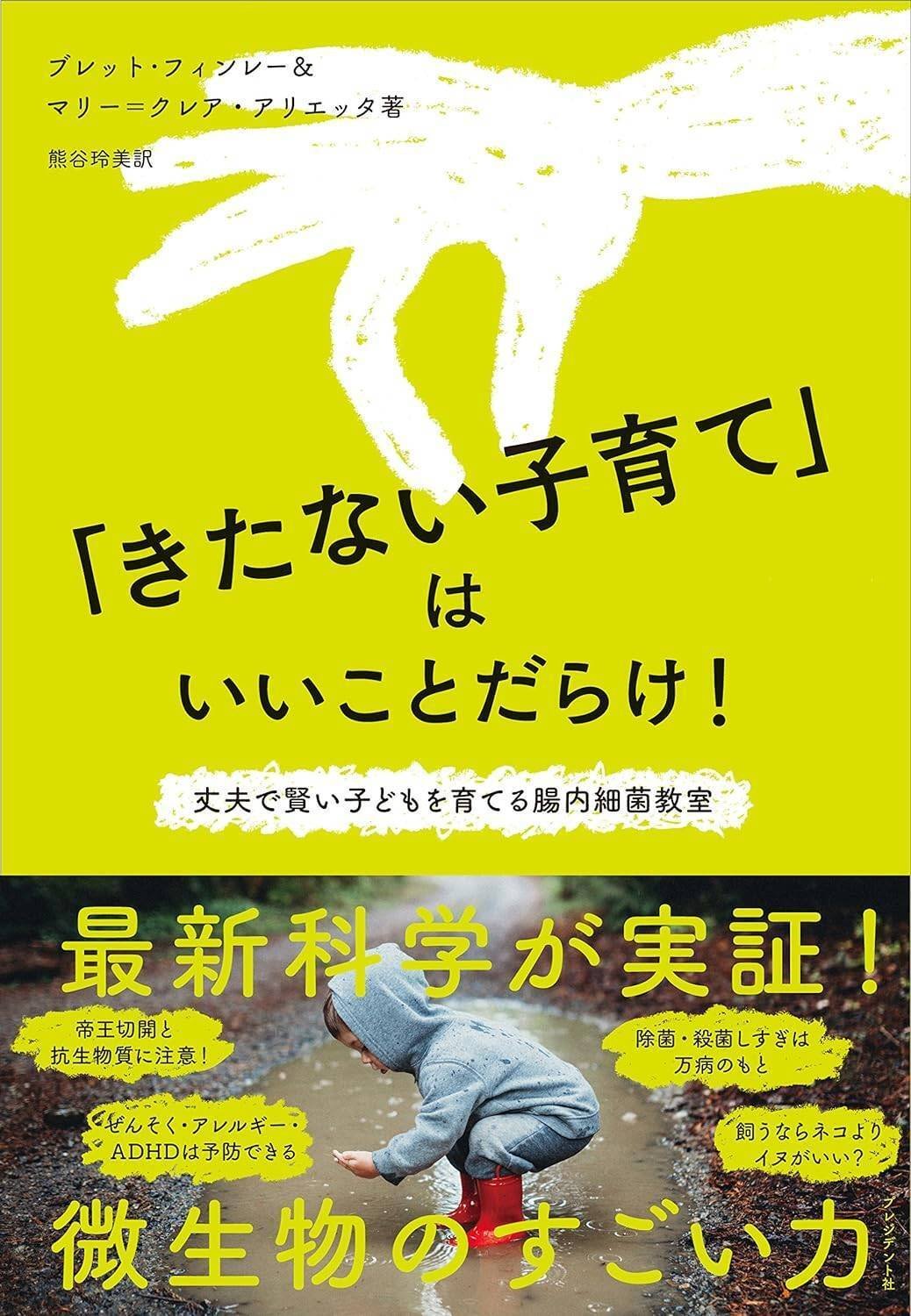
2017年出版の「きたない子育て」はいいことだらけ! ―丈夫で賢い子どもを育てる腸内細菌教室は、カナダの著名な微生物学者たちによる本。
どちらも子どもを持ち、仕事でも子どもに接する機会が多いことから、妊娠と出産、そして子どもたちの腸内細菌についての最新の科学論文をわかりやすくまとめてくれています。
本noteでも「腸内細菌は何歳までに決まる? 赤ちゃんから子どもへの成長とともに歩む菌たちのこと」と題したシリーズでお送りしている内容だけれど、もっとこの分野に関してだけでいいから詳しく知りたい人におすすめ。
同じような内容で「子どもの人生は「腸」で決まる: 3歳までにやっておきたい最強の免疫力の育て方」という本もあり、こちらはQ&A形式が基本で、さらに易しい内容。
4.中級編 いちばん活躍する知識を授けてくれる本たち
微生物の世界に馴染んできたら、これから紹介する本たちに手を出していい頃合いです。
手早く知識を得るなら簡単な本がいいけれど、ちゃんと理解しようと思うなら、大事な情報が「かんたん言葉」に翻訳される前の生の言い方をされている本を読むのがいいと思います。
(1)『共生微生物からみた新しい進化学』/長谷川 政美
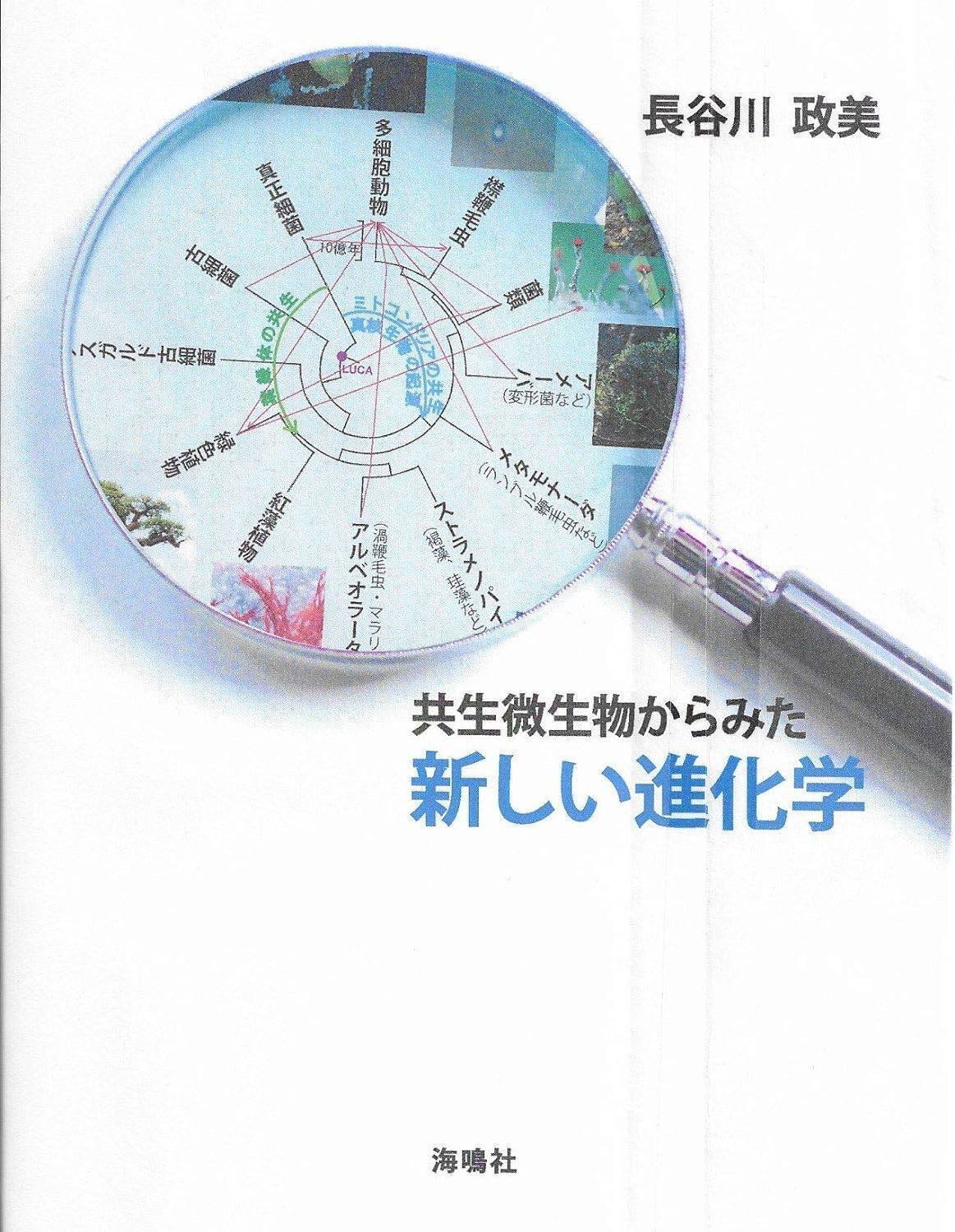
2020年出版の『共生微生物からみた新しい進化学』を紹介します。
この本の目次を見た途端、私のnoteの存在意義を再考させられました。
それくらい、網羅的に微生物と私たちの関係を、最新の研究を踏まえてまとめてある本です。
まえがきにある通り、著者が現役引退後に自分で勉強した内容をまとめているとのことで、どちらかというと一歩ひいた立場からいろんな研究を眺めることができます。
ヒト以外の生きものも含め、微生物との共生を「進化」という縦軸で理解できます。ストーリーを楽しむというより、リファレンス本としても活躍しそう。
(2)『失われてゆく、我々の内なる細菌』/マーティン・J・ブレイザー
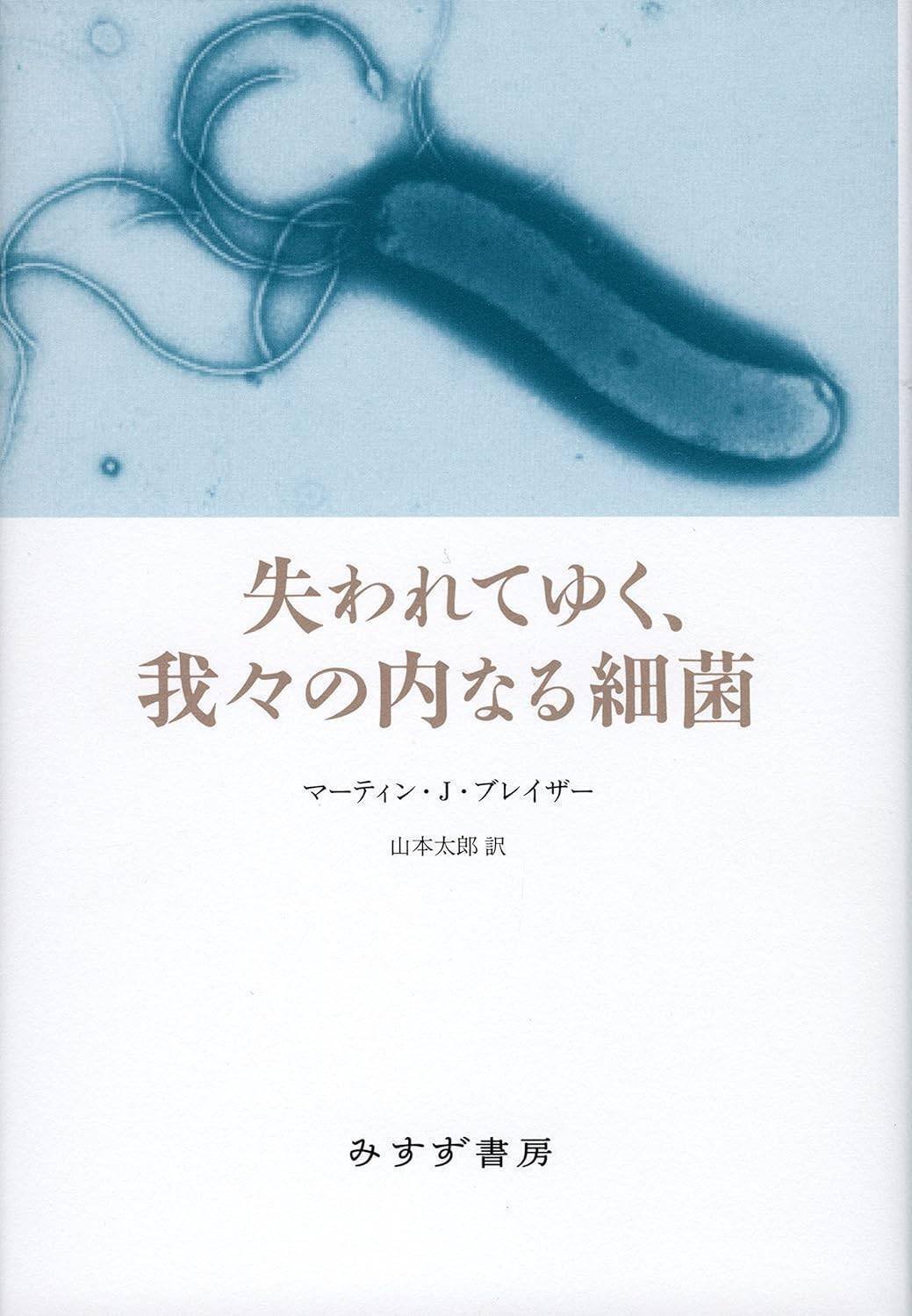
『失われてゆく、我々の内なる細菌』は、2015年に出版されて10年弱が経つにもかかわらず、未だに「読むべき腸内細菌関連の本」の五本指に入ると思います。
著者のマーティン・J・ブレイザー氏は、微生物学の第一人者も第一人者で、マイクロバイオーム研究の皮切りであるヒト・マイクロバイオーム・プロジェクト(HMP)のリーダー格です。
前述のロブ・ナイト氏と並んで、というよりこちらのほうが大御所でしょうが、この業界で知らない人はいないはず。
著者は長年、「ピロリ菌ってほんまにそんなに悪いん?」という視点で研究を続けてきて、のちに抗生物質が常在細菌に与える影響を幅広く研究しています。
特に肥満と細菌の関係に詳しいですが、細菌の多様性が失われることに早くから警鐘を鳴らしていた慧眼ある人。
(3)『土と内臓』/デイビッド・モントゴメリー、アン・ビクレー
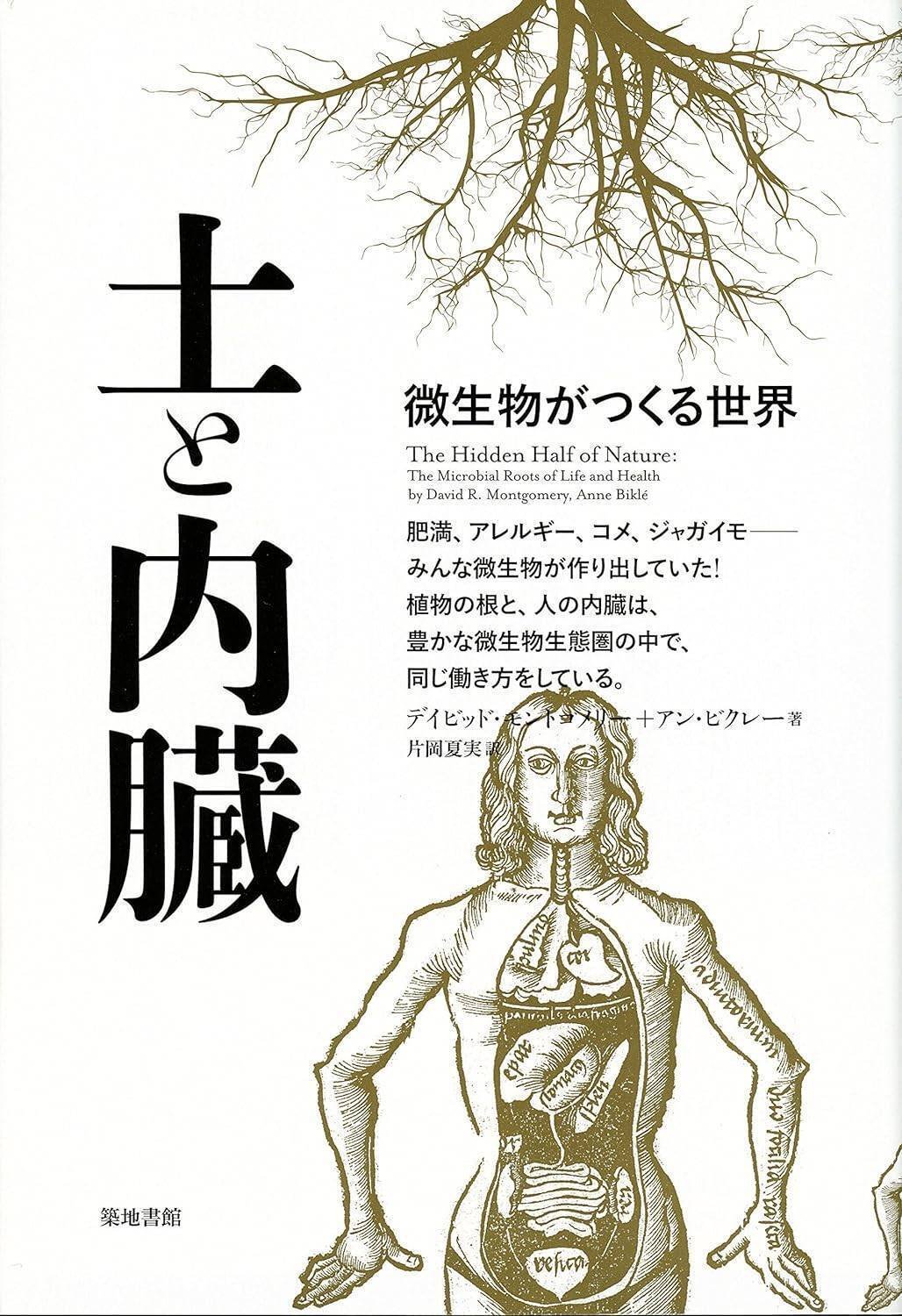
続いては2016年出版『土と内臓―微生物がつくる世界』を、愛を込めて紹介します。
地質学者の夫と環境計画のプロである妻が二人で作ったこの本は、表紙の絵と題名のインパクトだけでマーケティングをほぼ成功させていると言ってもいいんじゃないでしょうか。
そしてページを開くと、どの1ページとて裏切られることはありません。
豊かな畑に暮らす土壌微生物に焦点を当てた前半、がんを患った妻を主人公にヒト共生マイクロバイオームに焦点を当てた後半。
そのすべてが、著者たちの叡智と熱意と素晴らしい編集チームによって、芸術的にまとめられています。
そうよね、土の中とわたしたちの体って、つながってるよね!!科学的にも!
もし家が急に火事になったら、どうしても外せない小説5冊と、夫にもらった手作りのアルバムと手紙と、買ったばかりの木製ヨガブロックに次いで、まだ持てたら絶対に運び出したい一冊。(中途半端やな)
でも、仕事関係の本の中では一位やから!!(どんなフォローや)
(4)『家は生態系』/ロブ・ダン
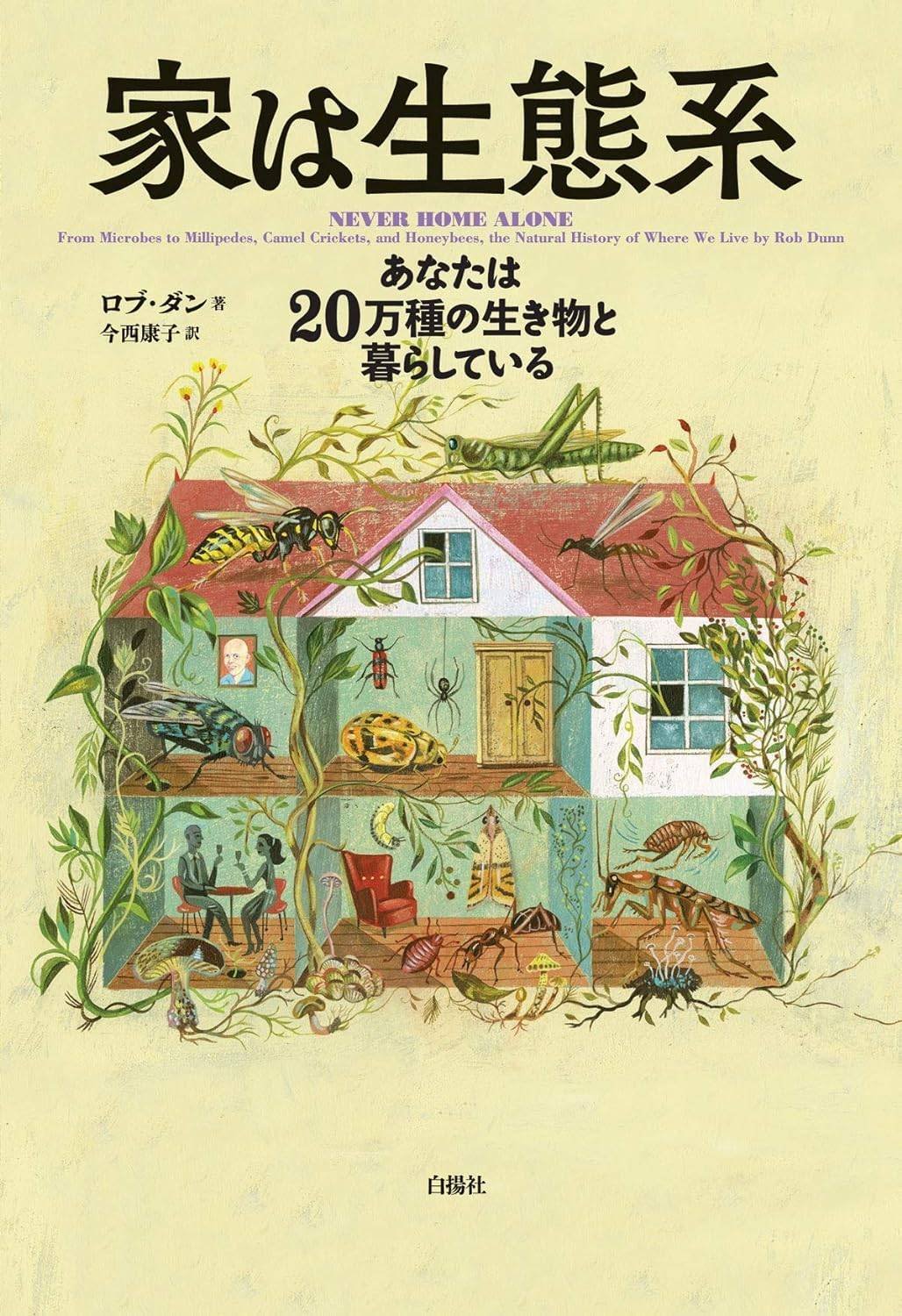
2021年に出版された新しい本である『家は生態系―あなたは20万種の生き物と暮らしている』には、ごく一部を除いて、ヒトの体に住むという意味でのヒトマイクロバイオームは出てきません。
そのかわり、私たちの家に住むマイクロバイオームを次々に紹介しています。微生物生態学といえば、これまで極限環境に出かけていって調べるのがメインでしたが、身の回りの菌たちに焦点を当てた研究がひそかに盛り上がっています。
著者はノースカロライナ州立大学教授のロブ・ダン氏で、本に掲載されている顔写真はハリー・ポッターに出てきそうな感じです。
いつのまにか、ミクロの世界が見える魔法にかかったような気分になる本。
日本で屋内環境微生物といえばBIOTAさんですよね。
はじめてウェブサイト見たときから、いつかここと仕事したいな〜と、自分を磨きながら狙っています。
自分と共生している菌たちも、身の回りの菌たちも。
目に見えないからこそ、その存在をしっかり感じたい。
5.上級編 この分野の概観をひととおり知ったあとのあなたに
ここに載せる本たちは、決して読みやすい本ではありません。
もっともっと微生物の世界にどっぷりつかっていきたいマニアたちに勧めます。
(1)『微生物が地球をつくった』/ポール・G・フォーコウスキー
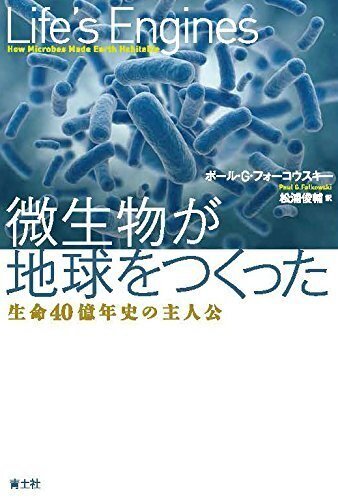
『微生物が地球をつくった -生命40億年史の主人公』をはじめて手に取ったのは、近所の図書館でした。
「おお、これは読まねば」と直感するも、貸出期限内に読み切れるような本ではないと思い、そのままブックオフオンラインで注文しました。
あのとき、2週間だけ借りて最初の方を読んでいたら、多分買っていなかったでしょう。
微生物の進化論や生化学が専門の海洋生物学者である著者の言葉は、化学な苦手な私には難解すぎました。
なので、この本は化学ができる人にとっては上級編には入らないと思われる本です。
ただ、後半は俄然面白くなってくるし、医療論文などの結果として目に見える現象の奥で何が起こっているのかを想像できるようになるので(なんとなくやけど)、読んでおいて損はないです。
というか、かなりの良書です。再読を誓っている一冊。
(2)『微生物生態学』/デイビッド・L・カーチマン
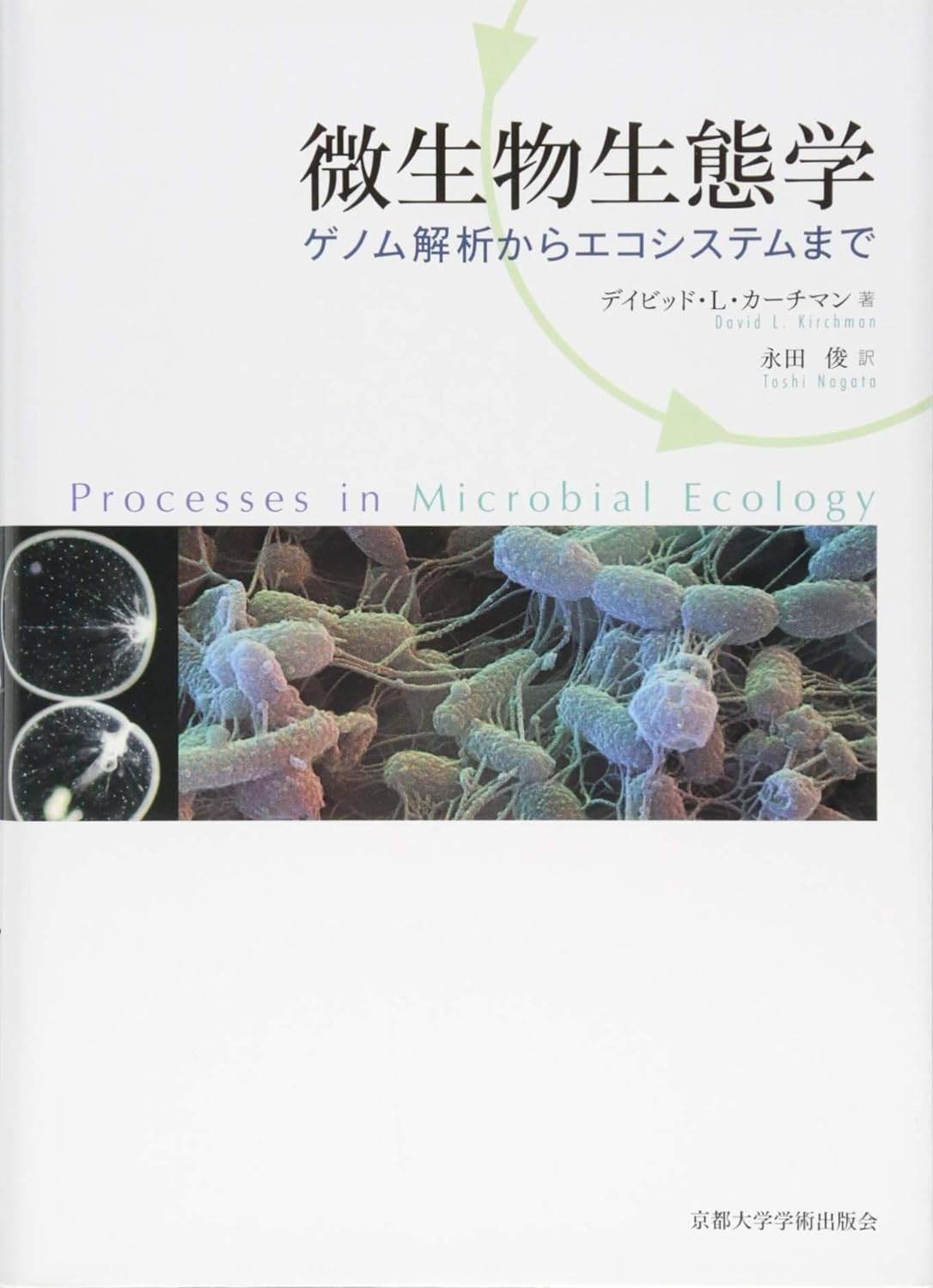
2016年に出版された『微生物生態学: ゲノム解析からエコシステムまで』は、こういう本、なかったよね! でも絶対に必要だよね! という声があちらこちらから聞こえてきそうな本です。
微生物学というのは全体ではなく部分から始まった学問で、それゆえに専門がばらばらと細分化しているフシがあるけれど、ほぼすべての生命が微生物と共生しているという事実を鑑みると、すべての(特に生物)科学者が知っておくべき分野である気もする。
そういうわけで、微生物の世界をすべて網羅しようとしたのが、本書の狙いのようです。
かなり難しく、これはもはや一般書ではなくて完全に専門書です。
いつか、この本が自分のバイブルになるよう精進しようと思いながら、最初の1割くらいを苦労して読んだところです。
今のところは、これが部屋にあると気が引き締まる、という役割しか果たせていません。
また面白そうな本があれば、紹介します。
6.番外編
(1)『発酵文化人類学 微生物から見た社会のカタチ』/小倉ヒラク
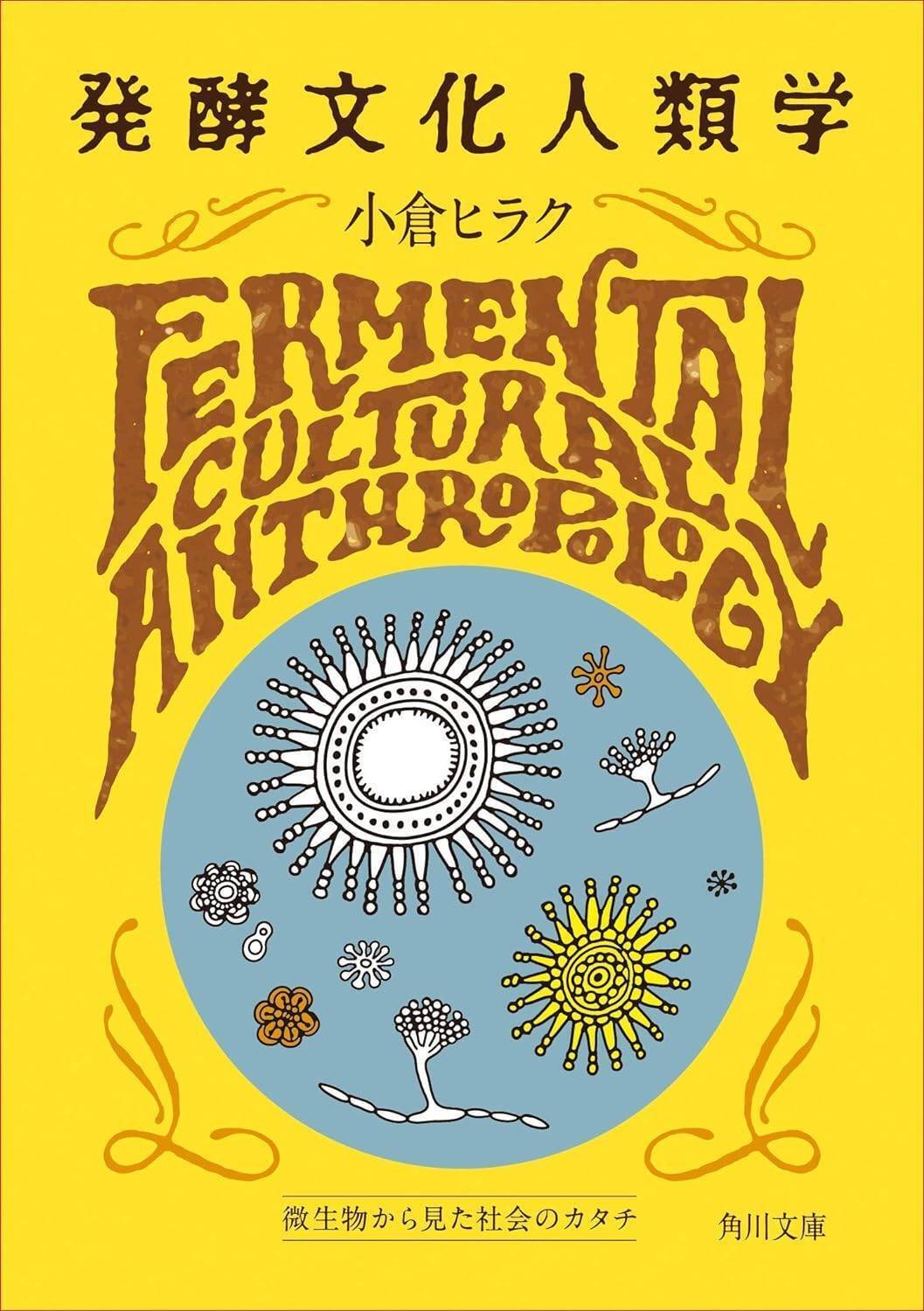
2020年に出版された『発酵文化人類学 微生物から見た社会のカタチ』は、微生物のことというより、その微生物が働いた結果としての「発酵」という現象に特に焦点を当てた一冊。
著者の小倉ヒラクさんは、もともと大学で文化人類学を専攻されており、デザイナーの仕事をされていたとのこと。
自身のアトピーや喘息が発酵食品で改善された経験から、「発酵デザイナー」として微生物に詳しいデザイナーとして活動されています。
私と同じく文系出身なのに、異様に微生物に詳しいので、私も尻に火がついた気持ちで勉強しようと決意したとともに、
微生物の世界は人文科学や哲学のような学問と重なるところが多いと感じていた自分の背中を押してくれた大切な一冊です。
最初はジャケ買いでしたけど。
本ブログ記事は、シンバイオシス株式会社微生物事業部の研究員がnoteにて作成した記事を一部変更しております。
元の投稿はこちらでご覧いただけます。
記事タイトル:ぜんぶ読んで選んだ、(入門〜上級)微生物・腸内細菌をもっと学ぶためのおすすめ一般書12選
記事リンク:https://note.com/symbiosis17/n/n2d2e6f4a96be

私たちは、私たちの食べたものでできている。
大人になると、この実感はやや薄くなってくる。
けれど、毎日ぐんぐんからだが大きくなっていく赤ちゃんを見ていると、彼らの食べるものがほんとうに彼らの体を作っているのだという感覚を抱く。
それでは、彼らの食べるものはマイクロバイオームたちのからだも作るのだろうか?
答えはほぼ間違いなくYESだ。
今日は、母乳や粉ミルク、そして離乳食がどんな菌たちを育むのか、わかっていることを紹介してみたい。
目次
- 母乳に含まれる消化不可能の糖の謎
- 謎の答え1
- 謎の答え(?)2
- まだまだある、謎の答え
- 粉ミルクと母乳神話とマイクロバイオーム
- 粉ミルクと腸内細菌
- 粉ミルクは太る説
- 離乳食のはじまりと多様性爆発
・本文中のカッコ付き番号は、記事下部の参考文献の番号を表しています。
母乳に含まれる消化不可能の糖の謎
出産によってお母さんからマイクロバイオーム一式を無事に受け取ったあと、赤ちゃんの腸でもマイクロバイオーム生態系の形成がはじまる。
出産後数日すると、複数の種類のビフィズス菌が赤ちゃんの腸で増え始める。この細菌は赤ちゃんの腸で70%〜90%まで増えることもあり(1)、乳酸菌と並んで離乳食が始まるまでの二大構成員となる。
どうしてこの細菌が急に増えてくるのか?
その理由は、母乳の成分を見ればわかる。
母乳には、乳糖、そして脂質に続いて三番目に多い成分であるオリゴ糖(Human milk oligosaccharides ,HMOs)が含まれる。
このオリゴ糖は、生まれた赤ちゃんを含むヒトには消化できない。これを消化して栄養に変えてくれるのがビフィズス菌たちだ。
母親はなぜ、赤ちゃんが直接消化できない成分をわざわざ母乳に含ませるのだろう?
生まれたばかりの赤ちゃんは、せいぜい一回の授乳で数十グラムの母乳しか飲めないというのに。
謎の答え1
第一の理由は、オリゴ糖が病原菌の「専門クレーム処理窓口」になってくれることだ。
未熟で不安定な赤ちゃんの腸マイクロバイオームは、ちょっとしたことで大きく乱れやすい。それでも、外界は容赦なく次々と病原体を赤ちゃんに送り込もうとする。
そこでオリゴ糖が頼りになる。
赤ちゃんを清潔に保つことに神経質になることは母親として自然な感情だが、心配することはない。
母乳に含まれる130種類ものオリゴ糖のうち数十種類は、特定の病原体にぴったりフィットして、病原体が腸壁に付着して増殖するのを防いでくれる(2-P315)。
あらゆるタイプのクレーマーが社長室に殴り込まないよう、クレーマーのタイプごとに専門のクレーム処理スタッフがいるかのようだ。
謎の答え(?)2
次の仮説。
これが答えかどうかは、解釈による。
母親は(母乳は)わざわざビフィズス菌を増やしたいのだと考えてみるとどうだろう。この仮説を支持する研究結果は、実は山ほどある(3)。
ビフィズス菌は、短鎖脂肪酸(乳酸、酢酸など)と呼ばれる有益な物質を出してまだ未熟な赤ちゃんの免疫系を育てるのに役立っている。さらには、腸内のpHを下げて他の菌たちを増えにくくしたり、腸壁のバリアを強くすることで、日々赤ちゃんの体に入り込もうとする病原菌から赤ちゃんを守る。
生後6ヶ月くらいまでは風邪をひきにくいという話を聞いたことはないだろうか?
この理由は、胎内にいるときや母乳を通して母親から抗体(病原菌などをやっつける免疫細胞)をもらうからだと説明されているが、出産時に受け取るビフィズス菌もひと役買っていることは間違いなさそうだ。
まだまだある、謎の答え
そのほかにも、ビタミンB2や葉酸の生成、ワクチンの効きを良くする働きなども知られている。
さらに、母乳そのものにもビフィズス菌をはじめとする母親由来の腸内細菌たちが含まれているとする研究(2-P316,4)も報告されている。
母乳は、ほかにも200種類以上のヒトが消化できない栄養を含んでいる。これらは無駄に存在するわけではなく、赤ちゃんの体内に住む無数のマイクロバイオームたちを育んでいるのかもしれない。
そしてそれらの存在意義は、決して謎ではなくて、綿密に計算された「当たりまえ」なのかもしれない。
生命というものはなんと賢くてかっこいいのか。こういう仕組みを知るたびに、感動して震える。
粉ミルクと母乳神話とマイクロバイオーム
「母乳神話」という言葉を聞いたことがあるだろうか。
母乳のメリットを強調するあまり、一部の母親にとっては精神的に負担になっている言葉でもある。
たしかに、母乳育児は先祖代々受け継がれてきただけあっていくつもメリットがある。母乳に含まれる成分は赤ちゃんの健康維持に大いに貢献するし、授乳による母子の絆形成なども挙げられている。
赤ちゃんの健康上の理由以外から母乳育児を選ぶ人もいる。経済的であること、ミルクを作ったり哺乳瓶を洗う手間がいらないこと。
授乳をしないと胸が張って乳腺炎になる人もいる。
しかし、母乳が出にくいお母さんもいれば、仕事の都合や本人の体力などの理由で粉ミルク育児、母乳/ミルク混合育児を選ぶ家庭もある。
いずれの場合でも、周りの意見に左右されすぎず、両親がいいと思える方法を選ぶのがいいのだろう。お母さんが元気で笑顔なのが子どもにとって一番大事だ、という考え方もあるし、実際にそれが一番の正論に思える。
粉ミルクと腸内細菌
ここでは、母乳神話を支持することになってしまうかもしれないが、マイクロバイオームの観点から粉ミルクの影響を考えてみたい。
強調しておきたいのは、あくまでも粉ミルク育児を否定するものではないということだ。そうでなくとも産後のお母さんは肉体的に本当に大変だし、粉ミルク育児にもメリットはたくさんあるのだから。
母乳だけを飲んでいる赤ちゃんの腸内は、乳酸菌(L. johnsonii/L.gasseri, L. paracasei/L. caseiなど)やビフィズス菌(B. longum)が多勢を占めている。これらの菌たちは、プロバイオティクスとしてサプリメントに含まれていることも多い。
一方で、粉ミルクを飲む赤ちゃんは別な細菌たちの割合が増える。Clostridium difficile、Granulicatella adiacens、Citrobacter spp.、Enterobacter cloacae、Bilophila wadsworthia、Bacteroides fragilis、 E. coliなどがその一例だが、これらの菌には「日和見病原体」と呼ばれる菌たちも含まれている。
日和見病原体は普段は悪さをしないけれど、なんらかの原因で赤ちゃんの免疫力が落ちたときなどに病原性を発揮することがある。
以前の記事で紹介したB. longumとB. adolescentisに注目すると、母乳を飲む赤ちゃんには前者が多く、粉ミルクを飲む赤ちゃんには後者が多い。
どちらも似たような機能を果たすけれど、長い進化の歴史を経て、ヒトはB. longumとより仲がいいのかもしれない。
粉ミルクは牛の乳から作られているが、母乳に含まれるオリゴ糖と粉ミルクに含まれるオリゴ糖の構造は、最大でも25%ほどしか重複しない。
各メーカーが企業努力を続けてはいるが、母乳のオリゴ糖構造を粉ミルクで再現するには至っていない。
その他にも母親由来の抗体など、母乳でしか提供できない成分はやはり存在する。
超低出生体重児など、特に母乳のメリットを受けるべき赤ちゃんを対象とした母乳バンクも存在している。
粉ミルクよりも母乳を、と願う母親たちが自分で母乳を与えられない事情を抱えながらも利用を検討できる無料の制度だ。低温殺菌などの工程で母乳の成分が一部失われているとはいえ、母乳バンクの存在が支えになった母子も多くいるだろう。
一般財団法人日本財団母乳バンク(東京)、一般社団法人日本母乳バンク協会(東京)、藤田医科大学(愛知)が2023年に開設した母乳バンクの3箇所があるが、いずれもNICUでの治療など特別な理由がないと利用はできない。
粉ミルクを選ぶ場合、たしかに初期のマイクロバイオーム形成に影響をあたえる。
それでも、菌たちは様々な機能を重複して、そして連携して担うことができることを思い出してほしい。
たとえマイクロバイオームの生態系が違っても、同じ機能を果たせればそれでいいのだ。あるいは少々もろい生態系になるかもしれないけれど、共生マイクロバイオームが完成するにはまだ時間がある。
最新の研究では、母乳に似せた成分を加えた粉ミルクでは、腸内細菌の組成やその機能(短鎖脂肪酸の産生能など)が母乳に遜色ないという報告も出ているので、粉ミルクメーカーの努力にも頭が下がる。(5)
ただ、この報告はあくまで試験管内での実験段階であることに注意したい。
粉ミルクは太る説
もうひとつだけ。
「粉ミルクは太る」というのは、母親たちのあいだで通説になっている。たしかに、ミルクで育っている赤ちゃんは育ちがいい。けれど、その差は年齢を重ねるごとに縮まり、将来の肥満の原因にはならないだろうという見方が強い。
ヒトが健康に育つかどうかには、無数の因子が存在する。完璧な育児は存在しない。
そのときそのときにできることをしていくために、ここで書いたことが少しでも参考になれば幸いだ。
離乳食のはじまりと多様性爆発
もちろん、出産時に受け取るのは乳酸菌とビフィズス菌だけではない。離乳食が始まると、この他の菌たちが急に増えてくる。
離乳食の中に、それを消化するための大量の菌が含まれるのだろうか?
そうは考えにくい。
ひと昔前までは進化の痕跡として無駄な臓器だとされていた組織がある。
虫垂(一般にモウチョウといわれる場所)だ。
実は虫垂は、腸の主な流れから少し外れたところにあるせいか、さまざまな細菌たちが流されずに密集して暮らしており、菌たちの隠れ家と呼ばれることもある。
そしてこの虫垂が、腸のマイクロバイオーム生態系の形成において非常に重要な司令塔のような役割も果たしているのではないかということが予測されている。
出産のとき、その後の生活で受け取った菌たちは、一時的に虫垂に隠れていることができ、そのときが来たら虫垂から大腸というより大きな世界のそれぞれの目的地に出ていけるのではないだろうか。
そうだとすれば、母親譲りの菌たちは離乳後も赤ちゃんのからだづくりを支えてくれるパートナーだということになるだろう。
一方で、スウェーデンのコホート研究では、赤ちゃんの腸内細菌の構成を大きく変えるのは、離乳食のはじまりというよりは母乳量の減少(または完全な離乳)によるものだとの見方を示している。
いずれにせよ、へその緒から栄養をもらっていた赤ちゃんが母乳栄養に変わるタイミング、そこからさらに様々な栄養源を消化吸収できるようになるタイミングで、腸内細菌たちがその顔ぶれや働きを柔軟に変えているのだ。
私たちの遺伝子が時と場合に応じてその発現度合いを変えるように、マイクロバイオームの生態系も健やかな変化をもって応じてくれている。
尊い。
1. Mueller NT, Bakacs E, Combellick J, Grigoryan Z, Dominguez-Bello MG. The infant microbiome development: mom matters. Trends Mol Med. 2015;21(2):109-117. doi:10.1016/j.molmed.2014.12.002
2. Collen A, アランナコリン. あなたの体は9割が細菌: 微生物の生態系が崩れはじめた. 河出書房新社; 2020.
3. Hegar B, Wibowo Y, Basrowi RW, et al. The Role of Two Human Milk Oligosaccharides, 2′-Fucosyllactose and Lacto-N-Neotetraose, in Infant Nutrition. Pediatr Gastroenterol Hepatol Nutr. 2019;22(4):330-340. doi:10.5223/pghn.2019.22.4.330
4. Martín R, Jiménez E, Heilig H, et al. Isolation of Bifidobacteria from Breast Milk and Assessment of the Bifidobacterial Population by PCR-Denaturing Gradient Gel Electrophoresis and Quantitative Real-Time PCR. Appl Environ Microbiol. 2009;75(4):965-969. doi:10.1128/AEM.02063-08
5. Borewicz K, Brück WM. Supplemented Infant Formula and Human Breast Milk Show Similar Patterns in Modulating Infant Microbiota Composition and Function In Vitro. Int J Mol Sci. 2024;25(3):1806. doi:10.3390/ijms25031806
本ブログ記事は、シンバイオシス株式会社微生物事業部の研究員がnoteにて作成した記事を一部変更しております。
元の投稿はこちらでご覧いただけます。
記事タイトル:菌の視点からみる母乳とミルク、そして離乳食の荒波
記事リンク:https://note.com/symbiosis17/n/na0a3bf86b3ef

前回の記事では、腸内細菌の生態系が幼少期に決まることや、赤ちゃんが1歳までに獲得する腸内細菌の顔ぶれや多様性について話をした。
今日は、彼らが実際に赤ちゃんの成長にどれほど貢献してくれているか、その機能を果たすためにどれほど強固なバックアップ体制を築いているかを見ていこう。
※本記事は「腸内細菌は何歳までに決まる? 赤ちゃんから子どもへの成長とともに歩む菌たちのこと」シリーズの一部です。
別のシリーズ「全プレママ&パパに届けたい、妊娠・出産とマイクロバイオーム全まとめ(腸内細菌、膣細菌を中心に)」(後日投稿予定)と併せて読むことを推奨します。
目次
- 遺伝子から機能を予測する
- 違う菌が同じ働きをする「機能の冗長性」
- 菌たちのバックアップ体制
・本文中のカッコ付き番号は、記事下部の参考文献の番号を表しています。
遺伝子から機能を予測する
細菌たちを含むマイクロバイオームの持つ遺伝子を、すでに明らかになっている「遺伝子→機能」のデータベースに当てはめることで、その機能を推測するという方法がある。(KEGG、COGsなどのデータベースが利用される場合が多い)
この方法を通して赤ちゃんの腸内細菌を眺めてみると、たとえばこのようなことが言える。
- 生後間もないうちは、からだを作る材料を運ぶための輸送体のキャパシティを増やす遺伝子が多い。
- DNAの合成や葉酸(ビタミンB9)を合成する細菌は生後間もない赤ちゃんに多い。
- 月齢が上がると、アミノ酸やビタミンの合成により焦点が当てられる。
- 母乳が減り、離乳食が導入されはじめると、さまざまな栄養源を消化吸収できるような機能が備わっていく。
- 細菌たちの構成や機能は、1歳が近づくにつれて母親のそれらに似ていく。
- 1歳の赤ちゃんの腸内細菌には、薬物輸送体の遺伝子が多い。(おそらく抗生物質の影響)(1)
1歳までの赤ちゃんの腸内細菌たちは、たとえ顔ぶれが違っていても、多くの場合はこれらの機能をきちんと果たしてくれる。
菌によって性質も代謝機能も違っているのに、どうしてなのだろう?
そのヒントは、マイクロバイオームや人体にかかわるあらゆるところで見つかる「機能の冗長性」にある。
違う菌が同じ働きをする「機能の冗長性」
たとえば、赤ちゃんによく見られる2種類のビフィズス菌を例に挙げてみよう。B. longumとB. adolescentisだ。
これらの菌は生後間もない頃は共にその数を増やしていくが、4ヶ月の時点ではどちらか片方が多くなっている。これは、2種の菌のあいだに競合関係、または生態学の用語で「多様化選択」と呼ばれる関係が成り立っているということができる。(2,3)
どちらが残るかを決定するのは、母乳の有無だ。B. longumは母乳に含まれるオリゴ糖を積極的に栄養源とするが、B. adolescentisはそうではない。
粉ミルクで育った赤ちゃんの腸ではB. adolescentisが増えている。
余談だが、大人でビフィドバクテリウム属を持つ場合は後者の菌が優勢だ。
どちらが増えるのがいいかという議論は、今のところできない。
「より環境に適したもの」が増殖していることには間違いないが、これらはいずれもビフィドバクテリウム属の菌で、ゲノム配列も予測される機能も似通っている。
たとえば、ビフィドバクテリウムの場合は免疫機能の活性などがそれにあたる。
菌たちのバックアップ体制
同じ機能を持ちながらも共存している菌たちは他にも数多く存在する。
「機能の冗長性」と呼ばれるこの状態は、菌たちによるバックアップ体制だ。
菌たち自身に必要な、あるいは彼らのすみかであるヒトの生存に必要な機能をいくつもの菌たちが重複して受け持つことの意義はなんだろう。
それは簡単に言えば、環境変化に耐えうる強さだ。
ある機能を担うのに一種類の細菌しか残さなければ、なんらかの原因でその種の細菌がいなくなってしまうと途端にネットワーク全体に影響が及ぶ。そうならないよう、複数の菌たちが柔軟に同じ機能を担い合っている。
会社で同じ業務を複数の人間が行っていれば、誰かが病気をしたり、仕事を辞めてしまっても全体におよぶ支障は少なくて済む。それと同じ仕組みを、菌たちも採用しているようなのだ。
ひとりひとりの人間は違うけれど、営業職、経理職、開発職、カスタマーサポート職、研究職などの同じ職種内ならば互いに抜けた穴を埋め合えるのだ。
だから、赤ちゃんが出会う菌の順番が違えばその顔ぶれも違うけれど、同じ機能を担うことが可能になるのだ。
ただし、いくら機能を重複して担っているとはいえ、生態系の柔軟性を超えて撹乱が起こることもある。場合によっては、機能に対するバックアップ体制を十分に取れない、もろい生態系しか獲得できないケースもあるかもしれない。
ここには、すでに述べた「菌の獲得プロセス」に影響する要因の違いや、幼少期の抗生物質の使用などが挙げられるだろう。
抗生物質などの環境要因については他の機会に譲るとして、次の記事では赤ちゃんの栄養源が腸内細菌の形成にどのように影響するかを見ていこう。
母乳やミルク、それから離乳食は、どんな細菌たちを育てるのだろう。
1. Odamaki T, Kato K, Sugahara H, et al. Age-related changes in gut microbiota composition from newborn to centenarian: a cross-sectional study. BMC Microbiol. 2016;16:90. doi:10.1186/s12866-016-0708-5
2. Bäckhed F, Roswall J, Peng Y, et al. Dynamics and Stabilization of the Human Gut Microbiome during the First Year of Life. Cell Host Microbe. 2015;17(5):690-703. doi:10.1016/j.chom.2015.04.004
3. Roswall J, Olsson LM, Kovatcheva-Datchary P, et al. Developmental trajectory of the healthy human gut microbiota during the first 5 years of life. Cell Host Microbe. 2021;29(5):765-776.e3. doi:10.1016/j.chom.2021.02.021
本ブログ記事は、シンバイオシス株式会社微生物事業部の研究員がnoteにて作成した記事を一部変更しております。
元の投稿はこちらでご覧いただけます。
記事タイトル:赤ちゃんとマイクロバイオーム “First 1000 Days”(最初の1000日)の重み
記事リンク:https://note.com/symbiosis17/n/n33f6d6e08a72

“First 1000 Days”ー最初の1000日ー、この表現はヒトとマイクロバイオームの関係を語るうえで大きな意味を持つ。
1000日とは生まれてから約3年間のことを指し、この期間に形成されたマイクロバイオームの生態系は、その後の長い人生を共に歩むことになるパートナーたちの顔ぶれを決めるベースとなる。
この数字は、どこから出てきたのだろう?
※本記事は「腸内細菌は何歳までに決まる? 赤ちゃんから子どもへの成長とともに歩む菌たちのこと」シリーズの一部です。
別のシリーズ「全プレママ&パパに届けたい、妊娠・出産とマイクロバイオーム全まとめ(腸内細菌、膣細菌を中心に)」(後日公開予定)と併せて読むことを推奨します。
目次
- 腸内細菌は◯歳までに決まる?
- 1歳までの腸内細菌
- 腸内細菌の顔ぶれ
- 多様性
腸内細菌は◯歳までに決まる?
Maria Gloria Dominguez-Bello氏やRob Knight氏に加え、現代微生物学の権威とも言えるJeffrey I. Gordon氏らが共同で2012年に発表した論文は、マイクロバイオーム(ここでは腸内細菌)と年齢や地域の関係を網羅的に示した最初の研究成果だ。
彼らは、アメリカ、ベネズエラの先住民、マラウイの3か国の人々を対象としたコホート研究を実施し、いくつかの興味深い発見をした。
そのなかのひとつが、腸内細菌の構成は3歳までに決まるというものだ。
もっともこの傾向はベネズエラとマラウイの人々により強く見られ、アメリカの子どもたちは1歳の時点ですでに大人と同じような腸内細菌の構成を持っていた。
もしかしたら、腸内細菌の成熟スピードには地域差があるのかもしれない。
3年後にスウェーデンのコホート研究(2,3)をはじめた研究者たちは、スウェーデンの子どもたちの場合は5歳時点でもまだ大人と同じレベルには腸内細菌の成熟が見られないと結論づけている。
他にもデンマークの4歳説(4)やアメリカの5歳以上説(5)など議論は絶えないが、おおむね幼少期に共生マイクロバイオームの生態系のベースができあがることや、心身の発達が著しい幼少期におけるマイクロバイオームの影響に焦点を当てている点は共通している。
そして言うまでもなく、命がお腹に宿った瞬間から、母親のマイクロバイオームは変わり始め、胎児をお腹で育てるのに適した構成へ、さらには誕生の瞬間に胎児に手渡すべき構成へと変化していく。
受胎の瞬間から幼少期まで、マイクロバイオームたちはそのときどきに最適な生態系を柔軟に築きながら、ヒトの発達を手助けしているようだ。
1歳までの腸内細菌
ヒトは他の動物と比べても未熟な状態で生まれてくる。
つまり、生まれてからしばらくのあいだは非常に不安定な状態にあり、同時に成長スピードも著しいということが言える。
おおむね3キロほどで生まれてくる赤ちゃんは、一ヶ月検診のときにはさらに1キロ増え、3ヶ月を迎えるころには体重は倍に増える。
首が据わり、早い子では寝返りをしはじめるようになる。
子育てをしたことのある人なら、赤ちゃんが一年間でできるようになることの多さを知っているだろう。
では、1歳までの腸内細菌はどのような変遷をたどるのだろう?
1歳までの赤ちゃんを対象とした大規模なコホート研究はまだまだ少ない。
それでも、上述したスウェーデンの研究成果や中国の研究(6)を中心に、赤ちゃんと腸内細菌の共生模様が少しずつ明らかになってきている。
腸内細菌の顔ぶれ
生まれてすぐの赤ちゃんの腸に棲む細菌たちは、通性嫌気性菌と呼ばれる菌たちが主要メンバーとなる。
エシェリヒア・コリ(Escherichia coli)、スタフィロコッカス(Staphylococcus)、ストレプトコッカス(Streptococcus)などに代表されるこれらの菌たちは、酸素があってもなくても生きていける。
その後すぐに、ビフィズス菌、バクテロイデス、クロストリジウムなどの偏性嫌気性菌と呼ばれる菌たちが増えてくる。彼らは酸素があると生きていけないが、私たちヒトの大腸ではマジョリティだ。
つまり、おそらくこういうことが言える。
生まれたての赤ちゃんは、大人のように大腸が強い嫌気的環境ではない。
そこで、酸素があっても生きていける菌たちが酸素を消費し、大腸を嫌気的環境に向かわせ、その後に増えるべき偏性嫌気性菌たちのための場所をつくる。
未熟な赤ちゃんの大腸があるべき姿になるために、腸内細菌たちが手伝ってくれているのだ。
多様性
赤ちゃん個人の腸内細菌の多様性(α多様性と呼ぶ)は、生まれてすぐがもっとも低く、1歳に向かうにつれて増加し続けていく。
赤ちゃんの成長を促し、病原菌から守るために最初は選ばれし菌たちだけが活躍し、その後の生活で段々と他の菌たちを迎え入れていくのだ。
菌たちが多様性を高めながら生態系をつくりあげていくさまは、柔軟で巧妙だ。初期に活躍する菌たちが次に棲みつく菌たちの環境を整え、ときには棲み着く菌を取捨選択していく。
そして、無事に生態系に含まれることになった菌たちは、別の菌の代謝物質などを利用しながら、相互に関連したネットワークを編み上げていくのだ。
一方で、ある赤ちゃんを他の赤ちゃんと比べたときの差の度合い(β多様性と呼ぶ)は、赤ちゃんの月齢が低いほど大きく、その個人差は月齢が上がるごとにだんだんと小さくなっていく。
ここから言えることは、赤ちゃんが共生する菌たちを獲得する初期のプロセスには、大きな個人差があるということだ。
このプロセスを左右する要因は、すでに見たような分娩方法や地域差に加え、あとの記事で見るように栄養源の差なども挙げられるだろう。
どんな菌たちがどのようなスピードで増えるのが理想的なのかはまだわかっていない。しかし、この初期の「個人差」が赤ちゃんの病気のかかりやすさや、その後の人生での疾患リスクにかかわっていそうだということが、少しずつ明らかになってきている。
菌たちは、赤ちゃんの発達において具体的に何をしているのだろう?
次の記事では、機能の観点から菌の働きを見てみよう。
本ブログ記事は、シンバイオシス株式会社微生物事業部の研究員がnoteにて作成した記事を一部変更しております。
元の投稿はこちらでご覧いただけます。
記事タイトル:赤ちゃんとマイクロバイオーム “First 1000 Days”(最初の1000日)の重み
記事リンク:https://note.com/symbiosis17/n/na6a44e2c9bfa

私たちのからだは、生まれてから数ヶ月のあいだに数倍になる。
そしてその急激なカーブは、多少ゆるやかになっていくものの、思春期まで続く。
精神的な発達も同じくらいダイナミックだけれど、33歳の私だって、まだ精神的には成長している気がする。
ぐんぐん大きくなった身長は中高生を最後に上げ止まり、あとは横に伸びる可能性が残されているだけになる。
肌や脳、臓器などの細胞も日々入れ替わりながら、その機能はそれ以上発達することはなく、むしろだんだんと下り坂を描いていく。
腸内細菌をはじめとする、私たちの体で共生するマイクロバイオームたちはどうだろう。
彼らは私たちの成長のそばでどんなふうに「成長」し「機能」するのだろう。
出産のときにお母さんから受け継いだ共生マイクロバイオームは、赤ちゃんや子どもたちの健康をどんなふうに支えていくのだろう。
そしてもし、マイクロバイオームとの健やかな共生が幼少期に崩れてしまったら、どんなことが起こり得るのだろう。
これから、何回かにわけて赤ちゃんと子どもたちのマイクロバイオームに焦点を当てていきたい。
本シリーズは、
「全プレママ&パパに届けたい、妊娠・出産とマイクロバイオーム全まとめ(腸内細菌、膣細菌を中心に)」シリーズと併せて読むことを推奨します。
※「全プレママ&パパに届けたい、妊娠・出産とマイクロバイオーム全まとめ(腸内細菌、膣細菌を中心に)」シリーズについては随時公開予定です。
目次
- 赤ちゃんとマイクロバイオーム “First 1000 Days”(最初の1000日)の重み
- 赤ちゃんの腸内細菌が担う機能と、ダブり機能の重要性
- 菌の視点からみる母乳vsミルク、そして離乳食の荒波
- 幼児、そして子どもたちとマイクロバイオーム
- どの国に生まれるかでマイクロバイオームはこんなに変わる
- 腸内細菌が乱れると子どもは太るのか? 抗生物質と肥満の関係
- 栄養失調だから腸内細菌が乱れるのか、その逆なのか。バングラディシュとアフリカの子どもたちの腸から学ぶ。
- 子どもたちの免疫力は微生物と一緒につくろう
- 子どもたちのこころの発達には、微生物が欠かせない
1.赤ちゃんとマイクロバイオーム “First 1000 Days”(最初の1000日)の重み
2.赤ちゃんの腸内細菌が担う機能と、ダブり機能の重要性
3.菌の視点からみる母乳vsミルク、そして離乳食の荒波
4.幼児、そして子どもたちとマイクロバイオーム
離乳食が終わりの段階を迎える1歳代以降も、マイクロバイオームはまだ発達の途上にある。彼らはその顔ぶれや働きを変えながら、乳幼児期の心身の発達を助けているようだ。
微生物があふれる外的環境にさらされることで、マイクロバイオームの生態系は急速に発達する。夏の積乱雲のように。
毎日のように新しい菌たちが子どもたちと出会う。
生まれてくるとき、母親によって与えられたマイクロバイオームの多様性は決して後戻りしない。
それでもなお、1歳以降の子どものマイクロバイオーム生態系はまだ不安定な状態だ。
母乳や離乳食のほかにも、子どもたちのマイクロバイオーム生態系に影響をあたえる要因はたくさんある。
生まれた国、食べるもの、住環境、衛生状態など、多数の因子が子どもたちのマイクロバイオームの構成、その機能を左右しているらしい。
日々新しいことを学び吸収していく子どもたち自身と同じように、彼らの繊細なマイクロバイオーム生態系に加わるかどうかの関門の扉をたたく微生物は無数にいる。
特に腸では、免疫系と相互にかかわることで微生物の選りすぐりをしている。環境中にいる雑多な微生物群集にくらべて、ヒトの腸に棲みつくかどうかの判断には強い選択圧がかかる。
真新しい家に、家具や日用品をどのように配置するかは、その後の住み心地に大きく影響する。
同じように、人生初期にどのマイクロバイオームを腸に迎え入れるかは、その後の生き心地にかかわるのかもしれない。
生態系が安定するほど、つまり年齢を重ねてマイクロバイオームができあがるにつれ、新しい種は棲みつきにくくなる。
大人がヨーグルトを食べても、乳酸菌が腸に定着しない理由はここにある。食生活によって変更できるマイクロバイオームもあるが、その話は別の機会にすることにしよう。
一方で、小さな生態系を乱す要因はそこらじゅうにある。
幼少期の抗生物質投与、栄養の不足した食生活、睡眠不足、行き過ぎた殺菌など挙げればきりがないが、乱れたマイクロバイオームはどんな結果を子どもたちに残すのだろう?
5.どの国に生まれるかでマイクロバイオームはこんなに変わる
随時公開予定です。
6.腸内細菌が乱れると子どもは太るのか?抗生物質と肥満の関係
随時公開予定です。
7.栄養失調だから腸内細菌が乱れるのか、その逆なのか。バングラディシュとアフリカの子どもたちの腸から学ぶ。
随時公開予定です。
8.子どもたちの免疫力は微生物と一緒につくろう
随時公開予定です。
9.子どもたちのこころの発達には、微生物が欠かせない
随時公開予定です。
本ブログ記事は、シンバイオシス株式会社微生物事業部の研究員がnoteにて作成した記事を一部変更しております。
元の投稿はこちらでご覧いただけます。
記事タイトル:腸内細菌は何歳までに決まる?赤ちゃんから子どもへの成長とともに歩む菌たちのこと
記事リンク:https://note.com/symbiosis17/n/n7c6008904c33