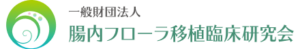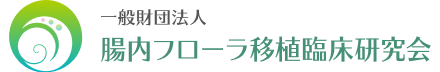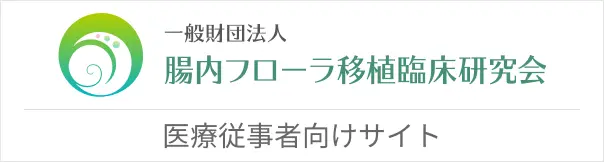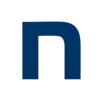便移植は、潰瘍性大腸炎などの消化器疾患をはじめとした多様な疾患に対する新たな治療法として注目されています。
腸内フローラ*のバランスを整えることで、症状の改善が期待されます。
(*腸内細菌の集まり、またそれを含む微生物群)
研究によると、便移植は難治性の潰瘍性大腸炎の患者において、症状の緩和や回復を促進することが示されています。また、便移植は従来の治療法と併用することも可能で、より良い結果を得ることができると言われています。
便移植とは
便移植とは、健康なドナーから採取した便から不純物を取り除き、患者の腸内に移植する治療法です。
この方法は、主に腸内フローラのバランスを回復させる目的で行われます。
腸内フローラが乱れると、消化器疾患の症状が悪化することがありますが、便移植によってドナーの健康な腸内細菌叢の生態系をまるごと移す(移植する)ことで、健康を取り戻せると期待されています。
海外では、2000年代に欧米でC. difficile腸炎(CDI)が深刻な社会問題となり、FMTが有効であると注目されはじめました。
また、便移植は、特に潰瘍性大腸炎やクローン病などの難治性疾患を持つ患者に対して有効であると言われています。臨床研究によると、便移植を受けた患者の多くが症状の改善を体験しており、一部の患者では寛解が見られることもあります。
ただし、便移植は医療現場での厳密な管理の下で行われる必要があります。
ドナーの選定や採取された便の検査が不可欠であり、安全性を確保することが重要です。
便移植の効果
便移植は、腸内の微生物バランスを正常化することを目的とした治療法です。
特に、潰瘍性大腸炎やクローン病の患者において、症状の改善が期待されています。
腸内フローラの乱れは、これらの疾患の発症や悪化に関与していると考えられています。
実際に便移植を受けた患者の多くが、腹痛や下痢、便秘といった症状の緩和を実感しています。また、腸内の炎症が低下し、病状が安定するケースも見られています。
これは、移植された便中の有用な微生物が患者の腸内で増殖し、炎症を抑える働きをするためです。
ただし、便移植の効果は個人差が大きく、必ずしも全ての患者に効果があるわけではありません。治療方法としての選択は、医療従事者との十分な相談、診断等を経て行うことが重要です。
腸内細菌叢の調整
腸内細菌叢は、私たちの健康に大きな影響を与える重要な要素です。
特に、潰瘍性大腸炎やクローン病といった消化器疾患では、腸内の微生物バランスが崩れることが炎症を引き起す一因となり、様々な症状が現れます。
便移植は、腸内細菌叢を調整する手段として注目されています。
健康なドナーの便を移植することで、腸内の有用な微生物を補充し、バランスを回復させることが狙いです。この治療法により腸内環境が整うことで、炎症が抑制され、症状の改善が期待できます。
しかし、腸内細菌叢の調整は個人差が大きいため、全ての患者に劇的な効果が現れるわけではありません。
腸内環境の改善には時間がかかることも多く、医療従事者との連携が不可欠です。
患者ひとりひとりの状態に応じた治療法を選択することが、より良い結果を引き出す鍵となります。
潰瘍性大腸炎への効果
潰瘍性大腸炎に対する便移植の効果は、多くの研究で示されています。
主な効果としては、腸内フローラの多様性を回復させることが挙げられます。
潰瘍性大腸炎は、有益な細菌の減少や腸内の一部の細菌の偏った増加、腸内細菌の多様性低下が関与しているため、健康なドナーを通じて新たな細菌(より広くは微生物全体)を導入することが症状の改善に繋がります。
具体的には、便移植を受けた患者の中には、腹痛や下痢の頻度が大きく減少したり、慢性的な便秘から解放されたケースも多く見られます。
また、医療機関でのデータに基づくと、一部の患者では炎症マーカーが低下し、炎症のコントロールが良好に行われたという結果もあります。
ただし、便移植の効果は、患者各々の腸内環境や治療歴によって異なることがあります。そのため、医師と相談しながら自分に合った治療法を選ぶことが重要です。
他の疾患への応用
便移植は潰瘍性大腸炎の治療にとどまらず、他の疾患への応用も広がっています。
最近の研究では、腸内フローラとさまざまな病気の関連性が明らかになりつつあります。
例えば、下痢型過敏性腸症候群や抗生物質関連下痢などの疾患にも便移植が試みられています。これらの疾患では腸内のバランスの崩れが影響を与えているため、便移植によって有用な微生物を導入し、症状の改善が期待されます。
さらに、肥満や糖尿病などの代謝性疾患にも腸内環境の影響が指摘されています。便移植を通じて腸内フローラを改善することで、体重管理や代謝の改善に寄与する可能性があるのです。
ただし、これらの他の疾患への応用についてはまだ研究段階にあり、エビデンスが確立されていないため、慎重な判断が求められます。医療従事者とよく相談し理解を深めて進めることが大切です。
便移植の方法
便移植の方法は、まず健康なドナーを選定することから始まります。
ドナーは、感染症や消化器系の疾患がないことを確認するため、十分なスクリーニングが行われます。これにより、安全な便が確保されます。
次に、ドナーから採取した便を調製します。通常、便は生理食塩水等の溶媒を加え、不純物を取り除くことで滑らかな状態にされます。この準備を経て、患者に移植するための手続きが行われます。
便移植の方法には、内視鏡を使用して腸内に直接便を注入する方法や、カプセルを用いて便を経口摂取する方法があります。
便移植の後は、腸内環境が回復するまで数日から数週間の観察を行い、効果を確認します。ここで重要なのは、便移植後の体調をしっかりと管理することです。
治療の流れ
便移植の治療の流れは、数段階に分かれています。まず、治療に関心を持つ患者は、専門の医療機関を訪れます。医師とのカウンセリングを通じて、患者の症状や既往歴を詳しく確認し、便移植が適切かどうかを判断します。
次に、患者の腸内フローラバランス検査を実施し、その患者の腸内フローラバランス状況を確認した上で、最適な菌液を調合します。
そして、健康なドナーの選定が行われます。ドナーは厳しいスクリーニングを受け、感染症や消化器疾患のリスクがないことが保証されます。受け入れ可能なドナーが確定したら、便の採取と調製の段階に進みます。
その後、移植の実施に移ります。内視鏡やカプセルを用いて便を患者の腸内に移植します。
治療後は、患者の経過を観察し、症状の変化や腸内環境の改善を評価します。
必要に応じて、追加のサポートやフォローアップが行われ、体調の管理をしっかりと行うことが重要です。
ドナーの選び方
ドナーの選び方は、便移植において非常に重要です。
まず、ドナーは健康であることが必須条件です。これには、感染症や消化器系の病歴がないことを確認するための詳細なスクリーニングが含まれます。
特に、肝炎やHIV、腸管感染症などの病歴について慎重に調査する必要があります。
さらに、ドナーの食生活や生活習慣も考慮されます。
腸内フローラの健康に必要な栄養素を豊富に含む食事を心がけている人が望ましいです。
また、喫煙や過度のアルコール摂取がないことも、ドナーとして好ましい条件となります。
こうしたポイントを踏まえることで、安全で効果的な便移植が実施できるでしょう。
便移植の費用
便移植の費用は、施設や地域によって異なるため、具体的な金額を一概に示すことは難しいでしょう。ただし現在のところ便移植は、保険適用外の自費診療であることから、一般的には数十万円から百万円程度の範囲であることが多く、患者の症状により最終的な移植回数も変わってきます。
便移植を検討する際は、自己負担の金額がどれくらいになるかを事前に確認することが重要です。医療機関に相談し、詳細な見積もりを取ることで、より安心して治療に臨むことができるでしょう。
一般的な費用の目安
一般的な費用の目安を考える際、どの便移植方法を選択するかで、費用も変わります。
例えば、一般財団法人腸内フローラ移植臨床研究会が運営するドナーバンク(https://fmt-japan.org/technical-features/japanbiome)を活用する便移植の場合は、便移植にかかる費用は、医療機関での診察料、腸内フローラ検査費用、移植費用で構成されています。ドナーバンク使用料は移植費用に含まれており、医療用ゴムチューブを用いる移植方法にて数十分で終了するため、入院は不要です。抗生物質の投与も食事制限も必要ありません。
一方で、ドナーバンクを使用しないその他の施設・機関での便移植の場合は、医療機関での診察料や検査費用、処置に伴う入院費用が便移植にかかる費用となります。具体的には、便移植に向けた前処置やフォローアップの診察が必要になる場合が多く、全体の費用が増加することがあります。
また、便の提供に関しても、ドナーバンクを使用しない場合は、ドナーを選定し、その健康状態を調べるための検査が必要です。このため、ドナーに関連する費用は別途かかることが一般的です。
このように最終的な費用は、治療を受ける医療機関の方針や地域の医療環境によって異なるため、事前に詳しい見積もりを行うことが望ましいでしょう。
保険適用の可否
便移植における保険適用の可否は、国や地域によって異なります。
日本では、便移植は保険適用外で、現在のところ100%自己負担となっています。
便移植のリスクと注意点
副作用とリスク
便移植には効果が期待できる一方で、副作用やリスクも存在します。
まず、一般的な副作用として、移植後に下痢や腹痛が起こることもあります。
これらの症状は、腸内フローラが急激に変化することに起因しています。
通常は一時的なものであり、体が新しい腸内環境に適応することで改善しますが、耐え難い場合は医療機関で相談することが重要です。
さらに、便移植のリスクとして懸念されるのが、感染症の可能性です。
特に、ドナーから移植された便に病原体が含まれている場合、感染を引き起こす恐れがあります。
そのため、ドナーの選定と厳格なスクリーニングが必要です。
なお、二親等以内のドナーを自分で見つけることが条件となっている便移植の方法以外にも、前述のドナーバンク(日本初の便バンクであるJapanbiome)を活用する方法もあります。
Japanbiomeでは、厳しいドナー管理が徹底されており、倫理委員会も設置されています。
どの便移植を選択するのかは、個別の状態を考慮した上で、医療従事者との十分な相談を通じて決めていくことが重要です。
注意すべき患者の特徴
便移植を検討する際には、特に注意すべき患者の特徴があります。
まず、免疫抑制剤を服用している患者です。これらの薬剤は感染症のリスクを高めるため、便移植の施行には慎重な判断が必要です。
次に、腸の解剖学的異常がある患者も注意が必要です。
これには、過去の手術歴や先天性の腸疾患が含まれます。こうした患者は、治療の効果が得られにくい場合があります。
さらに、精神的な健康状態も考慮に入れるべきです。
心的な問題を抱える患者は、治療に対する理解や忍耐力が不足することがあります。
医療従事者は、これらの特徴を把握しておくことで、適切な治療方針を策定できるでしょう。
最新の研究と今後の展望
最近の研究成果
最近の研究成果では、便移植が潰瘍性大腸炎の症状緩和に寄与するというエビデンスが増加しています。
また、実施された臨床試験では、便移植を受けた患者の約50%に症状改善があったとの報告もあります。この結果は、従来の治療法に反応しなかった難治性の患者にとって朗報となっています。
がん治療に関しても、便移植が免疫療法の効果を高める可能性が注目されています。腸内環境を改善し免疫応答を強化する働きが期待されており、治療法に対しての安全性や有効性を探る研究が進行中です。
その他にも、複数の臨床試験で成功例が報告されており、便移植は標準治療の一環として位置づけられる可能性が高まっています。2024年8月には、食道がん・胃がん患者さんを対象に 便移植の臨床試験が開始されています。
さらに、最近のデータは、便移植後のがん再発率が低下する可能性を示唆しており、長期的な効果も期待されているのです。
しかし、便移植はまだ新しい治療法であるため、安全性や長期的な効果についてのデータが不足しています。将来的には、これらの課題を解決し、より多くの患者に対して安心して提供できる治療法へと発展していくことが期待されています。
まとめ
便移植は、潰瘍性大腸炎をはじめとする消化器疾患に対して、新しい視点からの治療法として注目されています。
腸内環境を改善することで、症状の緩和につながる可能性があります。多くの研究が進行しており、実践例も増えてきました。
しかし、便移植には注意が必要です。ドナーの選定や感染症のリスク管理など、安全性を確保するためのプロセスが不可欠です。医療従事者との連携も重要であり、治療に対する適切な理解を深めることが求められます。
今後、便移植の効果や適応についての研究が進むことで、患者さんの選択肢が広がることが期待されます。腸内フローラをターゲットにした新しい薬剤や治療法の開発も進む中、便移植はその基盤と位置づけを高めていくと考えられます。
潰瘍性大腸炎に悩んでいる方やそのご家族は、ぜひ医療機関での相談を検討してみてください。
引用文献
1. Allegretti, J. R., Mullish, B. H., Kelly, C., & Fischer, M. (2019).
The evolution of the use of faecal microbiota transplantation and emerging therapeutic indications.
The Lancet, 394(10196), 420–431.
2. Bennet, J. D., & Brinkman, M. (1989).
Treatment of ulcerative colitis by implantation of normal colonic flora.
The Lancet, 1(8630), 164.
3. Cammarota, G., Ianiro, G., Tilg, H., Rajilić–Stojanović, M., Kump, P., Satokari, R., … & Gasbarrini, A. (2017).
European consensus conference on faecal microbiota transplantation in clinical practice.
Gut, 66(4), 569–580.
4. Costello, S. P., Hughes, P. A., Waters, O., Bryant, R. V., Vincent, A. D., Blatchford, P., … & Andrews, J. M. (2019).
Effect of fecal microbiota transplantation on 8-week remission in patients with ulcerative colitis: A randomized clinical trial.
JAMA, 321(2), 156–164.
5. Lopetuso, L. R., Ianiro, G., Allegretti, J. R., Bibbò, S., Gasbarrini, A., Scaldaferri, F., & others. (2020).
Fecal transplantation for ulcerative colitis: Current evidence and future applications.
Expert Opinion on Biological Therapy, 20(5), 343–351.
6. Moayyedi, P., Surette, M. G., Kim, P. T., Libertucci, J., Wolfe, M., Onischi, C., … & Marshall, J. K. (2015).
Fecal microbiota transplantation induces remission in patients with active ulcerative colitis in a randomized controlled trial.
Gastroenterology, 149(1), 102–109.e6.
7. Mullish, B. H., Quraishi, M. N., Segal, J. P., McCune, V. L., Baxter, M., Marsden, G. L., … & Williams, H. R. T. (2018).
The use of faecal microbiota transplant as treatment for recurrent or refractory Clostridium difficile infection and other potential indications: Joint British Society of Gastroenterology (BSG) and Healthcare Infection Society (HIS) guidelines.
Gut, 67(11), 1920–1941.
8. Ooijevaar, R. E., Terveer, E. M., Verspaget, H. W., Kuijper, E. J., & Keller, J. J. (2019).
Clinical application and potential of fecal microbiota transplantation.
Annual Review of Medicine, 70, 335–351.
9. Paramsothy, S., Kamm, M. A., Kaakoush, N. O., Walsh, A. J., van den Bogaerde, J., Samuel, D., … & Borody, T. J. (2017).
Multidonor intensive fecal microbiota transplantation for active ulcerative colitis: A randomized placebo-controlled trial.
The Lancet, 389(10075), 1218–1228.
10. Rossen, N. G., MacDonald, J. K., de Vries, E. M., D’Haens, G. R., de Vos, W. M., Zoetendal, E. G., & Ponsioen, C. Y. (2015).
Fecal microbiota transplantation as novel therapy in gastroenterology: A systematic review.
World Journal of Gastroenterology, 21(17), 5359–5371.