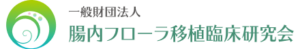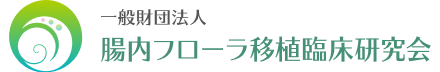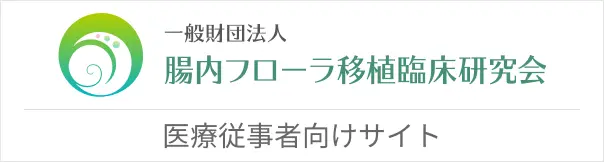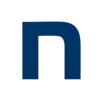赤ちゃんが元気に生まれてくれればなんだっていい。
それはたしかに正論だと思う。
赤ちゃんが危険にさらされるリスクがほんの少しでもあるなら、そしてそのリスクが減らせるなら、帝王切開だって構わない。
帝王切開が最初に行なわれ始めたのは古代ローマ時代。
命がけの出産中に母親が実際に死にかけると、胎児の命だけでも救うために行なわれた措置だった。当然、母親の死亡率はほとんど100%だっただろう。
要は切腹だ。想像するだけで痛すぎる。
麻酔や手術の技術が向上し、帝王切開は胎児だけではなく母親の命も助ける方法になった。
さらには、出産中にトラブルがあった場合には経膣分娩よりも安全な方法として帝王切開が選ばれるようになった。
帝王切開のおかげで、無数の命が助かった。
目次
- 帝王切開の現状
- どうして帝王切開が増えているのか
- 帝王切開とマイクロバイオーム
- 最初の研究
- 最初の研究は正しかったか?
- マイクロバイオーム生態系の立ち上がりが遅くなる
- 帝王切開とマイクロバイオームの両立を目指して
- 膣細菌を赤ちゃんに塗るという方法
- ”vaginal seeding”(膣の種まき)は安全か
・本文中のカッコ付き番号は、記事下部の参考文献の番号を表しています。
・用語解説はこちら(随時更新)
・主要記事マップはこちら(随時更新)
帝王切開の現状
現在日本では、4人に1人の赤ちゃんが帝王切開で生まれてくる。この数字は1990年代の2〜3倍にものぼり、世界の現状とほぼ同じだ。
WHOが推奨する帝王切開率は10〜15%だから、その数字を大きく上回っている。
医療技術や制度の進んでいる先進国たちが、その数字を押し上げているのだろうか?
実はそうでもなく、むしろ発展途上国や新興国で帝王切開率が増えているという現状がある。
エジプトでは、なんと70%以上もの妊婦が望むと望まざるとにかかわらず帝王切開を受けている。(参考:出産の72%が帝王切開 エジプト 医学的に必要ないのに広がる事情:朝日新聞デジタル)
他にもドミニカ共和国、ブラジル、キプロス、トルコなどで50%以上の高い帝王切開率になっている。
日本や世界平均の「20%」という数字がかすんで見えるほどだ。
この状況が続けば、最悪の場合は2030年までに東アジア63%、ラテンアメリカやカリブ海地域で54%、西アジアで50%、北アフリカで48%、南ヨーロッパで47%、オーストラリアやニュージーランドで45%まで数字が上がる可能性があるとWHOは予測している。
Caesarean section rates continue to rise, amid growing inequalities in access
逆に、北欧やオランダでは10%台である。このように国によって差があるということは、医学上の緊急性や必要性とは別のところで帝王切開が選ばれているということが推測できる。
どうして帝王切開が増えているのか
帝王切開には、予定帝王切開と緊急帝王切開がある。
母体や胎児が危険な状態にある場合、お産はしばしば緊急帝王切開に切り替えられる。
母親の年齢や既往症などを考慮して、もしもの場合に帝王切開をすぐに受けられるように大きな病院を産院として選ぶ人も多い。
予定帝王切開も、同様にリスクが高いと判断された妊婦に提案される。
前回のお産が帝王切開だった場合は、そのあとの出産は帝王切開しか選べない病院も多い。前の傷が開いて大量出血するなどのリスクがあると考える医師がいまだに多いからだ。
しかし、現場の医療スタッフの常識がそうだとしても、最新の研究では帝王切開のあとの経膣分娩でそれほどリスクが上がるわけではないということが明らかになっている。
(参考:Vaginal Birth After Cesarean: VBAC: – American Pregnancy Association)
ほかにも逆子や双子、巨大児の場合にも予定帝王切開が選ばれやすい。
医師が予定帝王切開を勧める背景には、実は裏の理由も存在する。
訴訟リスクを回避したい、出産にかかる時間を節約したい、高い手術費用を取れるといったものだ。
リスクが高いからという表向きの理由はあっても、実はすべてのケースで本当に帝王切開が医学的に必要であるというわけではない。
帝王切開を自ら望む母親もいる。
陣痛があまりにも長く耐え難い痛みであるとき、「切ってください」と涙ながらに訴える母親の言葉は、医師の背中を押すだろう。
産休制度が整っていない国や、産休を使えない仕事をしている場合、仕事のスケジュールに合わせて出産したいと望む女性がいてもおかしくない。
そして、予定帝王切開ならば、ずっと担当してくれていた主治医に最後まで見てもらえるというメリットもある。
必要以上に帝王切開が選ばれている現実で、誰かを責めることはおそらくナンセンスだ。
医学的な理由だけではなく、人間社会はさまざまな要素が複雑に絡んでいるのだから。
それでも、帝王切開にはリスクがある。わずかながらメスが赤ちゃんを傷つけたり、呼吸系の障害が残ることもある。
術後の母親の回復には時間がかかる。もちろん、経膣分娩ならリスクがゼロというわけではない。
主治医や妊婦は、それらのリスクを天秤にかける。
近年、帝王切開による長期的なリスクにあるもうひとつの点を加えるべきだという声が上がっている。
腸内細菌たちを中心としたマイクロバイオームの形成だ。
帝王切開とマイクロバイオーム
帝王切開で生まれた赤ちゃんたちは、経膣分娩で生まれた赤ちゃんたちに比べてマイクロバイオームの形成過程に違いがあるのかもしれない。
妊娠中に膣や腸のマイクロバイオームが赤ちゃん向けに変わるのなら、膣を通るプロセスをスキップすることで赤ちゃんが獲得するマイクロバイオームに違いが出るというのは自然な仮説だ。
最初の研究
それを最初に検証したのが、Maria Gloria Dominguez-Bello氏(当時プエルトリコ大学、現ラトガース大学)らの研究チームだ。
2010年に発表された「分娩方法が新生児のさまざまな体の部位において最初のマイクロバイオータの獲得と構成を左右する」と題されたこの研究論文(1)は、生まれたての赤ん坊のマイクロバイオーム(特に腸内細菌)形成における帝王切開の影響を網羅的に検証した最初の研究として位置づけられている。
この研究は、あるハプニングの結果行なわれたものだった。
Dominguez-Bello氏は祖国でもあるベネズエラで20年にわたり、栄養学や微生物学の研究を行っていた。
その時もベネズエラに赴き、ジャングルの奥地で先住民たちの微生物を採取する予定だったのだが、ヘリコプターがキャンセルされてしまった。
ベネズエラの首都で三週間足止めされてしまった彼女は、バカンスを取るよりも「別の研究」に着手することを選んだ。
地元の病院に行って、経膣分娩と帝王切開による分娩で生まれた赤ちゃんたちの細菌にどんな違いがあるか調べることにしたのだ。
この研究には、21歳から33歳まで9人の母親と10人の赤ちゃんが参加し、母親の皮膚、口、膣の細菌や、新生児の皮膚、口、鼻、便(胎便)の細菌が調べられた。
その結果、帝王切開で生まれた赤ちゃんと経膣分娩で生まれた赤ちゃんたちで、それぞれ細菌の構成が大きく異なっていることが示された。
経膣分娩で生まれた赤ちゃんたちは、からだじゅうが母親の膣常在菌で覆われていたのだ。
最初の研究は正しかったか?
この結果は、これに続くさまざまな別の研究者たちによる研究ですべて支持されたわけではない。
生後すぐの赤ちゃんから1歳未満の赤ちゃんまでを対象に、帝王切開による分娩と経膣分娩の差がマイクロバイオームにどのような影響を与えるのか、世界中の研究者が検証を試みた(2)。
その結果は、研究ごとにまちまちだった。
この検証をむずかしくしているいくつかの要因がある。
まず、生まれてから数日、あるいは数ヶ月の赤ちゃんは、マイクロバイオーム(検証対象は細菌)がめまぐるしく変わる。
生まれてから24時間以内に出る「胎便(たいべん)」の腸内細菌の構成は、翌日にはがらりと変わっている。ちなみに胎便は最近まで無菌だと考えられていたが、ある研究では3人に2人の割合で、わずかに検出可能なレベルで細菌が含まれることがわかっている(3)。
第二に、腸内細菌の構成は個人差が大きい。母親が違えば、受け取る細菌も違うのだ。
そして第三に、特に胎便は細菌の数そのものが少ない。解析対象の菌数が少ないと、解析過程でのコンタミネーションなどの影響が大きくなり、結果の信頼性が下がる。
マイクロバイオーム生態系の立ち上がりが遅くなる
それでも、帝王切開で生まれた赤ちゃんは明らかにマイクロバイオームの立ち上がりが遅いことを多くの研究は示唆している。
生態学的な言い方をすれば、生態系が安定するまでに時間がかかる。
特に0歳児に特徴的なビフィズス菌(Bifidobacterium)の増殖が何ヶ月も遅れてしまう。
母乳にはビフィズス菌とその栄養源であるオリゴ糖が含まれているにもかかわらず、帝王切開で生まれた赤ちゃんは母乳を飲んでいてもビフィズス菌がなかなか増えてこない。
これは、生まれる瞬間に母親の便に含まれるビフィズス菌を摂取できないことで、赤ちゃんの未熟な腸マイクロバイオームの生態系の中で別の菌たちが先に増殖を始めてしまい、あとから来たビフィズス菌が増えづらくなってしまっている可能性が考えられる。
両者の違いは、離乳食が始まる生後6ヶ月頃になるとだんだんと消えていくことがわかっている。
そうであっても、未熟な状態で生まれてくるヒトにとって、生後半年ものあいだ一緒にからだづくりをしてくれるメンバーの顔ぶれが違うことは、重要な意味を持つだろう。
では本当に、帝王切開で生まれたことによるマイクロバイオームの「顔ぶれの変更」は、その後の人生に不利益をもたらすのか?
おそらく、かなり確定的に答えはイエスだ。
帝王切開で生まれた赤ちゃんは、生後一年以内に感染症にかかりやすくなる。
病気のリスクは感染症にとどまらない。
小児喘息(4-6)、アトピー(7-9)、アレルギー(8,10)、Ⅰ型糖尿病(11)、炎症性腸疾患(IBD)(5,12)などの免疫応答に関する疾患リスクや、肥満(13)の増加も報告されている。
さらには、学童期において認知能力の発達にも影響をおよぼす(14)ことが示され始めている。
帝王切開とマイクロバイオームの両立を目指して
世界的な帝王切開の割合はうなぎのぼりだと言っていいだろう。
経済的に国全体に大きな負担がかかるうえ、母親の肉体的・精神的負担も大きい帝王切開は、本当に医学的に必要な場合に限るほうがいい。
マイクロバイオームの自然な形成が乱されることと深く関連しているらしいことを踏まえると、余計にその思いは強くなる。
けれど、女性の気持ちを置き去りにしたまま自然分娩信仰を祭り上げるわけにもいかない。
妊娠や出産の過程では、人には言えない心の傷を静かに抱えている女性も多い。
「下から産んであげたかった」
「帝王切開になってしまった」
無事に赤ちゃんが生まれたとしても、何十年もそんな思いを引きずる人もいる。
そんな状況で、赤ちゃんのマイクロバイオーム形成、ならびに将来の健康状態にも悪影響があるかもしれないという知らせは、そんな母親たちを余計に悲しませるだけかもしれない。
でも、科学は常に改善を試みている。ベストではなくとも、ベターな方法を安全に提案するのも、科学の役目だ。
帝王切開で生まれた赤ちゃんに正常なマイクロバイオームを形成してもらおうと、画期的な試みを始めた研究チームがある。
膣細菌を赤ちゃんに塗るという方法
カリフォルニア大学教授(当時コロラド大学教授)のRob Knight氏の娘は、2011年に緊急帝王切開で誕生した。
Knight氏は世界的に著名な微生物学者で、2007年に発足したHuman Microbiome Projectにも主要メンバーとして関わっている。
彼が帝王切開によるマイクロバイオームへの影響を知らなかったはずはない。
実は、Knight氏はその前年に出されたDominguez-Bello氏の論文(前述のベネズエラでの研究)の共同著者としても名を連ねている。
そして彼は、研究者というよりもひとりの父親として行動した。
手術のあと、妻と娘と三人きりになった病室で、彼は妻の膣を綿棒でぬぐって娘の体に塗りつけた。
開腹手術である帝王切開は、当然ながら母親に感染症のリスクがある。
執刀医をはじめとしたスタッフは、自身や器具、部屋の消毒や殺菌を念入りに行なっただろう。生まれてくる赤ちゃんも清潔に取り出されたはずだ。
彼の行為を病院スタッフが知っていたら、決していい顔はしなかっただろう。
けれど父親として娘が将来受けうる不利益をできるだけ避けようとした彼の行動を責めることは、誰にもできないのかもしれない。
この、おそらく世界ではじめての「膣マイクロバイオーム移植」は、どの研究にも含まれていない。研究計画なしの行為だ。
2016年、Dominguez-Bello氏やKnight氏を含む研究チームは、この「膣マイクロバイオーム移植」を帝王切開で生まれた4名の新生児に実施したという論文(15)を出した。
その結果、新生児の体の一部で母親の膣由来のマイクロバイオームが定着し、経膣分娩で生まれた赤ちゃんと同じような構成になったという。
彼らはこの方法を”vaginal seeding”(膣の種まき)と呼び、現在に至るまで着実に研究データ(16,17)を積み重ね続けている。
「この方法はこのようなリスクがある」という事実を明らかにするのも科学の大切な仕事のひとつだが、それが避けられないケースがある場合に「どうすればリスクを少しでも減らせるか」という方法を模索する姿は、研究者としてとても尊敬できる姿勢だ。
彼らは帝王切開の他にも、粉ミルク育児や分娩時の抗生物質の影響をできるだけ避けたり、受けた影響を少なくするための方法を模索している(18)。
”vaginal seeding”(膣の種まき)は安全か
一方で、”vaginal seeding”はまだ効果や安全性、機序がわからない面も多く、実施は慎重になるべきだという声もある。
アメリカ産婦人科学会(American College of Obstetricians and Gynecologists, ACOG)は、”vaginal seeding”はあくまで研究計画に含まれるケースでのみ実施されるべきで、一般的な医療の場や自己判断で行うべきではないとコメントを出している。
(参考:Vaginal Seeding | ACOG)
西オーストラリア大学の研究者らは、2018年に発表した論文(2)内でかなり批判的な立場を取っている。
彼らは帝王切開による分娩と経膣分娩の研究をいくつか取り上げたうえで、両者のマイクロバイオーム形成に本当に差があるのかをまず問題としている。さらに帝王切開そのものではなく、その他の因子に本当の原因がある可能性も考えるべきだと主張する。
帝王切開を余儀なくされた要因(母親側の年齢や疾患、肥満などのリスク因子)、帝王切開の際に服用する抗生物質、陣痛がないこと、母乳の影響、個人間・個人内のマイクロバイオームの多様性などがその因子として考えられるだろう。
別の研究チーム(19)は、これらの因子のうち抗生物質の影響を排除しても両者のマイクロバイオーム形成に明らかな違いがあることを示している。彼らは母乳、きょうだいやペットの有無、産後の入院日数の長さ、おしゃぶりに至るまでさまざまな因子を検討し、
さらには”vaginal seeding”に加え、”fecal seeding”(うんちの種まき)の可能性にすら言及している。
帝王切開はただの「相関」なのかそれとも「原因」なのか。
それを確かめるためには還元主義的な方法を試していくしかないが、無数にある交絡因子をすべて考慮した研究は、相当難しいだろう。
それよりは、完璧なリレーを見せてくれる自然な経膣分娩や母乳育児をなるべく後押しし、それが叶わない場合でも悲観せずにベターな方法を探っていく姿勢を、筆者としては応援したい。
1. Dominguez-Bello MG, Costello EK, Contreras M, et al. Delivery mode shapes the acquisition and structure of the initial microbiota across multiple body habitats in newborns. Proc Natl Acad Sci U S A. 2010;107(26):11971-11975. doi:10.1073/pnas.1002601107
2. Stinson LF, Payne MS, Keelan JA. A Critical Review of the Bacterial Baptism Hypothesis and the Impact of Cesarean Delivery on the Infant Microbiome. Front Med. 2018;5. Accessed October 31, 2023. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmed.2018.00135
3. Hansen R, Scott KP, Khan S, et al. First-Pass Meconium Samples from Healthy Term Vaginally-Delivered Neonates: An Analysis of the Microbiota. PLoS ONE. 2015;10(7):e0133320. doi:10.1371/journal.pone.0133320
4. Debley JS, Smith JM, Redding GJ, Critchlow CW. Childhood asthma hospitalization risk after cesarean delivery in former term and premature infants. Ann Allergy Asthma Immunol. 2005;94(2):228-233. doi:10.1016/S1081-1206(10)61300-2
5. Sevelsted A, Stokholm J, Bønnelykke K, Bisgaard H. Cesarean Section and Chronic Immune Disorders. Pediatrics. 2015;135(1):e92-e98. doi:10.1542/peds.2014-0596
6. Thavagnanam S, Fleming J, Bromley A, Shields MD, Cardwell CR. A meta-analysis of the association between Caesarean section and childhood asthma. Clin Exp Allergy. 2008;38(4):629-633. doi:10.1111/j.1365-2222.2007.02780.x
7. Negele K, Heinrich J, Borte M, et al. Mode of delivery and development of atopic disease during the first 2 years of life. Pediatr Allergy Immunol. 2004;15(1):48-54. doi:10.1046/j.0905-6157.2003.00101.x
8. Bager P, Wohlfahrt J, Westergaard T. Caesarean delivery and risk of atopy and allergic disesase: meta-analyses. Clin Exp Allergy. 2008;38(4):634-642. doi:10.1111/j.1365-2222.2008.02939.x
9. Laubereau B, Filipiak-Pittroff B, Berg A von, et al. Caesarean section and gastrointestinal symptoms, atopic dermatitis, and sensitisation during the first year of life. Arch Dis Child. 2004;89(11):993-997. doi:10.1136/adc.2003.043265
10. Eggesbø M, Botten G, Stigum H, Nafstad P, Magnus P. Is delivery by cesarean section a risk factor for food allergy? J Allergy Clin Immunol. 2003;112(2):420-426. doi:10.1067/mai.2003.1610
11. Cardwell CR, Stene LC, Joner G, et al. Caesarean section is associated with an increased risk of childhood-onset type 1 diabetes mellitus: a meta-analysis of observational studies. Diabetologia. 2008;51(5):726-735. doi:10.1007/s00125-008-0941-z
12. Li Y, Tian Y, Zhu W, et al. Cesarean delivery and risk of inflammatory bowel disease: a systematic review and meta-analysis. Scand J Gastroenterol. 2014;49(7):834-844. doi:10.3109/00365521.2014.910834
13. Darmasseelane K, Hyde MJ, Santhakumaran S, Gale C, Modi N. Mode of Delivery and Offspring Body Mass Index, Overweight and Obesity in Adult Life: A Systematic Review and Meta-Analysis. PLOS ONE. 2014;9(2):e87896. doi:10.1371/journal.pone.0087896
14. Polidano C, Zhu A, Bornstein JC. The relation between cesarean birth and child cognitive development. Sci Rep. 2017;7(1):11483. doi:10.1038/s41598-017-10831-y
15. Dominguez-Bello MG, De Jesus-Laboy KM, Shen N, et al. Partial restoration of the microbiota of cesarean-born infants via vaginal microbial transfer. Nat Med. 2016;22(3):250-253. doi:10.1038/nm.4039
16. Song SJ, Wang J, Martino C, et al. Naturalization of the microbiota developmental trajectory of Cesarean-born neonates after vaginal seeding. Med N Y N. 2021;2(8):951-964.e5. doi:10.1016/j.medj.2021.05.003
17. Mueller NT, Differding MK, Sun H, et al. Maternal Bacterial Engraftment in Multiple Body Sites of Cesarean Section Born Neonates after Vaginal Seeding—a Randomized Controlled Trial. mBio. 2023;14(3). doi:10.1128/mbio.00491-23
18. Mueller NT, Bakacs E, Combellick J, Grigoryan Z, Dominguez-Bello MG. The infant microbiome development: mom matters. Trends Mol Med. 2015;21(2):109-117. doi:10.1016/j.molmed.2014.12.002
19. Reyman M, van Houten MA, van Baarle D, et al. Impact of delivery mode-associated gut microbiota dynamics on health in the first year of life. Nat Commun. 2019;10:4997. doi:10.1038/s41467-019-13014-7
本ブログ記事は、
シンバイオシス株式会社微生物事業部の研究員が
noteにて作成した記事を転記しております。
記事タイトル:帝王切開と自然分娩をマイクロバイオームの視点で考える
記事リンク:https://note.com/symbiosis17/n/nd662182b4ed4?sub_rt=share_pw
「腸内細菌叢」は「ちょうないさいきんそう」と読みます。腸内細菌叢は人間の腸内に存在する微生物の集合体であり、健康維持に非常に重要な役割を果たしています。
近年の研究によって、腸内細菌のバランスが整っていることが、免疫機能や代謝、さらにはメンタルヘルスにまで影響を与えることが明らかになってきました。腸内環境が良好であると、病気のリスクも低下します。
腸内細菌叢の読み方
腸内細菌叢の読み方は「ちょうないさいきんそう」です。「叢(そう)」は「群れ」や「集まり」を意味し、「細菌叢」は「細菌の集団」という学術的な表現になります。
腸内細菌は、消化吸収を助けるだけでなく、免疫系の調整、栄養素の合成、さらにはホルモンの分泌にも関与しています。そのため、腸内細菌叢のバランスが崩れると、さまざまな健康問題を引き起こす原因となります。
通常、腸内細菌叢は善玉菌、悪玉菌、日和見菌の三種類に分類されます。
善玉菌は健康に有益な物質を産生したり、人の細胞の恒常性を維持するような働きがあるビフィズス菌や酪酸菌などを指します。悪玉菌は過剰に増えてしまった場合、有害な影響を及ぼすことがありますが、近年これらも健康において重要な役割を果たす可能性が示されています。日和見菌は腸内の状況によって良い役割になったり、悪い役割をするため、全体のバランスが重要です。(1)
重要なのは、善玉菌が優位でかつ、腸内細菌の種類が多く、全体のバランスが整っていることにあります。
腸内細菌叢の正しい理解は、健康促進に大きく貢献します。
注目される理由
腸内細菌叢が注目される理由は、健康への影響が多岐にわたるためです。
例えば、善玉菌が優勢な腸内環境は、感染症の予防に効果的です。良い代謝物を分泌する、適切でバランスの良い腸内細菌叢により、神経伝達物質などの有益な成分が生成することが知られ、それによりメンタルヘルスにも影響を与えるとされています。このように、腸内細菌叢は単なる消化の役割を超えて、身体全体の健康に深くかかわっているのです。
さらに、これまで医療は病気を治すことに焦点を当ててきましたが、腸内細菌の研究は予防医療の重要性を再認識させています。腸内環境を整えることで、日々の健康を維持し、長寿を促進するための新しいアプローチが期待されています。
腸内細菌叢とは
腸内細菌叢とは、人間の腸内に生息する多様な微生物の集合体を指します。これには、細菌、ウイルス、真菌、原生動物などが含まれており、特に細菌が主な構成要素です。私たちの腸内には数百種類、トータルで約100兆個もの微生物が存在するとされ、それぞれが特有の役割を果たしています。(2)
腸内細菌の定義と構造
腸内細菌の定義は、人間の腸内に生息する微生物のうち、特に細菌群を指します。腸内には数百種類の異なる細菌が存在し、その多様性は健康状態に大きな影響を与えます。腸内細菌は、小腸(回腸)に1,000万個/1g存在し、食物の分解や栄養素の吸収を助けています。大腸には約1兆個/1g生息し、小腸で消化し切れなかった食物繊維などを発酵する役割があります。
腸内細菌は、小腸から大腸まで、それぞれの細菌の棲みやすい場所に多く分布します。小腸には比較的空気が存在するので、空気があっても生育できる細菌(通性嫌気性菌)の乳酸桿菌が多く住んでいます。大腸になると、無酸素状態になり、無酸素でも生きられる細菌(偏性嫌気性菌)が爆発的に多くなります。偏性嫌気性菌の代表にビフィズス菌、バクテロイデス菌があります。大腸にも一部、通性嫌気性菌である乳酸桿菌や大腸菌も棲んでおり、腸内腐敗をおこしたりする有害菌も存在します。重要なのは、有用菌、有害菌および中間的な菌のバランスを整えることです。
腸内細菌のバランスが保たれていることが、消化器系の健康だけでなく、全身の健康にも寄与することが分かっています。このように、腸内細菌の定義と構造を理解することは、私たちの健康を考える上で非常に重要です。
腸内フローラと腸内細菌叢
腸内フローラとは、腸内に存在する微生物の集合体を指す言葉で、特に細菌の群れを強調した表現です。フローラ(flora)という言葉は、植物の群生を意味する英語であり、ラテン語の花を指す単語である「flos」にも由来されると言われています。この場合は腸内の微生物群を示しています。
「腸内フローラ」と「腸内細菌叢」は、どちらも腸内に存在する細菌の集まりを指しますが、厳密には学術的な表現の違いや言葉の背景に違いがあります。
腸内フローラは一般向けの説明や、健康・栄養関連の話題でよく使われます。例えば「腸内フローラを整える」「腸活」などです。以前は学術的にも使われていましたが、現在はやや古い表現とされています。
一方で腸内細菌叢は、医学・生物学の論文や専門書で使われます。近年の腸内細菌研究では、「腸内細菌叢(gut microbiota)」が正式な用語として定着しつつあり、「フローラ」と違い「細菌」という具体的な対象を明示しています。
腸内細菌叢はより正確な学術用語として「腸内フローラ」の代わりに使われることが増えています。
腸内細菌叢の機能と働き
腸内細菌の機能
腸内細菌叢は、私たちの健康に大きく寄与する多くの機能を持っています。
まず第一に、腸内細菌は食物を発酵させることで、栄養素を生成し、これを体に吸収可能な形に変換します。このプロセスにより、ビタミン群やビタミンK、酢酸などの短鎖脂肪酸などの重要な栄養素が生成されます。
さらに、腸内細菌は免疫システムの調整にも関与しています。腸は、体内の免疫細胞の約70%が存在する場所であり、腸内細菌がバランス良く存在することで、免疫機能が正常に働くことが可能です。
大腸等で産生された腸内細菌の代謝物である短鎖脂肪酸は、大腸の免疫細胞に作用し大腸内でのIgA産生を増強します。大腸から吸収されて血中に移行した短鎖脂肪酸は小腸パイエル板の免疫細胞にも作用し、小腸でのIgA産生も増強します。この様に腸内細菌によって誘導され分泌されたIgAは感染防御に役立ち、粘膜面における感染防御のバリア機能として大いに貢献しています。(3)
また、腸内細菌叢が整っていると、良い代謝物が分泌され、腸のバリア機能が強化され、外部からの病原菌に対する抵抗力を持つことが知られています。腸内環境が整っていると、腸内の炎症が抑えられ、さまざまな病気のリスクを低下させることができます。
このように、腸内細菌叢は私たちの健康を支える重要な役割を果たしているため、そのバランスを保つことが非常に大切です。
腸内細菌の働き
腸内細菌の働きも多岐にわたります。
まず、腸内細菌は食べ物の消化を助けることで、栄養素の吸収を促進します。特に食物繊維を分解し、ヒトのエネルギー源だけでなく、様々な生理活性作用を持つ短鎖脂肪酸を生成します。これにより、腸の健康を保つだけでなく、全身のエネルギーバランスにも寄与します。
次に、腸内細菌は免疫機能の調整にも重要な役割を果たしています。腸内に存在する善玉菌は、病原菌の侵入を防ぎ、体の免疫応答を強化します。腸内環境が整っていることにより、感染症などのリスクを低下させることができます。
さらに、腸内細菌の代謝物はホルモンの合成にも関与しています。特に、満腹感を感じさせるホルモンであるGLP-1や、ストレスに関連する体内のホルモンに影響を与えることが知られています。(4)このように腸内細菌は、消化、免疫、ホルモンなど多様な働きを通じて私たちの健康を支えています。
腸内細菌叢と健康
健康維持への影響
腸内細菌叢は、健康維持にさまざまな影響を与えています。
一つ目は、免疫機能の強化、二つ目は消化・吸収機能の向上、三つ目がストレス減少や気分の改善などメンタルヘルスの安定化に影響を与えています。
日常生活での腸内フローラのケア
腸内フローラを日常生活でケアするためには、いくつかのポイントを意識することが重要です。
まず、食生活の見直しが欠かせません。繊維質が豊富な野菜や果物、そして発酵食品を積極的に取り入れることで、腸内細菌のバランスを保つことができます。特にヨーグルトや納豆は良質なプロバイオティクスを含んでいるため、おすすめです。(5)
次に、水分をしっかり摂ることも大切です。水分が不足すると腸の動きが悪くなり、便秘を引き起こすことがあります。毎日十分な水分を摂取し、腸内環境を整えましょう。
さらに、ストレス管理も忘れてはいけません。
ストレスは腸内細菌叢に悪影響を与えることが知られていますので、趣味やリラクゼーションを通じて心身のリフレッシュを図ることが大切です。
これらの生活習慣を取り入れることで、腸内細菌叢のケアが実現し、健康的な生活を送る基盤を築くことができるでしょう。
腸内細菌叢の移植
腸内細菌叢「ちょうないさいきんそう」の注目と共に、近年では、腸内細菌叢移植「ちょうないさいきんそういしょく」にも注目が集まっています。
腸内細菌叢移植は、便移植とも糞便微生物叢移植とも呼ばれています。
腸内細菌叢移植、便移植、糞便移植の読み方と違い
腸内細菌叢移植は「ちょうないさいきんそういしょく」と読みます。
便移植は「べんいしょく」、糞便微生物叢移植は「ふんべんびせいぶつそういしょく」と読み、基本的に同じ医療・研究手法を指しますが、それぞれの呼び名には若干のニュアンスの違いがあります。
便移植 べんいしょく(Fecal Transplant)
便移植は、一般的な用語で、医学的な文脈でも広く使われています。便全体(糞便)をドナーから採取し、ろ過・調整した上で患者に移植する手法を指します。口語的にもよく使われますが、学術的にはやや曖昧な表現です。(6)
糞便微生物叢移植 ふんべんびせいぶつそういしょく(Fecal Microbiota Transplantation, FMT)
「糞便」は「便」よりも学術的・正式な表現で、医療論文などでは「糞便微生物叢移植」と表記されることが多いでしょう。便に含まれる微生物をそのまま、または一部処理したものを移植することを明確に示しています。医学界では「糞便微生物叢移植(FMT)」が正式名称として最もよく使用されています。
腸内フローラ移植 ちょうないふろーらいしょく(Fecal Microbiota Transplantation, FMT)
「糞便微生物叢移植(FMT)」とほぼ同義ですが、よりカジュアルな表現です。「腸内フローラ」という言葉は、かつて腸内細菌の集合体を指す一般的な用語でしたが、現在では「腸内細菌叢」がより正確な用語として使われています。
腸内細菌叢移植 ちょうないさいきんそういしょく(Microbiota Transplantation)
より学術的な表現で、移植の対象が「腸内細菌叢(microbiota)」であることを明示しています。「糞便(便)」ではなく、「腸内細菌叢の移植」とすることで、便そのものではなく腸内細菌の移植が主目的であることを強調しています。
「便移植」は日常的な表現として一般的に多く使用されていますが、「糞便微生物叢移植(FMT)」が最も標準的な学術用語です。「腸内細菌叢移植」はより高度な微生物学的視点を持つ用語として、合成微生物叢移植(糞便そのものではなく特定の細菌のみを抽出して移植する方法)などの新しい技術に適用され始めています。
シンバイオシス株式会社では、抗菌薬を使わない、患者さんへの負担の少ない新しい「腸内細菌叢移植」を既に690件以上実施しています。ご自身の腸内細菌叢の状態や、腸内細菌叢移植にご関心のある方はぜひお近くのクリニックにお問い合わせ下さい。
「腸内細菌叢移植」:https://fmt.sym-biosis.co.jp/transplantation
お近くのクリニック:https://fmt.sym-biosis.co.jp/transplantation/partner
まとめ
腸内細菌叢(ちょうないさいきんそう)は、腸内にいる無数の微生物の集合であり、そのバランスは健康に大きな影響を及ぼします。
腸内細菌叢のバランスが崩れた際には、「糞便微生物叢移植(FMT)」などの治療法が有効とされており、腸内環境の改善が期待できます。
腸内細菌叢についての理解を深め、その重要性を認識することで、将来に渡ってより健康的なライフスタイルを実現できます。普段の食事や生活習慣を見直し、自分自身の健康を守るために、腸内環境を大切にしていきましょう。
引用文献
1.Lynch, S. V., & Pedersen, O. (2016). The Human Intestinal Microbiome in Health and Disease. New England Journal of Medicine, 375(24), 2369-2379.
2.Sender, R., Fuchs, S., & Milo, R. (2016). Revised Estimates for the Number of Human and Bacteria Cells in the Body. PLoS Biology, 14(8), e1002533.
3.Rooks, M. G., & Garrett, W. S. (2016). Gut microbiota, metabolites and host immunity. Nature Reviews Immunology, 16(6), 341-352.
4.Cryan, J. F., et al. (2019). The Microbiota-Gut-Brain Axis. Physiological Reviews, 99(4), 1877-2013.
5.Hill, C., et al. (2014). Expert consensus document: The International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics consensus statement on the scope and appropriate use of the term probiotic. Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology, 11(8), 506-514.
6.Cammarota, G., et al. (2017). European consensus conference on faecal microbiota transplantation in clinical practice. Gut, 66(4), 569-580.
監修者:農学博士 嶋秀明(シンバイオシス株式会社)
便移植は、潰瘍性大腸炎などの消化器疾患をはじめとした多様な疾患に対する新たな治療法として注目されています。
腸内フローラ*のバランスを整えることで、症状の改善が期待されます。
(*腸内細菌の集まり、またそれを含む微生物群)
研究によると、便移植は難治性の潰瘍性大腸炎の患者において、症状の緩和や回復を促進することが示されています。また、便移植は従来の治療法と併用することも可能で、より良い結果を得ることができると言われています。
便移植とは
便移植とは、健康なドナーから採取した便から不純物を取り除き、患者の腸内に移植する治療法です。
この方法は、主に腸内フローラのバランスを回復させる目的で行われます。
腸内フローラが乱れると、消化器疾患の症状が悪化することがありますが、便移植によってドナーの健康な腸内細菌叢の生態系をまるごと移す(移植する)ことで、健康を取り戻せると期待されています。
海外では、2000年代に欧米でC. difficile腸炎(CDI)が深刻な社会問題となり、FMTが有効であると注目されはじめました。
また、便移植は、特に潰瘍性大腸炎やクローン病などの難治性疾患を持つ患者に対して有効であると言われています。臨床研究によると、便移植を受けた患者の多くが症状の改善を体験しており、一部の患者では寛解が見られることもあります。
ただし、便移植は医療現場での厳密な管理の下で行われる必要があります。
ドナーの選定や採取された便の検査が不可欠であり、安全性を確保することが重要です。
便移植の効果
便移植は、腸内の微生物バランスを正常化することを目的とした治療法です。
特に、潰瘍性大腸炎やクローン病の患者において、症状の改善が期待されています。
腸内フローラの乱れは、これらの疾患の発症や悪化に関与していると考えられています。
実際に便移植を受けた患者の多くが、腹痛や下痢、便秘といった症状の緩和を実感しています。また、腸内の炎症が低下し、病状が安定するケースも見られています。
これは、移植された便中の有用な微生物が患者の腸内で増殖し、炎症を抑える働きをするためです。
ただし、便移植の効果は個人差が大きく、必ずしも全ての患者に効果があるわけではありません。治療方法としての選択は、医療従事者との十分な相談、診断等を経て行うことが重要です。
腸内細菌叢の調整
腸内細菌叢は、私たちの健康に大きな影響を与える重要な要素です。
特に、潰瘍性大腸炎やクローン病といった消化器疾患では、腸内の微生物バランスが崩れることが炎症を引き起す一因となり、様々な症状が現れます。
便移植は、腸内細菌叢を調整する手段として注目されています。
健康なドナーの便を移植することで、腸内の有用な微生物を補充し、バランスを回復させることが狙いです。この治療法により腸内環境が整うことで、炎症が抑制され、症状の改善が期待できます。
しかし、腸内細菌叢の調整は個人差が大きいため、全ての患者に劇的な効果が現れるわけではありません。
腸内環境の改善には時間がかかることも多く、医療従事者との連携が不可欠です。
患者ひとりひとりの状態に応じた治療法を選択することが、より良い結果を引き出す鍵となります。
潰瘍性大腸炎への効果
潰瘍性大腸炎に対する便移植の効果は、多くの研究で示されています。
主な効果としては、腸内フローラの多様性を回復させることが挙げられます。
潰瘍性大腸炎は、有益な細菌の減少や腸内の一部の細菌の偏った増加、腸内細菌の多様性低下が関与しているため、健康なドナーを通じて新たな細菌(より広くは微生物全体)を導入することが症状の改善に繋がります。
具体的には、便移植を受けた患者の中には、腹痛や下痢の頻度が大きく減少したり、慢性的な便秘から解放されたケースも多く見られます。
また、医療機関でのデータに基づくと、一部の患者では炎症マーカーが低下し、炎症のコントロールが良好に行われたという結果もあります。
ただし、便移植の効果は、患者各々の腸内環境や治療歴によって異なることがあります。そのため、医師と相談しながら自分に合った治療法を選ぶことが重要です。
他の疾患への応用
便移植は潰瘍性大腸炎の治療にとどまらず、他の疾患への応用も広がっています。
最近の研究では、腸内フローラとさまざまな病気の関連性が明らかになりつつあります。
例えば、下痢型過敏性腸症候群や抗生物質関連下痢などの疾患にも便移植が試みられています。これらの疾患では腸内のバランスの崩れが影響を与えているため、便移植によって有用な微生物を導入し、症状の改善が期待されます。
さらに、肥満や糖尿病などの代謝性疾患にも腸内環境の影響が指摘されています。便移植を通じて腸内フローラを改善することで、体重管理や代謝の改善に寄与する可能性があるのです。
ただし、これらの他の疾患への応用についてはまだ研究段階にあり、エビデンスが確立されていないため、慎重な判断が求められます。医療従事者とよく相談し理解を深めて進めることが大切です。
便移植の方法
便移植の方法は、まず健康なドナーを選定することから始まります。
ドナーは、感染症や消化器系の疾患がないことを確認するため、十分なスクリーニングが行われます。これにより、安全な便が確保されます。
次に、ドナーから採取した便を調製します。通常、便は生理食塩水等の溶媒を加え、不純物を取り除くことで滑らかな状態にされます。この準備を経て、患者に移植するための手続きが行われます。
便移植の方法には、内視鏡を使用して腸内に直接便を注入する方法や、カプセルを用いて便を経口摂取する方法があります。
便移植の後は、腸内環境が回復するまで数日から数週間の観察を行い、効果を確認します。ここで重要なのは、便移植後の体調をしっかりと管理することです。
治療の流れ
便移植の治療の流れは、数段階に分かれています。まず、治療に関心を持つ患者は、専門の医療機関を訪れます。医師とのカウンセリングを通じて、患者の症状や既往歴を詳しく確認し、便移植が適切かどうかを判断します。
次に、患者の腸内フローラバランス検査を実施し、その患者の腸内フローラバランス状況を確認した上で、最適な菌液を調合します。
そして、健康なドナーの選定が行われます。ドナーは厳しいスクリーニングを受け、感染症や消化器疾患のリスクがないことが保証されます。受け入れ可能なドナーが確定したら、便の採取と調製の段階に進みます。
その後、移植の実施に移ります。内視鏡やカプセルを用いて便を患者の腸内に移植します。
治療後は、患者の経過を観察し、症状の変化や腸内環境の改善を評価します。
必要に応じて、追加のサポートやフォローアップが行われ、体調の管理をしっかりと行うことが重要です。
ドナーの選び方
ドナーの選び方は、便移植において非常に重要です。
まず、ドナーは健康であることが必須条件です。これには、感染症や消化器系の病歴がないことを確認するための詳細なスクリーニングが含まれます。
特に、肝炎やHIV、腸管感染症などの病歴について慎重に調査する必要があります。
さらに、ドナーの食生活や生活習慣も考慮されます。
腸内フローラの健康に必要な栄養素を豊富に含む食事を心がけている人が望ましいです。
また、喫煙や過度のアルコール摂取がないことも、ドナーとして好ましい条件となります。
こうしたポイントを踏まえることで、安全で効果的な便移植が実施できるでしょう。
便移植の費用
便移植の費用は、施設や地域によって異なるため、具体的な金額を一概に示すことは難しいでしょう。ただし現在のところ便移植は、保険適用外の自費診療であることから、一般的には数十万円から百万円程度の範囲であることが多く、患者の症状により最終的な移植回数も変わってきます。
便移植を検討する際は、自己負担の金額がどれくらいになるかを事前に確認することが重要です。医療機関に相談し、詳細な見積もりを取ることで、より安心して治療に臨むことができるでしょう。
一般的な費用の目安
一般的な費用の目安を考える際、どの便移植方法を選択するかで、費用も変わります。
例えば、一般財団法人腸内フローラ移植臨床研究会が運営するドナーバンク(https://fmt-japan.org/technical-features/japanbiome)を活用する便移植の場合は、便移植にかかる費用は、医療機関での診察料、腸内フローラ検査費用、移植費用で構成されています。ドナーバンク使用料は移植費用に含まれており、医療用ゴムチューブを用いる移植方法にて数十分で終了するため、入院は不要です。抗生物質の投与も食事制限も必要ありません。
一方で、ドナーバンクを使用しないその他の施設・機関での便移植の場合は、医療機関での診察料や検査費用、処置に伴う入院費用が便移植にかかる費用となります。具体的には、便移植に向けた前処置やフォローアップの診察が必要になる場合が多く、全体の費用が増加することがあります。
また、便の提供に関しても、ドナーバンクを使用しない場合は、ドナーを選定し、その健康状態を調べるための検査が必要です。このため、ドナーに関連する費用は別途かかることが一般的です。
このように最終的な費用は、治療を受ける医療機関の方針や地域の医療環境によって異なるため、事前に詳しい見積もりを行うことが望ましいでしょう。
保険適用の可否
便移植における保険適用の可否は、国や地域によって異なります。
日本では、便移植は保険適用外で、現在のところ100%自己負担となっています。
便移植のリスクと注意点
副作用とリスク
便移植には効果が期待できる一方で、副作用やリスクも存在します。
まず、一般的な副作用として、移植後に下痢や腹痛が起こることもあります。
これらの症状は、腸内フローラが急激に変化することに起因しています。
通常は一時的なものであり、体が新しい腸内環境に適応することで改善しますが、耐え難い場合は医療機関で相談することが重要です。
さらに、便移植のリスクとして懸念されるのが、感染症の可能性です。
特に、ドナーから移植された便に病原体が含まれている場合、感染を引き起こす恐れがあります。
そのため、ドナーの選定と厳格なスクリーニングが必要です。
なお、二親等以内のドナーを自分で見つけることが条件となっている便移植の方法以外にも、前述のドナーバンク(日本初の便バンクであるJapanbiome)を活用する方法もあります。
Japanbiomeでは、厳しいドナー管理が徹底されており、倫理委員会も設置されています。
どの便移植を選択するのかは、個別の状態を考慮した上で、医療従事者との十分な相談を通じて決めていくことが重要です。
注意すべき患者の特徴
便移植を検討する際には、特に注意すべき患者の特徴があります。
まず、免疫抑制剤を服用している患者です。これらの薬剤は感染症のリスクを高めるため、便移植の施行には慎重な判断が必要です。
次に、腸の解剖学的異常がある患者も注意が必要です。
これには、過去の手術歴や先天性の腸疾患が含まれます。こうした患者は、治療の効果が得られにくい場合があります。
さらに、精神的な健康状態も考慮に入れるべきです。
心的な問題を抱える患者は、治療に対する理解や忍耐力が不足することがあります。
医療従事者は、これらの特徴を把握しておくことで、適切な治療方針を策定できるでしょう。
最新の研究と今後の展望
最近の研究成果
最近の研究成果では、便移植が潰瘍性大腸炎の症状緩和に寄与するというエビデンスが増加しています。
また、実施された臨床試験では、便移植を受けた患者の約50%に症状改善があったとの報告もあります。この結果は、従来の治療法に反応しなかった難治性の患者にとって朗報となっています。
がん治療に関しても、便移植が免疫療法の効果を高める可能性が注目されています。腸内環境を改善し免疫応答を強化する働きが期待されており、治療法に対しての安全性や有効性を探る研究が進行中です。
その他にも、複数の臨床試験で成功例が報告されており、便移植は標準治療の一環として位置づけられる可能性が高まっています。2024年8月には、食道がん・胃がん患者さんを対象に 便移植の臨床試験が開始されています。
さらに、最近のデータは、便移植後のがん再発率が低下する可能性を示唆しており、長期的な効果も期待されているのです。
しかし、便移植はまだ新しい治療法であるため、安全性や長期的な効果についてのデータが不足しています。将来的には、これらの課題を解決し、より多くの患者に対して安心して提供できる治療法へと発展していくことが期待されています。
まとめ
便移植は、潰瘍性大腸炎をはじめとする消化器疾患に対して、新しい視点からの治療法として注目されています。
腸内環境を改善することで、症状の緩和につながる可能性があります。多くの研究が進行しており、実践例も増えてきました。
しかし、便移植には注意が必要です。ドナーの選定や感染症のリスク管理など、安全性を確保するためのプロセスが不可欠です。医療従事者との連携も重要であり、治療に対する適切な理解を深めることが求められます。
今後、便移植の効果や適応についての研究が進むことで、患者さんの選択肢が広がることが期待されます。腸内フローラをターゲットにした新しい薬剤や治療法の開発も進む中、便移植はその基盤と位置づけを高めていくと考えられます。
潰瘍性大腸炎に悩んでいる方やそのご家族は、ぜひ医療機関での相談を検討してみてください。
引用文献
1. Allegretti, J. R., Mullish, B. H., Kelly, C., & Fischer, M. (2019).
The evolution of the use of faecal microbiota transplantation and emerging therapeutic indications.
The Lancet, 394(10196), 420–431.
2. Bennet, J. D., & Brinkman, M. (1989).
Treatment of ulcerative colitis by implantation of normal colonic flora.
The Lancet, 1(8630), 164.
3. Cammarota, G., Ianiro, G., Tilg, H., Rajilić–Stojanović, M., Kump, P., Satokari, R., … & Gasbarrini, A. (2017).
European consensus conference on faecal microbiota transplantation in clinical practice.
Gut, 66(4), 569–580.
4. Costello, S. P., Hughes, P. A., Waters, O., Bryant, R. V., Vincent, A. D., Blatchford, P., … & Andrews, J. M. (2019).
Effect of fecal microbiota transplantation on 8-week remission in patients with ulcerative colitis: A randomized clinical trial.
JAMA, 321(2), 156–164.
5. Lopetuso, L. R., Ianiro, G., Allegretti, J. R., Bibbò, S., Gasbarrini, A., Scaldaferri, F., & others. (2020).
Fecal transplantation for ulcerative colitis: Current evidence and future applications.
Expert Opinion on Biological Therapy, 20(5), 343–351.
6. Moayyedi, P., Surette, M. G., Kim, P. T., Libertucci, J., Wolfe, M., Onischi, C., … & Marshall, J. K. (2015).
Fecal microbiota transplantation induces remission in patients with active ulcerative colitis in a randomized controlled trial.
Gastroenterology, 149(1), 102–109.e6.
7. Mullish, B. H., Quraishi, M. N., Segal, J. P., McCune, V. L., Baxter, M., Marsden, G. L., … & Williams, H. R. T. (2018).
The use of faecal microbiota transplant as treatment for recurrent or refractory Clostridium difficile infection and other potential indications: Joint British Society of Gastroenterology (BSG) and Healthcare Infection Society (HIS) guidelines.
Gut, 67(11), 1920–1941.
8. Ooijevaar, R. E., Terveer, E. M., Verspaget, H. W., Kuijper, E. J., & Keller, J. J. (2019).
Clinical application and potential of fecal microbiota transplantation.
Annual Review of Medicine, 70, 335–351.
9. Paramsothy, S., Kamm, M. A., Kaakoush, N. O., Walsh, A. J., van den Bogaerde, J., Samuel, D., … & Borody, T. J. (2017).
Multidonor intensive fecal microbiota transplantation for active ulcerative colitis: A randomized placebo-controlled trial.
The Lancet, 389(10075), 1218–1228.
10. Rossen, N. G., MacDonald, J. K., de Vries, E. M., D’Haens, G. R., de Vos, W. M., Zoetendal, E. G., & Ponsioen, C. Y. (2015).
Fecal microbiota transplantation as novel therapy in gastroenterology: A systematic review.
World Journal of Gastroenterology, 21(17), 5359–5371.