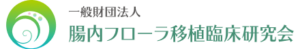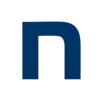赤ちゃんが元気に生まれてくれればなんだっていい。
それはたしかに正論だと思う。
赤ちゃんが危険にさらされるリスクがほんの少しでもあるなら、そしてそのリスクが減らせるなら、帝王切開だって構わない。
帝王切開が最初に行なわれ始めたのは古代ローマ時代。
命がけの出産中に母親が実際に死にかけると、胎児の命だけでも救うために行なわれた措置だった。当然、母親の死亡率はほとんど100%だっただろう。
要は切腹だ。想像するだけで痛すぎる。
麻酔や手術の技術が向上し、帝王切開は胎児だけではなく母親の命も助ける方法になった。
さらには、出産中にトラブルがあった場合には経膣分娩よりも安全な方法として帝王切開が選ばれるようになった。
帝王切開のおかげで、無数の命が助かった。
目次
- 帝王切開の現状
- どうして帝王切開が増えているのか
- 帝王切開とマイクロバイオーム
- 最初の研究
- 最初の研究は正しかったか?
- マイクロバイオーム生態系の立ち上がりが遅くなる
- 帝王切開とマイクロバイオームの両立を目指して
- 膣細菌を赤ちゃんに塗るという方法
- ”vaginal seeding”(膣の種まき)は安全か
・本文中のカッコ付き番号は、記事下部の参考文献の番号を表しています。
・用語解説はこちら(随時更新)
・主要記事マップはこちら(随時更新)
帝王切開の現状
現在日本では、4人に1人の赤ちゃんが帝王切開で生まれてくる。この数字は1990年代の2〜3倍にものぼり、世界の現状とほぼ同じだ。
WHOが推奨する帝王切開率は10〜15%だから、その数字を大きく上回っている。
医療技術や制度の進んでいる先進国たちが、その数字を押し上げているのだろうか?
実はそうでもなく、むしろ発展途上国や新興国で帝王切開率が増えているという現状がある。
エジプトでは、なんと70%以上もの妊婦が望むと望まざるとにかかわらず帝王切開を受けている。(参考:出産の72%が帝王切開 エジプト 医学的に必要ないのに広がる事情:朝日新聞デジタル)
他にもドミニカ共和国、ブラジル、キプロス、トルコなどで50%以上の高い帝王切開率になっている。
日本や世界平均の「20%」という数字がかすんで見えるほどだ。
この状況が続けば、最悪の場合は2030年までに東アジア63%、ラテンアメリカやカリブ海地域で54%、西アジアで50%、北アフリカで48%、南ヨーロッパで47%、オーストラリアやニュージーランドで45%まで数字が上がる可能性があるとWHOは予測している。
Caesarean section rates continue to rise, amid growing inequalities in access
逆に、北欧やオランダでは10%台である。このように国によって差があるということは、医学上の緊急性や必要性とは別のところで帝王切開が選ばれているということが推測できる。
どうして帝王切開が増えているのか
帝王切開には、予定帝王切開と緊急帝王切開がある。
母体や胎児が危険な状態にある場合、お産はしばしば緊急帝王切開に切り替えられる。
母親の年齢や既往症などを考慮して、もしもの場合に帝王切開をすぐに受けられるように大きな病院を産院として選ぶ人も多い。
予定帝王切開も、同様にリスクが高いと判断された妊婦に提案される。
前回のお産が帝王切開だった場合は、そのあとの出産は帝王切開しか選べない病院も多い。前の傷が開いて大量出血するなどのリスクがあると考える医師がいまだに多いからだ。
しかし、現場の医療スタッフの常識がそうだとしても、最新の研究では帝王切開のあとの経膣分娩でそれほどリスクが上がるわけではないということが明らかになっている。
(参考:Vaginal Birth After Cesarean: VBAC: – American Pregnancy Association)
ほかにも逆子や双子、巨大児の場合にも予定帝王切開が選ばれやすい。
医師が予定帝王切開を勧める背景には、実は裏の理由も存在する。
訴訟リスクを回避したい、出産にかかる時間を節約したい、高い手術費用を取れるといったものだ。
リスクが高いからという表向きの理由はあっても、実はすべてのケースで本当に帝王切開が医学的に必要であるというわけではない。
帝王切開を自ら望む母親もいる。
陣痛があまりにも長く耐え難い痛みであるとき、「切ってください」と涙ながらに訴える母親の言葉は、医師の背中を押すだろう。
産休制度が整っていない国や、産休を使えない仕事をしている場合、仕事のスケジュールに合わせて出産したいと望む女性がいてもおかしくない。
そして、予定帝王切開ならば、ずっと担当してくれていた主治医に最後まで見てもらえるというメリットもある。
必要以上に帝王切開が選ばれている現実で、誰かを責めることはおそらくナンセンスだ。
医学的な理由だけではなく、人間社会はさまざまな要素が複雑に絡んでいるのだから。
それでも、帝王切開にはリスクがある。わずかながらメスが赤ちゃんを傷つけたり、呼吸系の障害が残ることもある。
術後の母親の回復には時間がかかる。もちろん、経膣分娩ならリスクがゼロというわけではない。
主治医や妊婦は、それらのリスクを天秤にかける。
近年、帝王切開による長期的なリスクにあるもうひとつの点を加えるべきだという声が上がっている。
腸内細菌たちを中心としたマイクロバイオームの形成だ。
帝王切開とマイクロバイオーム
帝王切開で生まれた赤ちゃんたちは、経膣分娩で生まれた赤ちゃんたちに比べてマイクロバイオームの形成過程に違いがあるのかもしれない。
妊娠中に膣や腸のマイクロバイオームが赤ちゃん向けに変わるのなら、膣を通るプロセスをスキップすることで赤ちゃんが獲得するマイクロバイオームに違いが出るというのは自然な仮説だ。
最初の研究
それを最初に検証したのが、Maria Gloria Dominguez-Bello氏(当時プエルトリコ大学、現ラトガース大学)らの研究チームだ。
2010年に発表された「分娩方法が新生児のさまざまな体の部位において最初のマイクロバイオータの獲得と構成を左右する」と題されたこの研究論文(1)は、生まれたての赤ん坊のマイクロバイオーム(特に腸内細菌)形成における帝王切開の影響を網羅的に検証した最初の研究として位置づけられている。
この研究は、あるハプニングの結果行なわれたものだった。
Dominguez-Bello氏は祖国でもあるベネズエラで20年にわたり、栄養学や微生物学の研究を行っていた。
その時もベネズエラに赴き、ジャングルの奥地で先住民たちの微生物を採取する予定だったのだが、ヘリコプターがキャンセルされてしまった。
ベネズエラの首都で三週間足止めされてしまった彼女は、バカンスを取るよりも「別の研究」に着手することを選んだ。
地元の病院に行って、経膣分娩と帝王切開による分娩で生まれた赤ちゃんたちの細菌にどんな違いがあるか調べることにしたのだ。
この研究には、21歳から33歳まで9人の母親と10人の赤ちゃんが参加し、母親の皮膚、口、膣の細菌や、新生児の皮膚、口、鼻、便(胎便)の細菌が調べられた。
その結果、帝王切開で生まれた赤ちゃんと経膣分娩で生まれた赤ちゃんたちで、それぞれ細菌の構成が大きく異なっていることが示された。
経膣分娩で生まれた赤ちゃんたちは、からだじゅうが母親の膣常在菌で覆われていたのだ。
最初の研究は正しかったか?
この結果は、これに続くさまざまな別の研究者たちによる研究ですべて支持されたわけではない。
生後すぐの赤ちゃんから1歳未満の赤ちゃんまでを対象に、帝王切開による分娩と経膣分娩の差がマイクロバイオームにどのような影響を与えるのか、世界中の研究者が検証を試みた(2)。
その結果は、研究ごとにまちまちだった。
この検証をむずかしくしているいくつかの要因がある。
まず、生まれてから数日、あるいは数ヶ月の赤ちゃんは、マイクロバイオーム(検証対象は細菌)がめまぐるしく変わる。
生まれてから24時間以内に出る「胎便(たいべん)」の腸内細菌の構成は、翌日にはがらりと変わっている。ちなみに胎便は最近まで無菌だと考えられていたが、ある研究では3人に2人の割合で、わずかに検出可能なレベルで細菌が含まれることがわかっている(3)。
第二に、腸内細菌の構成は個人差が大きい。母親が違えば、受け取る細菌も違うのだ。
そして第三に、特に胎便は細菌の数そのものが少ない。解析対象の菌数が少ないと、解析過程でのコンタミネーションなどの影響が大きくなり、結果の信頼性が下がる。
マイクロバイオーム生態系の立ち上がりが遅くなる
それでも、帝王切開で生まれた赤ちゃんは明らかにマイクロバイオームの立ち上がりが遅いことを多くの研究は示唆している。
生態学的な言い方をすれば、生態系が安定するまでに時間がかかる。
特に0歳児に特徴的なビフィズス菌(Bifidobacterium)の増殖が何ヶ月も遅れてしまう。
母乳にはビフィズス菌とその栄養源であるオリゴ糖が含まれているにもかかわらず、帝王切開で生まれた赤ちゃんは母乳を飲んでいてもビフィズス菌がなかなか増えてこない。
これは、生まれる瞬間に母親の便に含まれるビフィズス菌を摂取できないことで、赤ちゃんの未熟な腸マイクロバイオームの生態系の中で別の菌たちが先に増殖を始めてしまい、あとから来たビフィズス菌が増えづらくなってしまっている可能性が考えられる。
両者の違いは、離乳食が始まる生後6ヶ月頃になるとだんだんと消えていくことがわかっている。
そうであっても、未熟な状態で生まれてくるヒトにとって、生後半年ものあいだ一緒にからだづくりをしてくれるメンバーの顔ぶれが違うことは、重要な意味を持つだろう。
では本当に、帝王切開で生まれたことによるマイクロバイオームの「顔ぶれの変更」は、その後の人生に不利益をもたらすのか?
おそらく、かなり確定的に答えはイエスだ。
帝王切開で生まれた赤ちゃんは、生後一年以内に感染症にかかりやすくなる。
病気のリスクは感染症にとどまらない。
小児喘息(4-6)、アトピー(7-9)、アレルギー(8,10)、Ⅰ型糖尿病(11)、炎症性腸疾患(IBD)(5,12)などの免疫応答に関する疾患リスクや、肥満(13)の増加も報告されている。
さらには、学童期において認知能力の発達にも影響をおよぼす(14)ことが示され始めている。
帝王切開とマイクロバイオームの両立を目指して
世界的な帝王切開の割合はうなぎのぼりだと言っていいだろう。
経済的に国全体に大きな負担がかかるうえ、母親の肉体的・精神的負担も大きい帝王切開は、本当に医学的に必要な場合に限るほうがいい。
マイクロバイオームの自然な形成が乱されることと深く関連しているらしいことを踏まえると、余計にその思いは強くなる。
けれど、女性の気持ちを置き去りにしたまま自然分娩信仰を祭り上げるわけにもいかない。
妊娠や出産の過程では、人には言えない心の傷を静かに抱えている女性も多い。
「下から産んであげたかった」
「帝王切開になってしまった」
無事に赤ちゃんが生まれたとしても、何十年もそんな思いを引きずる人もいる。
そんな状況で、赤ちゃんのマイクロバイオーム形成、ならびに将来の健康状態にも悪影響があるかもしれないという知らせは、そんな母親たちを余計に悲しませるだけかもしれない。
でも、科学は常に改善を試みている。ベストではなくとも、ベターな方法を安全に提案するのも、科学の役目だ。
帝王切開で生まれた赤ちゃんに正常なマイクロバイオームを形成してもらおうと、画期的な試みを始めた研究チームがある。
膣細菌を赤ちゃんに塗るという方法
カリフォルニア大学教授(当時コロラド大学教授)のRob Knight氏の娘は、2011年に緊急帝王切開で誕生した。
Knight氏は世界的に著名な微生物学者で、2007年に発足したHuman Microbiome Projectにも主要メンバーとして関わっている。
彼が帝王切開によるマイクロバイオームへの影響を知らなかったはずはない。
実は、Knight氏はその前年に出されたDominguez-Bello氏の論文(前述のベネズエラでの研究)の共同著者としても名を連ねている。
そして彼は、研究者というよりもひとりの父親として行動した。
手術のあと、妻と娘と三人きりになった病室で、彼は妻の膣を綿棒でぬぐって娘の体に塗りつけた。
開腹手術である帝王切開は、当然ながら母親に感染症のリスクがある。
執刀医をはじめとしたスタッフは、自身や器具、部屋の消毒や殺菌を念入りに行なっただろう。生まれてくる赤ちゃんも清潔に取り出されたはずだ。
彼の行為を病院スタッフが知っていたら、決していい顔はしなかっただろう。
けれど父親として娘が将来受けうる不利益をできるだけ避けようとした彼の行動を責めることは、誰にもできないのかもしれない。
この、おそらく世界ではじめての「膣マイクロバイオーム移植」は、どの研究にも含まれていない。研究計画なしの行為だ。
2016年、Dominguez-Bello氏やKnight氏を含む研究チームは、この「膣マイクロバイオーム移植」を帝王切開で生まれた4名の新生児に実施したという論文(15)を出した。
その結果、新生児の体の一部で母親の膣由来のマイクロバイオームが定着し、経膣分娩で生まれた赤ちゃんと同じような構成になったという。
彼らはこの方法を”vaginal seeding”(膣の種まき)と呼び、現在に至るまで着実に研究データ(16,17)を積み重ね続けている。
「この方法はこのようなリスクがある」という事実を明らかにするのも科学の大切な仕事のひとつだが、それが避けられないケースがある場合に「どうすればリスクを少しでも減らせるか」という方法を模索する姿は、研究者としてとても尊敬できる姿勢だ。
彼らは帝王切開の他にも、粉ミルク育児や分娩時の抗生物質の影響をできるだけ避けたり、受けた影響を少なくするための方法を模索している(18)。
”vaginal seeding”(膣の種まき)は安全か
一方で、”vaginal seeding”はまだ効果や安全性、機序がわからない面も多く、実施は慎重になるべきだという声もある。
アメリカ産婦人科学会(American College of Obstetricians and Gynecologists, ACOG)は、”vaginal seeding”はあくまで研究計画に含まれるケースでのみ実施されるべきで、一般的な医療の場や自己判断で行うべきではないとコメントを出している。
(参考:Vaginal Seeding | ACOG)
西オーストラリア大学の研究者らは、2018年に発表した論文(2)内でかなり批判的な立場を取っている。
彼らは帝王切開による分娩と経膣分娩の研究をいくつか取り上げたうえで、両者のマイクロバイオーム形成に本当に差があるのかをまず問題としている。さらに帝王切開そのものではなく、その他の因子に本当の原因がある可能性も考えるべきだと主張する。
帝王切開を余儀なくされた要因(母親側の年齢や疾患、肥満などのリスク因子)、帝王切開の際に服用する抗生物質、陣痛がないこと、母乳の影響、個人間・個人内のマイクロバイオームの多様性などがその因子として考えられるだろう。
別の研究チーム(19)は、これらの因子のうち抗生物質の影響を排除しても両者のマイクロバイオーム形成に明らかな違いがあることを示している。彼らは母乳、きょうだいやペットの有無、産後の入院日数の長さ、おしゃぶりに至るまでさまざまな因子を検討し、
さらには”vaginal seeding”に加え、”fecal seeding”(うんちの種まき)の可能性にすら言及している。
帝王切開はただの「相関」なのかそれとも「原因」なのか。
それを確かめるためには還元主義的な方法を試していくしかないが、無数にある交絡因子をすべて考慮した研究は、相当難しいだろう。
それよりは、完璧なリレーを見せてくれる自然な経膣分娩や母乳育児をなるべく後押しし、それが叶わない場合でも悲観せずにベターな方法を探っていく姿勢を、筆者としては応援したい。
1. Dominguez-Bello MG, Costello EK, Contreras M, et al. Delivery mode shapes the acquisition and structure of the initial microbiota across multiple body habitats in newborns. Proc Natl Acad Sci U S A. 2010;107(26):11971-11975. doi:10.1073/pnas.1002601107
2. Stinson LF, Payne MS, Keelan JA. A Critical Review of the Bacterial Baptism Hypothesis and the Impact of Cesarean Delivery on the Infant Microbiome. Front Med. 2018;5. Accessed October 31, 2023. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmed.2018.00135
3. Hansen R, Scott KP, Khan S, et al. First-Pass Meconium Samples from Healthy Term Vaginally-Delivered Neonates: An Analysis of the Microbiota. PLoS ONE. 2015;10(7):e0133320. doi:10.1371/journal.pone.0133320
4. Debley JS, Smith JM, Redding GJ, Critchlow CW. Childhood asthma hospitalization risk after cesarean delivery in former term and premature infants. Ann Allergy Asthma Immunol. 2005;94(2):228-233. doi:10.1016/S1081-1206(10)61300-2
5. Sevelsted A, Stokholm J, Bønnelykke K, Bisgaard H. Cesarean Section and Chronic Immune Disorders. Pediatrics. 2015;135(1):e92-e98. doi:10.1542/peds.2014-0596
6. Thavagnanam S, Fleming J, Bromley A, Shields MD, Cardwell CR. A meta-analysis of the association between Caesarean section and childhood asthma. Clin Exp Allergy. 2008;38(4):629-633. doi:10.1111/j.1365-2222.2007.02780.x
7. Negele K, Heinrich J, Borte M, et al. Mode of delivery and development of atopic disease during the first 2 years of life. Pediatr Allergy Immunol. 2004;15(1):48-54. doi:10.1046/j.0905-6157.2003.00101.x
8. Bager P, Wohlfahrt J, Westergaard T. Caesarean delivery and risk of atopy and allergic disesase: meta-analyses. Clin Exp Allergy. 2008;38(4):634-642. doi:10.1111/j.1365-2222.2008.02939.x
9. Laubereau B, Filipiak-Pittroff B, Berg A von, et al. Caesarean section and gastrointestinal symptoms, atopic dermatitis, and sensitisation during the first year of life. Arch Dis Child. 2004;89(11):993-997. doi:10.1136/adc.2003.043265
10. Eggesbø M, Botten G, Stigum H, Nafstad P, Magnus P. Is delivery by cesarean section a risk factor for food allergy? J Allergy Clin Immunol. 2003;112(2):420-426. doi:10.1067/mai.2003.1610
11. Cardwell CR, Stene LC, Joner G, et al. Caesarean section is associated with an increased risk of childhood-onset type 1 diabetes mellitus: a meta-analysis of observational studies. Diabetologia. 2008;51(5):726-735. doi:10.1007/s00125-008-0941-z
12. Li Y, Tian Y, Zhu W, et al. Cesarean delivery and risk of inflammatory bowel disease: a systematic review and meta-analysis. Scand J Gastroenterol. 2014;49(7):834-844. doi:10.3109/00365521.2014.910834
13. Darmasseelane K, Hyde MJ, Santhakumaran S, Gale C, Modi N. Mode of Delivery and Offspring Body Mass Index, Overweight and Obesity in Adult Life: A Systematic Review and Meta-Analysis. PLOS ONE. 2014;9(2):e87896. doi:10.1371/journal.pone.0087896
14. Polidano C, Zhu A, Bornstein JC. The relation between cesarean birth and child cognitive development. Sci Rep. 2017;7(1):11483. doi:10.1038/s41598-017-10831-y
15. Dominguez-Bello MG, De Jesus-Laboy KM, Shen N, et al. Partial restoration of the microbiota of cesarean-born infants via vaginal microbial transfer. Nat Med. 2016;22(3):250-253. doi:10.1038/nm.4039
16. Song SJ, Wang J, Martino C, et al. Naturalization of the microbiota developmental trajectory of Cesarean-born neonates after vaginal seeding. Med N Y N. 2021;2(8):951-964.e5. doi:10.1016/j.medj.2021.05.003
17. Mueller NT, Differding MK, Sun H, et al. Maternal Bacterial Engraftment in Multiple Body Sites of Cesarean Section Born Neonates after Vaginal Seeding—a Randomized Controlled Trial. mBio. 2023;14(3). doi:10.1128/mbio.00491-23
18. Mueller NT, Bakacs E, Combellick J, Grigoryan Z, Dominguez-Bello MG. The infant microbiome development: mom matters. Trends Mol Med. 2015;21(2):109-117. doi:10.1016/j.molmed.2014.12.002
19. Reyman M, van Houten MA, van Baarle D, et al. Impact of delivery mode-associated gut microbiota dynamics on health in the first year of life. Nat Commun. 2019;10:4997. doi:10.1038/s41467-019-13014-7
本ブログ記事は、
シンバイオシス株式会社微生物事業部の研究員が
noteにて作成した記事を転記しております。
記事タイトル:帝王切開と自然分娩をマイクロバイオームの視点で考える
記事リンク:https://note.com/symbiosis17/n/nd662182b4ed4?sub_rt=share_pw

出産の現場に医療が介入すればするほど、お産は安全になった。
でも、メリットばかりなのだろうか?
私たちが見落としていることはないのか?
今日は、出産を予定している人たち、その周りの人たち、産婦人科の人たちにぜひ知っていただきたいことを書きます。
今回も長文。
今日は「私って細菌をリレーするために存在しているのかもしれない」と思わせてくれた、出産と菌たちのお話。
目次
- ヒトのかくも完璧な細菌リレー
- 赤ちゃんが受け取るもう1セットの菌たち
- 健やかな出産と育児は菌だらけ?
- 帝王切開と自然分娩をマイクロバイオームの視点で考える
- 早産で生まれた赤ちゃんのマイクロバイオーム
- 出産の現場に登場する抗生物質
- 母親のマイクロバイオームに含まれる細菌以外のメンバーたち
- 参考文献リスト
・本文中のカッコ付き番号は、記事下部の参考文献の番号を表しています。
・用語解説はこちら(随時更新)
・主要記事マップはこちら(随時更新)
ヒトのかくも完璧な細菌リレー
私たちの体は、37兆という膨大な数の細胞が集まってできている。
そしてそれと同じ、もしくはそれ以上の数の細菌や、彼らを含むマイクロバイオームとともに生きている。
菌たちはどこからやってきたのだろう?
卵子と精子が出会った瞬間? それはたぶんちょっと早すぎる。
今のところ、子宮で羊水が破裂するまではほぼ無菌状態なのではないかという見方が強い。赤ちゃんは、まさに生まれる瞬間に母親から細菌を受け取るのだ。
その一連の流れと、その流れの持つ意味を考えてみたい。
まず、正産期に入って出産準備がばっちり整ったと判断すると、母親の体は出産に関連するホルモンを出し始める。
陣痛がはじまり、破水する(陣痛より先に破水する場合もある)。
出産にかかる時間はまちまちだが、赤ちゃんは確実に子宮から膣の出口へ向けて少しずつ降りてくる。
普段はぴっちり閉まっている子宮の入り口が赤ちゃんが通れるほどに大きく開く過程は、言葉では言い表せないくらいのすさまじい痛みを伴う。(が、出産中はそれどころではなく、産後はさらにそれをしんみり思い出すどころではなくなるという)
産道を少しずつ通過していくとき、赤ちゃんはお母さんより前にお母さんの膣内細菌たちに出会う。母親の膣には、妊娠中に「赤ちゃん向け」にカスタマイズされた菌たちが待ち構えている。
その多くは乳酸菌であり、この種類の菌たちは乳酸や抗生物質をつくりだし、他の菌たちが悪さをしないようにしっかり見張る役割を果たす。
乳酸菌は妊娠前から膣の主要メンバーだが、このときはふだん腸に棲んでいる菌たちの一部も膣に移動している。小腸にいて胆汁を分解する酵素を出すラクトバチルス・ジョンソニイという細菌がその好例だ。
赤ちゃんは口を通して乳酸菌たちを自分の消化管に取り込みながら、出口を目指していく。
なぜ膣には乳酸菌が多いのだろう?
その答えは、赤ちゃんが生後どのように栄養を摂取するかを考えれば合点がいく。そう、赤ちゃんは生後半年ものあいだ母乳またはミルクで育つ。母乳の約7%が糖質で、そのほとんどが乳糖として存在する。粉ミルクも同様に作られている場合が多い。
(参考:和光堂レーベンスミルク はいはい|商品紹介|離乳食、粉ミルク、ベビーフードの和光堂)
生まれたばかりの赤ちゃんは、ラクターゼという酵素の活性が高く、乳糖(ラクトース)をグルコースとガラクトースという消化しやすい形の糖に変えることができる。牛乳でお腹を壊す人が多いのは、大人になるとこの酵素の活性が低下するためだ。
赤ちゃんの小腸で消化しきれない乳糖を待ち受けるのが、乳酸菌だ。
へその緒から受け取っていた栄養の代わりに母乳を飲むようになる赤ちゃんのために、その栄養を余すところなく吸収できるようにお母さんが手渡す置き土産が乳酸菌たちなのだ。
赤ちゃんが受け取るもう1セットの菌たち
実は、赤ちゃんが受け取るのは膣の細菌だけではない。
生まれる瞬間、赤ちゃんは母親の背中側に顔を向けて出てくる。
膣のすぐ後ろに肛門が位置しているのは、偶然なのだろうか?
進化生物学の博士号を取り、サイエンスライターとして活躍するアランナ・コリンは著書の中でこう述べている。
子宮収縮ホルモンの作用と降りてくる胎児の圧力を受けて、陣痛中や出産時にほとんどの女性は排便する。赤ん坊は顔を母親のお尻の側に向けて頭から先に出てくる。そして母親がつぎの陣痛に備えて体を休めているあいだ、赤ん坊の頭と口はうってつけの位置に来る。あなたは本能的に顔をしかめるかもしれないが、これは幸先のいいスタートだ。母から子への最初の贈り物、糞便と膣の微生物が無事に届けられることになるのだから。
これは進化的に「適応した」誕生だ。肛門が膣口のすぐそばにあるのも、子宮収縮ホルモンが直腸を刺激して排便を促すのも、別段悪いことではない。自然選択は、それが赤ん坊の役に立つから選んだのだろう。少なくとも害にはならないから排除しなかった。
『あなたの体は9割が細菌: 微生物の生態系が崩れはじめた』P300
無我夢中で出産する女性たちは、自分の股が裂けていることにも気づかない。当然、排便をした感覚などない。便はすぐにスタッフの手で処理されるし、排便したことをからかう人もいない。
しかし、出産前に浣腸処理をする産院は少なくない。妊婦が恥ずかしくないようにという配慮として、赤ちゃんが受け取るはずの腸内細菌たちが赤ちゃんが出てくるよりも先に出てきてしまう。
ここまで読んでくださった読者のみなさんなら、「そんなもったいないことを」と思ってもらえるだろうか。
健やかな出産と育児は菌だらけ?
赤ちゃんのマイクロバイオームの住まいはもちろん消化管だけではない。
皮膚にはじまり生殖器、呼吸器、わずかではあるが血液中に至るまで文字通り微生物たちが覆っていく。彼らは目に見えない。でもたしかにそこにいるのだ。母親から赤ちゃんへの菌のリレーを科学的に検証した論文(1)もどんどん出てきている。
生まれたあとも、赤ちゃんは家族の手や口、ベッドの手すりやお風呂の水などから、どんどんルームメイトを見つけていく。
公衆衛生の概念が人々のあいだに広まって以降、殺菌・消毒は「すればするほどいい」という考えを持つ人も多い。
実際、パンデミック以降はどこにでも当たり前にアルコール消毒のスプレーが置かれるようになった。
出産の現場では医療スタッフが入念に消毒を行い、生まれた赤ちゃんは写真映えがするようにすぐにきれいに拭き取られる。
その中には、有用な成分や膣の細菌を含み、赤ちゃんを危険な細菌から守ってくれる「胎脂(たいし)」と呼ばれる膜も含まれる。
きれいにすることに益はあっても害はない。そう信じられてきた衛生観念を考え直すときが来ている。
実際、お産の前の浣腸を実施しない産院もかなり増えている。また、生まれた赤ちゃんを軽く拭き取る程度にして、沐浴は3〜4日待ってからおこなう「ドライテクニック」という方法も注目されはじめている。
帝王切開と自然分娩をマイクロバイオームの視点で考える
経膣分娩(自然分娩など)と並んで、少なくない人が経験するのが帝王切開による出産だ。
出産におけるリスクを少しでも下げるため、実は帝王切開は本当に必要な数以上に行われている。
母体への負担も大きいが、生まれてくる胎児へのリスクはないのだろうか?
マイクロバイオームの視点で帝王切開を考えてみたい。
↓文字数が多すぎるので、記事を分けます。
https://note.com/embed/notes/nd662182b4ed4
早産で生まれた赤ちゃんのマイクロバイオーム
妊娠中の母親の体は、出産予定日に向けて膣や腸のマイクロバイオームを変化させていく。
もしその日が早まったとしたら、赤ちゃんへ届ける予定だったマイクロバイオームの内容は少々変更されるかもしれない。
36週6日までに生まれた赤ちゃんを早産児と呼ぶ。
早産の場合は赤ちゃんのほうも体が未熟で、うまくマイクロバイオームを形成できない可能性も考えられる。
研究の現場でも、早産児の腸内細菌たちは、一般的に「形成が遅く」「種数が少なく」「多様性や豊富さに欠ける」ということが徐々に明らかになってきている(2)。
早産児はしばしば抗生物質のお世話になることも多いが、早産児に対するバンコマイシンの投与が腸神経系の発達に影響をおよぼすという研究報告(3)もある。
細菌たちへの影響も考えると、抗生物質使用の短期的メリットと長期的デメリットは十分に考慮されるべきだろう。
妊娠前の母親の膣マイクロバイオームも、早産に影響している可能性がある。
大人の女性では、膣のマイクロバイオームの生態系が月経によるホルモンバランスの変化などの影響を受けて時期によって大きく変わる。
その変化を含めて、膣の生態系はおおむね5つのタイプ(コミュニティ・ステート・タイプ、CSTs)に分けられるが、そのうちタイプⅣの生態系では乳酸菌ではなくプレボテラ属などの細菌が優位に見られる。
近年、このタイプⅣの膣マイクロバイオームを持つ女性は、早産のリスクが高まるのではないかといった研究(4)も進んでいる。
出産の現場に登場する抗生物質
妊娠中の服薬に過剰なまでに慎重になる妊婦は多い。
一方で、医師は妊婦に与えても胎児への影響が少ないであろうという薬の一覧を持っている。
抗生物質の一部は、そんな「安全リスト」に入っており、妊婦に対して気軽に抗生物質が投与されるケースは実は多い。
「このお薬は赤ちゃんに影響がありませんから安心してください。むしろ、お母さんが感染症などにかからず元気で過ごすほうが赤ちゃんにとって大事ですから、飲み切ってくださいね」
医師のこの言葉は、母親の背中を優しく押してくれる。けれど、出産のそのときに母親が渡すはずの細菌一式が受ける影響は考慮されていない。
B群溶血性連鎖球菌。
このものものしい名前のついた細菌はGBSと一般的に呼ばれ、妊婦にはなじみのある呼び名だ。全妊婦の10-20%が常在細菌として持つこの細菌は、何も悪さをしない普通の細菌だ。
通常、妊婦自身にはなんの自覚症状もない。
けれど、この細菌は出産時に赤ちゃんに伝播する可能性が40%ほどあり、さらにそのうち250-800分の1の確率で赤ちゃんが敗血症や肺炎、髄膜炎を起こす可能性がある。そのうち死亡率は10%にのぼる。
日本では、すべての妊婦を対象にGBSの検査を妊娠35〜37週におこなっている。陽性だった場合、陣痛が起こると同時に妊婦に抗生物質が点滴投与される。
常在細菌であるGBSが赤ちゃんに移行するリスクを下げるためだ。
この措置は完全ではないが、たしかにリスクを下げることができるらしい。
けれど、抗生物質が母親の常在細菌にあたえる影響や、その細菌たちを受け取る赤ちゃんたちへの影響へ思いを巡らせると、果たしてその措置は正しいのだろうかと首を傾げざるを得ない。
GBS陽性の母親から生まれた赤ちゃんが死亡する確率は、6,000-20,000分の1だ。この数字をどう捉えるかは、人によるだろう。
けれど、GBSが陽性の場合に医師からこの細菌のリスクを知らされたら、ほとんどなんのためらいもなく抗生物質投与に同意するだろう。
ひとりしかいない我が子が、その20,000分の1になるかもしれないのだ。そのリスクを減らせる方法として、抗生物質投与で失うものはなにもない。
ここまで読んでいただいた読者のみなさんは、失うものだらけだとういうことがわかっていただけるだろう。
実は、筆者自身の出産もこのケースに該当している。
当時は今ほど細菌のことをわかっていなかったとはいえ、いちおう腸内細菌の仕事をしている身だったので、かなり悩んだ。
けれど、抗生物質投与を当たり前の事実として医師に告げられ、ほんのわずかでも娘が死んでしまうリスクがある状況に、私は勝てなかった。
娘は健康にすくすく育っているが、軽度の牛乳アレルギーがある。
いまでも、あのときの自分の選択が正しかったのかどうか、私には正直自信が持てない。
短期的で確率の低い重大なリスクと、長期的で確率の高い比較的軽微なリスクを並べられたら、私たちはどうすればいいのだろう。
覚えておくべきことは、20,000分の1のリスクのために、19,999人の赤ちゃんがはからずも「抗生物質処理済み」の母親のマイクロバイオームを受け取ってしまったという事実だ。
母親のマイクロバイオームに含まれる細菌以外のメンバーたち
以前の記事で述べたようにマイクロバイオームという言葉の定義には、細菌やその他の微生物だけが含まれるわけではない。遺伝子の断片やウイルス、代謝産物も含まれる。
母親からリレーされるのは、細菌だけではないのだ。最近の研究では、母親から赤ちゃんへ遺伝子の断片が水平伝播しているという報告(5)もある。
妊娠と出産で母親がリレーするのは、次世代のヒトの命だけではないのだ。
そこには細菌、ウイルス、遺伝子、そのほか私たちがまだ知らないさまざまなものがリレーされ、それらは少しずつ変化しながら進化の原動力となっていく。
科学技術が微生物の姿を目に見えるかたちで映し出す前から、私たちの先祖たちは彼らと共存し、ともに進化してきた。
目に見えず、手で触れない存在を現代の私たちはうまく信じることができなくなっている。
けれど、どんな科学技術をもってしてもマイクロバイオームの全体を完璧に把握することは難しいだろう。
私たちはもっと、目に見えないものの力を信じてみるべきなのかもしれない。
※無事に赤ちゃんにリレーされたあとの菌たちの活躍についてはこちら。
https://note.com/embed/notes/n7c6008904c33
参考文献リスト
1. Bogaert D, van Beveren GJ, de Koff EM, et al. Mother-to-infant microbiota transmission and infant microbiota development across multiple body sites. Cell Host Microbe. 2023;31(3):447-460.e6. doi:10.1016/j.chom.2023.01.018
2. Cuna A, Morowitz MJ, Ahmed I, Umar S, Sampath V. Dynamics of the preterm gut microbiome in health and disease. Am J Physiol – Gastrointest Liver Physiol. 2021;320(4):G411-G419. doi:10.1152/ajpgi.00399.2020
3. Schill EM, Joyce EL, Floyd AN, et al. Vancomycin-induced gut microbial dysbiosis alters enteric neuron-macrophage interactions during a critical period of postnatal development. Front Immunol. 2023;14:1268909. doi:10.3389/fimmu.2023.1268909
4. Charbonneau MR, Blanton LV, DiGiulio DB, et al. Human developmental biology viewed from a microbial perspective. Nature. 2016;535(7610):48-55. doi:10.1038/nature18845
5. Vatanen T, Jabbar KS, Ruohtula T, et al. Mobile genetic elements from the maternal microbiome shape infant gut microbial assembly and metabolism. Cell. 2022;185(26):4921-4936.e15. doi:10.1016/j.cell.2022.11.023
本ブログ記事は、
シンバイオシス株式会社微生物事業部の研究員が
noteにて作成した記事を転記しております。
記事タイトル:出産前にどうか知っていてほしい。母から子への菌リレーのこと。
記事リンク:https://note.com/symbiosis17/n/nd5df05396bc2?sub_rt=share_pw

妊娠を経験した人、もしくは近くにそんな人がいるなら覚えがあるかもしれないが、妊娠すると劇的に体が変わる。
つわりの有無や、お腹が大きくなっていくというだけではなく、体調もメンタルもすさまじく変わる。
ホルモンバランス、免疫機能、代謝機能もその一部だ。
実際にお腹が膨らんでいくまではなかなか実感しづらいところがあるが、妊娠した瞬間から、妊婦の体もマイクロバイオームも「妊娠モード」にばっちり切り替わる。
そう、私たちの体と菌たちは共同で出産への準備を整えていく。
マイクロバイオームを赤ちゃんに手渡すだけではなく、赤ちゃんを健康に育てていくために(1)。
今日は、妊娠すると体のマイクロバイオーム(細菌)がどう変わるのか、そして赤ちゃんによりよい細菌を渡すためにできることはあるのか、科学的にわかっていることを紹介したい。
この記事に妊娠中のことを全部をまとめたので、かなり長文です。腰を据えて読んでください。
目次
- 妊娠前のマイクロバイオームは赤ちゃんに影響する?
- 妊娠後期のマイクロバイオームと代謝機能
- 妊娠合併症とマイクロバイオーム
- 妊娠糖尿病(gestational diabetes mellitus, GDM)
- 妊娠高血圧腎症(preeclampsia, PE)
- その他
- 妊娠後期のビフィズス菌・乳酸菌増加現象
- 妊婦のマイクロバイオームと赤ちゃんの健康
- 神経の発達
- 代謝系の発達
・本文中のカッコ付き番号は、記事下部の参考文献の番号を表しています。
・用語解説はこちら(随時更新)
・主要記事マップはこちら(随時更新)
妊娠前のマイクロバイオームは赤ちゃんに影響する?
出産の高齢化などによって、妊娠するために「妊活」を行う夫婦が増えている。
単に避妊をやめるだけではなく、食事、睡眠、運動などの生活習慣を整えることで妊娠しやすくなると考えられており、不妊治療の前にまずは取るべき行動とされている。
では、妊娠前のマイクロバイオームは妊娠のしやすさ、妊婦・胎児の健康に影響するのだろうか?
残念ながら、この分野の研究はまだまだ未開拓だ。
現在、膣のマイクロバイオーム(1)や腸のマイクロバイオーム(2)と不妊の関係を調べる研究が進んでいる。
また、IBD(炎症性腸疾患)患者の妊娠時の腸内細菌を調べる研究(3)もある。先にネタバラシをすると、IBD患者は妊娠すると炎症レベルが下がり、妊娠が進むにしたがって腸内細菌の多様性が健康な妊婦に近い状態になった。
このことは、IBD患者にとって妊娠は安全で、自身の健康へのメリットさえあるかもしれないことを示している。
いずれにせよ、マイクロバイオームと妊婦や胎児の健康を議論するには、妊娠前のマイクロバイオームの影響も考慮する必要があるということが言える程度だ。
妊娠後期のマイクロバイオームと代謝機能
コーネル大学(当時、現マックスプランク生物学研究所の微生物学部長)のRuth E Ley氏は、自身の出産の直後に妊娠とマイクロバイオームの関係を研究し始めた。
彼女が率いる研究チームが2012年に発表した論文(4)は、妊娠とマイクロバイオームの関係を探る研究分野でランドマーク的な存在となっている。
フィンランドの妊婦91人を対象にしたこの研究では、妊娠後期の女性の腸内細菌叢が糖尿病や肥満など代謝異常系疾患の患者のそれと驚くほど似ていることが示された。
妊娠後期は水を飲むだけで太る、というのは妊婦たちの悩みの種だ。けれどそれは、赤ちゃんを守るためのメカニズムなのかもしれない。
ただし、この変化は妊娠時の一時的なものであって、たとえば肥満患者で起こっている脂肪蓄積のメカニズムとは違う可能性もある。非常に面白い論文なので、以下に要点をまとめてみたい。
- 妊娠初期(T1)の腸内細菌叢は健康な非妊娠時のものに似ている。
- 妊娠後期(T3)は腸内細菌の多様性が低くなる。
- T3ではインスリン抵抗性が高まり、高血糖状態となり、炎症性のマーカーが上昇した。この軽度の炎症が腸内細菌の構成を変え、妊婦の代謝を出産へ向けて変えているのではないか。
- T3は妊婦同士で腸内細菌の構成の違いが大きくなるが、概してプロテオバクテリア門とアクチノバクテリア門の細菌が増えていた。前者は炎症との関連が知られ、後者はビフィズス菌を含むグループである。逆に、抗炎症との関連が知られるフィーカリバクテリウム属の細菌は減っていた。
- ただし、生まれた子どもの腸内細菌叢は母親のT1のものに近くなっていく。
- T3期のマイクロバイオームを無菌マウスに移植したところ、T1期の細菌を移植されたマウスに比べて体重の増加と高血糖が見られた。
この論文の成果は、妊娠時に胎児へ効率的にエネルギーを補給するために、マイクロバイオームが一役買っていることを示したことだった。
しかしこの妊婦と菌たちの連携プレーがうまくいかないと、さまざまな妊娠合併症を引き起こす可能性がある。
妊娠合併症とマイクロバイオーム
妊娠中は免疫力をあえて下げることで、胎児を体の中にとどめておく仕組みが知られている。
そのため、妊婦は感染症に気をつけなければならない。場合によっては、胎児にまで細菌やウイルスが届いてしまう場合もある。
1391名の妊婦を対象にしたマラウイでの研究(5)では、絨毛羊膜炎などの感染症が低体重児の出産につながるという結果も出ている。
日本では、感染症以上に多くの妊婦が気にしているのは体重管理ではないだろうか。
「体重が増えすぎると妊娠糖尿病になりますよ」だとか、「産道に脂肪がつくと難産になりますよ」と医師にアドバイスされた人は少なくないだろう。
マイクロバイオームたちが妊娠中の代謝機能を調節しているのなら、菌たちの構成と妊娠合併症も大きく関連があるはずだ。
妊娠糖尿病(gestational diabetes mellitus, GDM)
日本では、10%前後の妊婦に妊娠糖尿病(GDM)の診断がつく。
本来は赤ちゃんのためにエネルギーの吸収効率を上げようとする働きに、妊婦自身の体が耐えられなくなって起こる。
GDMとマイクロバイオームの関連を探る研究はいくつかあり、特定の細菌の増減や特定の遺伝子の増減が観察されている。GDM患者では、マイクロバイオームの変化によってドーパミンが不足したり、短鎖脂肪酸のバランスが崩れたり、代謝性の炎症が起こることも示されている。
2023年に発表された非常に興味深い論文(6)では、44人のGDM患者のデータと無菌マウス実験の結果を統合している。前述のRuth Ley氏の研究室で学んだOmry Koren氏(現バル=イラン大学)の研究室による成果だ。
彼らは、臨床データやマイクロバイオームの構成をもとに、妊娠初期の段階からGDMのリスクを予測したり、GDMリスクを下げられる可能性を示している。
彼らは細菌だけではなく、その他の微生物やウイルス、代謝産物などを含めたマイクロバイオーム全体がGDMの原因になっている可能性も同時に指摘している。
妊娠高血圧腎症(preeclampsia, PE)
妊娠高血圧腎症(PE)とマイクロバイオームに関する文献は非常に少ない。けれど、PE患者では腸内細菌の多様性が低下していたり、日和見病原体と呼ばれる潜在的な病原体が増えているケースが報告されている(7)。
さらに、PE患者の便マイクロバイオームをマウスに移植すると、血圧上昇や蛋白尿が引き起こされたことから、マイクロバイオームの変化は結果ではなく原因と言えそうだ。
その他
妊娠時のトラブルとマイクロバイオームの関係を調べたものは、上記に挙げたGDMかPEに関するものがほとんどだが、早産や原因不明の流産との関連も調べられ始めている。
妊娠後期のビフィズス菌・乳酸菌増加現象
胎児は、お母さんのお腹の中でお母さんから栄養をもらって10ヶ月間をかけて成長する。
お母さんたちは、そのときが来たらただ赤ちゃんを体の外に出すだけではない。一緒に手土産も渡すようなのだ。
妊娠中のマイクロバイオームの変化が、妊婦や妊娠中の胎児の成長だけではなく、生まれてくる瞬間・生まれた後の赤ちゃんのためにもなっているという証拠がいくつもある。
前述のOmry Koren氏の研究室の成果をまたひとつ紹介したい。
妊娠後期になると、母親の腸内細菌の構成は大きく変わる。個人差が大きくなり、多様性が低下する。
ただし、共通点もある。ビフィズス菌(Bifidobacterium)、ブラウティア属(Blautia)、コリンセラ属(Collinsella)などの細菌が増えるのだ。このうち、ビフィズス菌はマウスでも妊娠中に増加する細菌だ。
著者らは、妊娠期間を通じて高い水準を保つホルモンのひとつであるプロゲステロンに注目した。プロゲステロンがビフィズス菌の増殖を促している可能性はないだろうか?
結果、この仮説は大正解だった。
プロゲステロンを投与したマウスの便ではビフィズス菌が増加した。さらには、便そのものにプロゲステロンを添加して培養したところ、それでもビフィズス菌が増えるという結果になった。
妊娠中に増えるプロゲステロンが、ビフィズス菌を増やしているのは間違いなさそうだ。
この結果は、何を意味しているのだろうか?
ビフィズス菌は、ヒトの健康に有益な菌として知られている。免疫力の強化、体重増加の調整、インスリン感受性とグルコース耐性の向上などによって妊婦自身にメリットは多いだろう。
それ以上に魅力的な説明がある。
ビフィズス菌は、経膣分娩により生まれた赤ちゃんのお腹にまで届く。そして、ビフィズス菌は母乳に含まれるオリゴ糖(HMOs)の消化に必要不可欠なメンバーなのだ。
へその緒から切り離された赤ちゃんが、母乳からしっかり栄養を吸収できるよう、妊娠後期の母親の腸内細菌はしっかり準備を始めているのだ。
そしてもちろん、ビフィズス菌は赤ちゃんの免疫形成にも役立つだろう。
マウス実験では確かめられなかったブラウティア属、コリンセラ属などの細菌も、それぞれに理由があって増えているに違いない。
マイクロバイオームの変化は、腸内細菌だけに限らない。
赤ちゃんの出口である膣でも、細菌の構成が大きく変わる。住んでいる国や人種によっても大きく差があり一概には言えないが、乳酸桿菌が非常に優勢になり、多様性が下がることが研究で報告(8,9)されている。
乳酸桿菌は、自身の出す乳酸によって周りの環境を酸性に傾ける。これによって、他の細菌が増殖できなくなり、産道を通ってくる赤ちゃんを感染症から守ってくれる。
出産を控えて細菌の多様性が下がってしまったのではない。あえて多様性を狭め、赤ちゃんの誕生に最適な細菌を優位にしているのだ。
妊婦のマイクロバイオームと赤ちゃんの健康
母親のマイクロバイオームが生まれてくる赤ちゃんに及ぼす影響は他にもある。
神経の発達
カリフォルニア大学のHelen E. Vuongらは、マウスを使った実験により母親の腸内細菌が胎児の神経発達に大きな役割を果たしていることを示した(10)。この結果は、胎児のふるまいに影響を与えるだろうと予測された。
そして翌年、オーストラリアのディーキン大学Peter Vuillermin氏らの研究チームが行った大規模なコホート研究(11)によって、この予測は正しいと証明された。
213名の母親と215名の子どもが参加したこの研究では、妊娠後期の母親の腸内細菌の多様性と、生まれた子どもが2歳に達したときのChild Behavior Checklist (CBCL) のスコアに相関関係を見出した。
ただ、215名の子どものうち2歳時点でチェックリストにひっかかったのは20名のみだったので、より大規模なコホート研究が必要ではあるが。
代謝系の発達
他にも、腸内細菌の産生する短鎖脂肪酸などを含む代謝系への影響を示す研究(12)もある。
こちらは、日本の研究なので日本語の要約も参考にしていただければと思う。
妊娠中の食物繊維摂取は胎児の代謝機能の発達を促し、出生後、子の肥満になりにくい体質をつくる
アレルギーの予防
他には、プレボテラ・コプリという細菌が食物アレルギーのリスクを下げる可能性があるかもしれないことを示す論文(13)も出ている。
インスリン抵抗性などと関連しているとされ、悪者扱いされがちなこの細菌が、生まれてくる子どもを守っているかもしれないのだ。
特定の細菌を一概に悪者扱いすることの不合理性を示すいい例だろう。
これらの研究はいずれも、出産時に母親のマイクロバイオームが赤ちゃんに移行することを前提としている。
つまり、経膣分娩(自然分娩)による微生物の伝達だ。
子宮で育つ赤ちゃんは無菌で、産道を通る際に初めて細菌と出会うというのがとりあえずの通説だ。
けれど、近年の研究では子宮も無菌ではない可能性があることが示されている(14)。一方で、生まれてくるまでは赤ちゃんはやはり無菌だという説(15)も根強い。
経産婦のマイクロバイオームは第二子に有利?
ブタを使った研究で、出産回数が多くなると早くマイクロバイオームの組成が変わったという研究(16)もある。
胎内にいるうちから母親のマイクロバイオームの恩恵を受けているとしたら、第二子以降のほうがその恩恵には与りやすいのかもしれない。
妊娠中の生活習慣と赤ちゃんの健康
妊娠中のマイクロバイオームが赤ちゃんにとってそんなに大切なら、心がけひとつでマイクロバイオームを少しでもいい状態にすることはできるのだろうか?
結論は、どうもある程度はできるらしい。
妊娠中は生活習慣を整えましょうとよく言われるが、その根拠のひとつにマイクロバイオームを加えたら、やる気アップにつながるだろうか。
妊娠中の食生活とマイクロバイオーム
私たちの体は食べたものでできている。
あらゆる分野で繰り返されるこのフレーズは、たしかに真理の一面をあらわしている。
私たちの食べたものはどの程度マイクロバイオームに影響するのだろうか?
食事でマイクロバイオームを良い方向に変えられるかどうかの議論は、まだ割れている。それは、妊娠中の食事に関しても同じことだ。
けれど、母親のマイクロバイオームが出産時に赤ちゃんに移行することを考えると、妊娠中にできるだけ良いマイクロバイオームを準備したいと願うお母さんたちのための食生活アドバイスがあってもいいはずだ。
妊娠中の食生活と、妊婦自身や生まれてくる赤ちゃんのマイクロバイオームへの影響を調べた研究は、少ないながらもいくつか報告されている。
その中で、腸内細菌を対象にした7つの研究を包括的にまとめた論文(17)では、高脂肪食や食物繊維の摂取と腸内細菌への影響が考察されている。
他の研究としては、オメガ3脂肪酸やポリフェノールに注目した研究(18)や、乳製品、魚介類、果物等の摂取に注目した研究(19)もある。
マイクロバイオームに関する研究ではないが、2023年7月に発表された山梨大学のエコチル調査甲信ユニットセンター(山縣然太朗氏ら)による研究発表(20)が非常に有意義なので紹介したい。(日本語版要約はこちら)
「妊娠中の母親の食物繊維摂取と3歳時の発達との関連について」と題されたこの研究は、環境省の「子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)」に参加している約7万6千組の母子を対象にしている。
その結果、妊娠中の食物繊維摂取量が少ない母親から生まれた子どもは、多い母親の子どもと比べて3歳時のコミュニケーション能力、微細運動能力、問題解決能力、個人・社会能力において発達に遅れが出やすい傾向にあることが示された。
この結果には、腸内細菌を含めたマイクロバイオームの影響がかなり関係していると推測するのは難しくない。上述したディーキン大学のPeter Vuillermin氏らの研究を補完する結果と言えるだろう。
山梨大学の研究グループは同年1月にも、たんぱく質摂取に関して同様の結果を発表(21)している。(日本語版要約はこちら)
結局、バランスの取れた食事をしっかり摂ることが大切ということかもしれない。
科学というものは、ただ観察された事実だけを述べる。そこからどうするのかは、広い視点と自分が信じられるかどうかで選んでいくしかない。
赤ちゃんのためにできることがあるなら少し食事に気をつけよう、くらいの気持ちで聞いていただくのがいいだろう。
この他にも、妊婦自身がもともと持っているマイクロバイオームの影響や、分娩方法による違いもある。
現代女性は痩せ志向の人が多いため、妊婦の痩せすぎが問題にもなっている。妊娠中は適切な範囲で体重をきっちり増加させることも推奨されている。
マイクロバイオームばかりを見て、他の要素を無視していては、木を見て森を見ずだ。最適な食生活というのは、個人差も大きいし、同じ人間でもその時々によって変わるだろう。あくまでも、妊娠・非妊娠時にかかわらず健やかな食生活を目指したい。
ちなみに筆者は、つわりで痩せ、妊娠中期に一気に太り、後期づわりで上げ止まったため、目標増加体重に届かなかった。おそらくそれが原因で(という論文をいくつか読んでいたため)娘が低体重児ギリギリで生まれてしまい、しばらく申し訳なさで自己嫌悪の日々を送った(そして産後になって今更という感じで食欲が爆増した)。
いくら知識があっても、妊娠は思い通りにいかない。ストレスにならない範囲でのんびり取り組むことをおすすめする。
その他の生活習慣
食事以外の生活習慣については、まだまだ研究が進んでいない。
健康食品の代表選手であるプレバイオティクスやプロバイオティクスは、あれだけ大きく健康効果が宣伝されていながら、実は多くの研究でその効果の是非については意見が割れている。
妊娠中の効果についても同様で、(19)の研究をまとめた論文(22)でも明らかな相関関係はみられなかったという。
妊娠糖尿病や妊娠高血圧腎症などの妊娠合併症との関連について1440名の妊婦を対象とした研究(23)でも、プロバイオティクスは妊娠糖尿病のリスクを下げないどころか、妊娠高血圧腎症のリスクを上げる可能性すらあることを指摘している。
これを受けて英国の非営利団体であるコクランは、妊娠中にプロバイオティクスを使用することに対して注意喚起を発表した。(Cochrane Update 2021: Probiotics Use in Pregnancy for the Prevention of Gestational Diabetes – The ObG Project )
母親のもともとのBMIや、妊娠中の体重増加が赤ちゃんに与える影響に関しては、研究によって意見が割れている。
喫煙は妊娠中の禁忌とされているが、マイクロバイオームへの影響という点でも悪影響がありそうだ。
そして、薬の使用。妊娠中は服薬にかなり気を遣う人は多いが、抗生物質や胃薬、下剤、糖尿病治療薬、プレバイオティクス、プロバイオティクスなどの服用についても様々な研究が進んでいる。
妊婦や胎児の健康を守るために薬が必要になることはある。胎児への暴露やマイクロバイオームへの影響は確かにしっかり考慮しなければいけないが、妊娠中でも服薬可能な薬は多くある。
主治医に相談しながら、あくまでも慎重な姿勢で服薬するのが大切だろう。かくいう筆者も、妊娠時は酸化マグネシウム(便秘薬)やアセトアミノフェン(解熱鎮痛薬)にお世話になった。
参考文献リスト
1. Vitale SG, Ferrari F, Ciebiera M, et al. The Role of Genital Tract Microbiome in Fertility: A Systematic Review. Int J Mol Sci. 2022;23(1). doi:10.3390/ijms23010180
2. Komiya S, Naito Y, Okada H, et al. Characterizing the gut microbiota in females with infertility and preliminary results of a water-soluble dietary fiber intervention study. J Clin Biochem Nutr. 2020;67(1):105-111. doi:10.3164/jcbn.20-53
3. Giessen J van der, Binyamin D, Belogolovski A, et al. Modulation of cytokine patterns and microbiome during pregnancy in IBD. Gut. 2020;69(3):473-486. doi:10.1136/gutjnl-2019-318263
4. Koren O, Goodrich JK, Cullender TC, et al. Host Remodeling of the Gut Microbiome and Metabolic Changes during Pregnancy. Cell. 2012;150(3):470-480. doi:10.1016/j.cell.2012.07.008
5. Doyle RM, Harris K, Kamiza S, et al. Bacterial communities found in placental tissues are associated with severe chorioamnionitis and adverse birth outcomes. PLoS ONE. 2017;12(7):e0180167. doi:10.1371/journal.pone.0180167
6. Pinto Y, Frishman S, Turjeman S, et al. Gestational diabetes is driven by microbiota-induced inflammation months before diagnosis. Gut. 2023;72(5):918-928. doi:10.1136/gutjnl-2022-328406
7. Chen X, Li P, Liu M, et al. Gut dysbiosis induces the development of pre-eclampsia through bacterial translocation. Gut. 2020;69(3):513-522. doi:10.1136/gutjnl-2019-319101
8. Romero R, Hassan SS, Gajer P, et al. The composition and stability of the vaginal microbiota of normal pregnant women is different from that of non-pregnant women. Microbiome. 2014;2(1):4. doi:10.1186/2049-2618-2-4
9. MacIntyre DA, Chandiramani M, Lee YS, et al. The vaginal microbiome during pregnancy and the postpartum period in a European population. Sci Rep. 2015;5(1):8988. doi:10.1038/srep08988
10. Vuong HE, Pronovost GN, Williams DW, et al. The maternal microbiome modulates fetal neurodevelopment in mice. Nature. 2020;586(7828):281-286. doi:10.1038/s41586-020-2745-3
11. Dawson SL, O’Hely M, Jacka FN, et al. Maternal prenatal gut microbiota composition predicts child behaviour. EBioMedicine. 2021;68:103400. doi:10.1016/j.ebiom.2021.103400
12. Kimura I, Miyamoto J, Ohue-Kitano R, et al. Maternal gut microbiota in pregnancy influences offspring metabolic phenotype in mice. Science. 2020;367(6481):eaaw8429. doi:10.1126/science.aaw8429
13. Vuillermin PJ, O’Hely M, Collier F, et al. Maternal carriage of Prevotella during pregnancy associates with protection against food allergy in the offspring. Nat Commun. 2020;11(1):1452. doi:10.1038/s41467-020-14552-1
14. Funkhouser LJ, Bordenstein SR. Mom Knows Best: The Universality of Maternal Microbial Transmission. PLOS Biol. 2013;11(8):e1001631. doi:10.1371/journal.pbio.1001631
15. Kennedy KM, Gerlach MJ, Adam T, et al. Fetal meconium does not have a detectable microbiota before birth. Nat Microbiol. 2021;6(7):865-873. doi:10.1038/s41564-021-00904-0
16. Berry ASF, Pierdon MK, Misic AM, et al. Remodeling of the maternal gut microbiome during pregnancy is shaped by parity. Microbiome. 2021;9(1):146. doi:10.1186/s40168-021-01089-8
17. Maher SE, O’Brien EC, Moore RL, et al. The association between the maternal diet and the maternal and infant gut microbiome: a systematic review. Br J Nutr. 2023;129(9):1491-1499. doi:10.1017/S0007114520000847
18. García-Mantrana I, Selma-Royo M, González S, Parra-Llorca A, Martínez-Costa C, Collado MC. Distinct maternal microbiota clusters are associated with diet during pregnancy: impact on neonatal microbiota and infant growth during the first 18 months of life. Gut Microbes. 2020;11(4):962-978. doi:10.1080/19490976.2020.1730294
19. Lundgren SN, Madan JC, Emond JA, et al. Maternal diet during pregnancy is related with the infant stool microbiome in a delivery mode-dependent manner. Microbiome. 2018;6(1):109. doi:10.1186/s40168-018-0490-8
20. Miyake K, Horiuchi S, Shinohara R, et al. Maternal dietary fiber intake during pregnancy and child development: the Japan Environment and Children’s Study. Front Nutr. 2023;10:1203669. doi:10.3389/fnut.2023.1203669
21. Miyake K, Mochizuki K, Kushima M, et al. Maternal protein intake in early pregnancy and child development at age 3 years. Pediatr Res. 2023;94(1):392-399. doi:10.1038/s41390-022-02435-8
22. Jarde A, Lewis-Mikhael AM, Moayyedi P, et al. Pregnancy outcomes in women taking probiotics or prebiotics: a systematic review and meta-analysis. BMC Pregnancy Childbirth. 2018;18(1):14. doi:10.1186/s12884-017-1629-5
23. Davidson SJ, Barrett HL, Price SA, Callaway LK, Nitert MD. Probiotics for preventing gestational diabetes. Cochrane Database Syst Rev. 2021;(4). doi:10.1002/14651858.CD009951.pub3
本ブログ記事は、
シンバイオシス株式会社微生物事業部の研究員が
noteにて作成した記事を転記しております。
記事タイトル:妊婦さん必読【どこよりも詳しい】妊娠中の腸内細菌の変化
記事リンク:https://note.com/symbiosis17/n/n946cebb74766?sub_rt=share_pw

コアラの主食は毒である
主にオーストラリアに生息するコアラは、ユーカリの葉を食べて生きている。その葉は多くの動物にとって毒であり、私たちが食べるとお腹を壊してしまうし、もちろん栄養にもならない。
コアラの肝臓はユーカリの毒に強いが、栄養を引き出すための酵素を出す遺伝子はどこにも持っていない。
秘密は2メートルもある盲腸に棲む微生物(細菌)にある。
彼らはユーカリの葉の毒を解毒する成分を出しつつ、そこから栄養を引き出してくれるため、コアラたちはユーカリの葉で生きていくことができる。
資源が有限な地球に住む動物にとって、他の動物が食べられないものを栄養源にできるというのは、生き残りにかなり有利に働く。

コアラの赤ちゃんはお母さんのうんち?を食べる
コアラにとって生命線であるこの細菌たちを、生まれたばかりのコアラはまだ持ち合わせていない。
コアラの子どもも、ヒトと同じくかなり未熟な状態で生まれてくる。
生後すぐから母親のお腹の袋に入り母乳だけを飲んでいた子コアラは、生後8ヶ月頃からユーカリを食べ始める。
その数週間前、母コアラが「そろそろ母乳だけで育てる時期が終わったな」と判断すると、自分の盲腸で作った「パップ」と呼ばれる黄緑色のやわらかい物質を肛門から出して子コアラに与える。
これは母コアラが通常するうんちとは別もので、子コアラにユーカリの消化を助けてくれる細菌と消化途中のユーカリの葉を渡すことを目的として作られている特別製のうんちだ。
この素晴らしい天然の離乳食のおかげで、子コアラの腸には微生物と一緒に、微生物がそこで増えていくための食事も届けられることになる。
有益な細菌そのもの(プロバイオティクス)と、細菌のエサ(プレバイオティクス)が両方含まれている、シンバイオティクスの究極例だろう。

いろんな生きものたちが菌のリレーをしている
植物(のセルロースという成分、多くの哺乳類が分解できない)を栄養源とするために微生物の力を借りる方式は、コアラだけではなくウシやヒツジも採用している。
コアラの例はやや特殊ではあるけれど、他の哺乳類も同じように産まれてくる子どもに微生物のセットを渡している。
経膣出産やその後の授乳を通して、赤ちゃんは母親の膣、腸、皮膚などの微生物を獲得していく。
そのような「微生物の垂直伝播(菌のリレー)」は、出産行為に伴って結果として生じているだけなのだろうか?
哺乳類以外の生き物にも目を向けてみよう。
カメムシやツツジコブハムシは、産卵後の卵の表面に糞を塗りつける。卵から孵った子は、自動的に母親の微生物を受け取れる仕組みだ。
ゴキブリやカエルも同じようなことをする。
つまり、確認されているだけでもかなり多くの生物にとって、微生物は子孫にたまたま引き渡されるのではなく、積極的に伝えられているようなのだ。
この事実は、進化学的に考えると合点がいく。
地球にはじめて誕生した生命は今の原核生物(細菌や古細菌)に似ていると考えられているし、すべての動植物は体内外にいる微生物と共生することで今のかたちに進化してきた。
つまり、自分の遺伝子だけではなく自分の微生物をも含めて子どもに渡すことで、ほんとうの意味での生殖が完了するのかもしれない。
こういった菌リレーを先祖代々続けてきた動物たちには、私たちヒトももちろん含まれている。
今の人類に近い形になってからの何千世代、何万世代だけではなく、おそらく最初の最初から。
次に私たちヒトの出産と微生物の関係を紹介したいところだが、その前に妊娠期間中の腸内細菌に目を向けてみたい。
妊娠中に腸内細菌が母体にどのような変化を起こすのか、また妊娠中の生活習慣がどのように腸内細菌に影響を与えるのか。

本ブログ記事は、
シンバイオシス株式会社微生物事業部の研究員が
noteにて作成した記事を転記しております。
記事タイトル:動物たちの母子菌リレーから学ぶマイクロバイオームの垂直伝播
記事リンク:https://note.com/symbiosis17/n/n4301c7b3c7d8